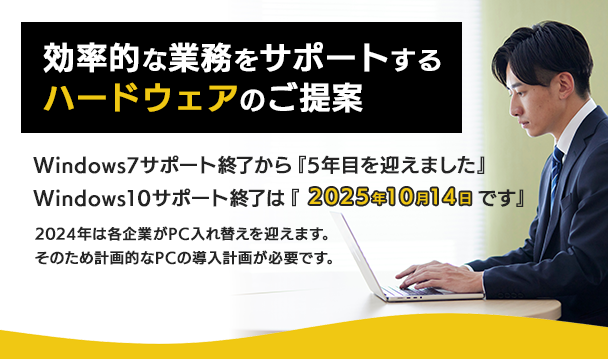住民税は地方税の一種で、行政サービスに必要な経費を住民の能力(給料の多さなどの「担税力」)に応じて負担する税金です。このうち、個人が負担するものを「個人住民税」、法人が負担するものを「法人住民税」といいます。会社員の場合、個人住民税は会社が給与から天引きして納税しており、これを「特別徴収」といいます。
※出典:東京都主税局「個人住民税」
人事/労務給与 2020/06/09
個人住民税の特別徴収、新年度分の納入は6月からスタート

企業によっては、経理担当者が経理業務のほかに人事労務の作業を行っている場合も多いのではないでしょうか。人事労務の重要な業務のひとつに「給与計算」がありますが、その一環で欠かせないのが「個人住民税」に関する処理です。原則、企業は社員の個人住民税を特別徴収する必要があり、毎年6月は新年度の個人住民税の特別徴収が始まる時期です。今回は、個人住民税の概要と特別徴収の流れについて解説します。
個人住民税とは
個人住民税の納付方法の種類
個人住民税の納付方法は「普通徴収」と、先述した「特別徴収」の2種類に大別できます。
普通徴収
納税者自らが納付する方法で、主に個人事業主が対象となります。納付のタイミングは市区町村から送られてくる納税通知書に従い、年4回に分けられています。
副業している会社員など、給与以外の所得がある人も、確定申告時に「普通徴収」を選択することができますが、所属する会社からの給与しか受け取っていない場合は、原則として、社員の意思で普通徴収を選択することはできません。
特別徴収
会社員、パート、アルバイトなどの「給与所得者」に代わり、勤務先の会社が給与から差し引いて納入する方法です。
納入のタイミングは、6月から翌年5月にかけて毎月です。また、地方税法第321条の4の規定によって、会社は社員の個人住民税の「特別徴収義務者」と定められています。これにより、社員や会社の意思は関係なく、会社は社員の個人住民税を特別徴収しなければなりません。
普通徴収
納税者自らが納付する方法で、主に個人事業主が対象となります。納付のタイミングは市区町村から送られてくる納税通知書に従い、年4回に分けられています。
副業している会社員など、給与以外の所得がある人も、確定申告時に「普通徴収」を選択することができますが、所属する会社からの給与しか受け取っていない場合は、原則として、社員の意思で普通徴収を選択することはできません。
特別徴収
会社員、パート、アルバイトなどの「給与所得者」に代わり、勤務先の会社が給与から差し引いて納入する方法です。
納入のタイミングは、6月から翌年5月にかけて毎月です。また、地方税法第321条の4の規定によって、会社は社員の個人住民税の「特別徴収義務者」と定められています。これにより、社員や会社の意思は関係なく、会社は社員の個人住民税を特別徴収しなければなりません。
特別徴収による納税の流れ
特別徴収の税額は、市区町村側が社員それぞれの前年1月~12月までの所得をもとに計算します。算出された金額を、その年の6月~翌年5月に会社が社員から徴収し、市区町村に納入するという流れです。
■特別徴収と会社、社員、市区町村の役割
この流れにおいて経理担当者の実務となり得るのは、1月の年末調整の期限までに給与支払報告書を提出することです。 それ以降は、5月に送られてきた特別徴収税額通知書の「毎月の天引き額」の通りに、毎月の給料から住民税を差し引く作業が必要になります。
また、住民税の納入は、特別徴収税額通知書に添付されている12カ月分の納付書を用います。納入方法は「市区町村の窓口に直接納入」、「金融機関からの振り込み」の2種類がありますが、一部の銀行が提供している「特別徴収地方税納入サービス」を利用することで、自動的に毎月の納入額を自社の口座から引き落とすこともできます。
なお、納入期限は税金徴収月の翌月10日なので、6月に天引きした住民税は7月10日が納入期限です。
■特別徴収と会社、社員、市区町村の役割
- 会社(給与支払者)が給与支払報告書を作成し、市区町村に提出(1月)
- 給与支払報告書をもとに市区町村が税額を算出
- 市区町村が「特別徴収税額通知書」を会社に郵送(5月)
- 通知書に則り、会社が個人住民税を社員(納税者)から徴収
- 6月~翌5月までの給与支払時に、会社が社員から該当の税額を差し引く
- 徴収した税金を、翌月10日までに会社が市区町村へ納入
この流れにおいて経理担当者の実務となり得るのは、1月の年末調整の期限までに給与支払報告書を提出することです。 それ以降は、5月に送られてきた特別徴収税額通知書の「毎月の天引き額」の通りに、毎月の給料から住民税を差し引く作業が必要になります。
また、住民税の納入は、特別徴収税額通知書に添付されている12カ月分の納付書を用います。納入方法は「市区町村の窓口に直接納入」、「金融機関からの振り込み」の2種類がありますが、一部の銀行が提供している「特別徴収地方税納入サービス」を利用することで、自動的に毎月の納入額を自社の口座から引き落とすこともできます。
なお、納入期限は税金徴収月の翌月10日なので、6月に天引きした住民税は7月10日が納入期限です。
個人住民税の納期の特例

■納期の特例を受けるための要件
- 給与の支払いを受ける者(正社員、パート、アルバイトなど)の人数が常時10人未満
- 納入先である市区町村の住民税に滞納がない
- 特例の取り消しから1年以上経過済み
※参考例:中野区「特別区民税・都民税 特別徴収税額の納期の特例について」
住民税の納入業務を負担に感じている場合、以上の要件を満たしていれば納入にかかる時間を6分の1にすることができます。検討してみてください。
**********