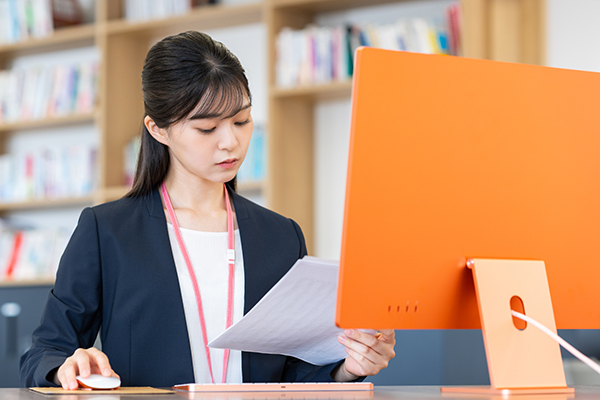まずは海外子会社と海外支店の基本的な違いを見ていきましょう。
法人格の有無
海外子会社と海外支店の最大の違いは、法人格の有無です。
海外子会社は、現地で独立した法人格を持つ「現地法人」であり、日本の親会社とは別法人として扱われます。
一方、海外支店は法人格を持たず、日本本社の一部門として機能するものです。
この法人格の有無が税務・法務・実務のすべての根本的な違いにつながります。
税務上の扱い
法人格の違いは、税務上でも重要な意味を持ちます。
海外子会社
海外子会社は、現地法人としてその国の会計基準に基づいて帳簿を作成し、発生した利益に対して現地で法人税を納める義務があります。
海外支店
海外支店は現地で事業活動を行う拠点ではありますが、恒久的施設(Permanent Establishment:PE)として認定されない限り、現地では課税対象となりません。
PE認定とは、外国企業が現地において継続的な事業活動を行う「恒久的施設」を有すると判断され、その国で課税権が生じる状態を指します。
例えば、これまで出張ベースで行っていた活動に加え、現地にオフィスなどの物理的な拠点を設けた場合、その国でPEと認定される可能性が高まります。
その結果、現地で法人税などの納税義務が発生する場合があります。
ただし、PEの定義や課税基準は国ごとに異なるため、事前の慎重な検討が必要です。
ガバナンスや実務対応への影響
法人格を持つかどうかはガバナンスや実務対応にも影響します。
海外子会社
海外子会社の場合は、現地での取締役会の設置・開催、決算書の作成・提出など、独立した法人としての手続きが求められます。
海外支店
海外支店は日本本社の一部であるため、本社の規程や決裁ルールをそのまま適用できることが多く、組織運営の面では比較的シンプルです。
手続きやコスト
海外子会社と海外支店では、手続きやコストも異なります。
設立手続きと初期コスト
初期コストの観点では、海外支店よりも海外子会社の方が事前準備や書類作成の負担が大きいことが一般的です。
海外子会社
海外子会社を設立する場合は、現地法に基づいた法人設立手続きが必要です。
具体的には、定款の作成、登記、資本金の払込、現地での銀行口座開設、必要な許認可の取得などが求められます。
初期コストは安くても数十万円、場合によっては数百万円以上かかることがあり、設立までの期間も3~6カ月程度を見込む必要があります。
また、国によっては現地の弁護士や会計士の関与が義務付けられている場合もあり、これら専門家への報酬も別途発生します。
さらに、資本金の払込に関しても、国によっては事業開始前に一定額を現地銀行口座へ振り込む必要があるため、進出時にはまとまった余剰資金を用意することが求められます。
海外支店
海外支店の場合は、新たに法人を設立するわけではないため、手続きは比較的簡単です。
初期コストは数十万円程度で済むことが多く、設立期間も1~3カ月程度と短く抑えられます。
ただし、海外支店であっても、日本本社の取締役情報の提出や、登記簿謄本の英訳などが必要となる場合もあるため、本社側での準備作業が一定程度発生することになります。
維持コスト
設立時だけでなく、年間の維持コストも考慮が必要です。
海外子会社
現地での会計帳簿作成、税理士報酬、登記維持費用などが毎年発生します。
海外支店
上記のコストを比較的抑えられる場合が多いとされています。
会計処理や決算業務での違い
海外子会社と海外支店では、日常的な会計処理や決算業務の進め方が大きく異なります。
海外子会社
海外子会社の場合は、現地の会計基準に基づく決算書の作成が必要です。
現地基準で財務諸表を作成した後、日本の親会社の会計基準に合わせて連結財務諸表を作成します。
この過程では、子会社から提出される連結パッケージ(連結用報告資料)を基に、為替換算や内部取引の消去などの連結調整を行います。
これらの作業は専門性が高く、手作業では時間や労力がかかるため、連結会計システムの導入による効率化が有効です。
現地データの効率的な収集、組替調整の自動化、為替レートの一元管理などが可能になり、連結決算を迅速化できます。
海外支店
海外支店の場合は、本社決算に直接合算されます。
本支店間取引については相殺・消去が必要ですが、連結財務諸表を作成する必要はありません。
決算書は本社と支店を合わせた単一の財務諸表としてまとめられるため、本社の会計システムで一元管理することもでき、シンプルに対応できます。
ただし、支店であっても現地での税務申告義務が発生する場合もあるため注意が必要です。
支店が現地でPE認定されると、現地税法に基づく所得計算・税務申告書の提出が必要となります。
この時、日本側で外国税額控除の適用を受けるためには、現地で納付した税額を正確に把握し、日本の法人税申告書に適切に反映させる必要があります。
海外子会社と海外支店の基本的な違いのまとめ
ここまでの内容を整理すると、海外子会社と海外支店の違いは以下のようにまとめられます。
| 項目 |
海外子会社 |
海外支店 |
| 法人格 |
法人格あり |
法人格なし |
| 設立コスト |
数十万~数百万円 |
数十万円~ |
| 設立期間 |
3~6カ月程度 |
1~3カ月程度 |
| 決算方式 |
連結財務諸表の作成が必要 |
本社決算に合算 |
| 撤退の難易度 |
手続きが複雑 |
比較的容易 |
※実際は国・進出形態により大きく異なるため、あくまでも一例となります。
申告書作成から電子申告までトータルサポート
税務システム
MJSの税務システムなら、「豊富な機能」・「高い操作性」・「システム連携」で税務(申告)を大幅に効率化します。税制改正や環境変化にも柔軟に対応します。
海外子会社として海外進出する際、税務面で有利に進めるためには、以下のような日本の税制における優遇措置を理解し、適切に活用することが重要です。
外国子会社配当益金不算入制度
外国子会社配当益金不算入制度は海外子会社が活用できる代表的な制度です。
この制度を利用すると、一定の要件を満たす海外子会社から受け取った配当金の95%が日本で益金不算入となり、配当時の税負担を大幅に軽減することが可能になります。
ただし、制度の適用を受けるには以下のような要件を満たす必要があります。
- 日本の親会社が、対象となる海外子会社の株式を25%以上保有していること
- 上記の株式を6カ月以上継続して保有していること
これらの条件を満たす場合に限り、日本で受け取った配当の95%が益金不算入となります。
つまり、日本での課税対象となるのは残りの5%のみとなり、国際的な二重課税を回避しつつ、税負担を最小限に抑えることができます。
※参考資料:国税庁「第1 法人税基本通達関係」
外国税額控除
外国税額控除は、日本法人が海外で得た所得に対して二重課税が発生するのを防ぐための制度です。
日本法人が海外で事業活動を行う場合、現地で発生した所得は日本本社の所得と合算され、日本でも課税対象となります。
しかし、同時に現地国でも課税が行われると、同一の所得に対して日本と現地の両方で課税される「二重課税」が生じてしまいます。
この重複課税を調整するため、外国税額控除制度では、海外で発生した所得に対して、現地で納めた法人税額のうち一定額を、日本で納める法人税額から控除することができます。
例えば、海外支店で1,000万円の利益が発生し、現地の法人税率が20%の場合、現地で200万円の税金を納めることになります。
日本の法人税率が30%の場合、日本では1,000万円に対して300万円の税額が計算されます。
この時、外国税額控除の制度を適用すると、日本で納める法人税から現地で納めた200万円を控除することができます。
結果として、日本での追加納税は100万円で済み、全体の税負担は合計300万円(現地200万円+日本100万円)となります。
ただし、外国税額控除には限度額があるため、限度額を超える外国税額は、原則として控除できない点に注意が必要です。
※参考資料:税務研究会「法令集 法人税法 第69条 外国税額の控除」
海外子会社として海外進出する際には、活用できる税制だけでなく、注意すべき税制もあります。
外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)
外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)は、海外子会社で税負担割合が低い会社がある場合、その子会社で発生した利益を日本の親会社の所得に合算して日本で課税する制度です。
この制度は、課税逃れが目的でない正当な海外進出であっても適用される可能性があります。
特に、シンガポールや香港など法人税率の比較的低い国では、通常の事業活動であっても外国子会社合算税制の対象となる場合があるため注意が必要です。
実務的には、以下の点を確認することが重要です。
- 現地オフィスの有無、従業員数などを含めた事業の実態に関する内容
- 進出予定国の法人税率が20%未満かどうか
これらの情報を定期的に確認し、外国子会社合算税制の適用リスクがないかを毎年判断する必要があります。
※参考資料:財務省「外国子会社合算税制の概要」
移転価格税制
移転価格税制は、親子会社間の取引について、第三者間取引と同等であることを求める制度です。
グループ内取引では価格を自由に設定できるため、例えば利益の出ていない海外子会社に対して通常より低い金額で販売することも可能です。
しかし、このような取引は移転価格の観点から租税回避と見なされるおそれがあり、税務調査で指摘を受けた場合には、第三者間価格で再計算(更正)され、多額の追徴課税が発生することがあります。
日本法人と海外子会社は別法人であるという原則を忘れず、価格設定を慎重に行うこと、継続的な取引については取引内容を文書化し、必要に応じて専門家の意見を得ることが重要です。
※関連記事:相互関税で日本に24%上乗せ?トランプ関税と併せて見直したい関税の経理実務
申告書作成から電子申告までトータルサポート
税務システム
MJSの税務システムなら、「豊富な機能」・「高い操作性」・「システム連携」で税務(申告)を大幅に効率化します。税制改正や環境変化にも柔軟に対応します。
最後に海外進出時の管理における注意点と、海外子会社と海外支店、どちらの進出形態を選択するかの判断ポイントを解説します。
海外進出時の注意点
海外子会社や海外支店の管理には以下のようなリスクがあるため、対策の検討が必要です。
不正リスク
日本本社の監督が十分でないと、売上の過大・過少計上や、本来不要な高額支払いなどの不正が発生する可能性があります。
こうしたリスクを防ぐには、ガバナンス体制の整備が欠かせません。
月次での財務報告を義務付け、予算と実績に乖離がある場合はその理由を報告させたり、日本本社の担当者が定期的に現地を訪問し、会計処理の適正性や業務プロセスの有効性を確認したりなど、内部統制の仕組みを構築しましょう。
為替変動リスク
現地通貨で発生した売上や費用は、最終的に円換算して日本の財務諸表に反映されるため、為替レートの変動によって現地業績と日本での数値が乖離することがあります。
経理担当者としては、現地通貨の為替動向を定期的にモニタリングし、為替差損益の処理方針を事前に把握しておくことが大切です。
※関連記事:その為替差益、実は課税対象かも!為替差益の課税ルールを個人・法人別にスッキリ整理!
進出形態の判断ポイント
海外子会社と海外支店、どちらの形態とするか判断する際は、以下の内容を参考にしましょう。
海外子会社
海外子会社が適しているのは、黒字化が見込まれる場合や、進出国の税率が日本より低い場合、あるいは大規模な事業展開を予定している場合です。
ただし、子会社を設立した場合は、連結決算業務が必要となるため、経理システムや人員体制が対応可能かを事前に確認しておく必要があります。
海外支店
海外支店は、管理がシンプルで初期費用や運営コストを低く抑えられるため、海外進出の初期段階に最適です。
例えば、小規模な市場テストや現地調査を目的とした進出が適しているでしょう。
ただし、海外支店は法人格を持たないため、大規模な商取引や長期的な投資活動には不向きです。
まずは海外支店で進出し、事業が軌道に乗り、継続的な黒字が見込まれる段階になったら、海外子会社への移行を検討するというように段階を踏むとよいでしょう。
これらのポイントを踏まえ、自社の事業規模・目的・リスク許容度に応じて最適な形態を選択することが、海外進出を成功に導く第一歩となります。
ただし、業種によっては、法規制などにより海外法人がないと営業自体が認められない場合もあります。
自社の進出目的や事業内容に応じて、最適な形態を慎重に判断することが重要です。
※本記事の内容は掲載日時点での情報です。
申告書作成から電子申告までトータルサポート
税務システム
MJSの税務システムなら、「豊富な機能」・「高い操作性」・「システム連携」で税務(申告)を大幅に効率化します。税制改正や環境変化にも柔軟に対応します。