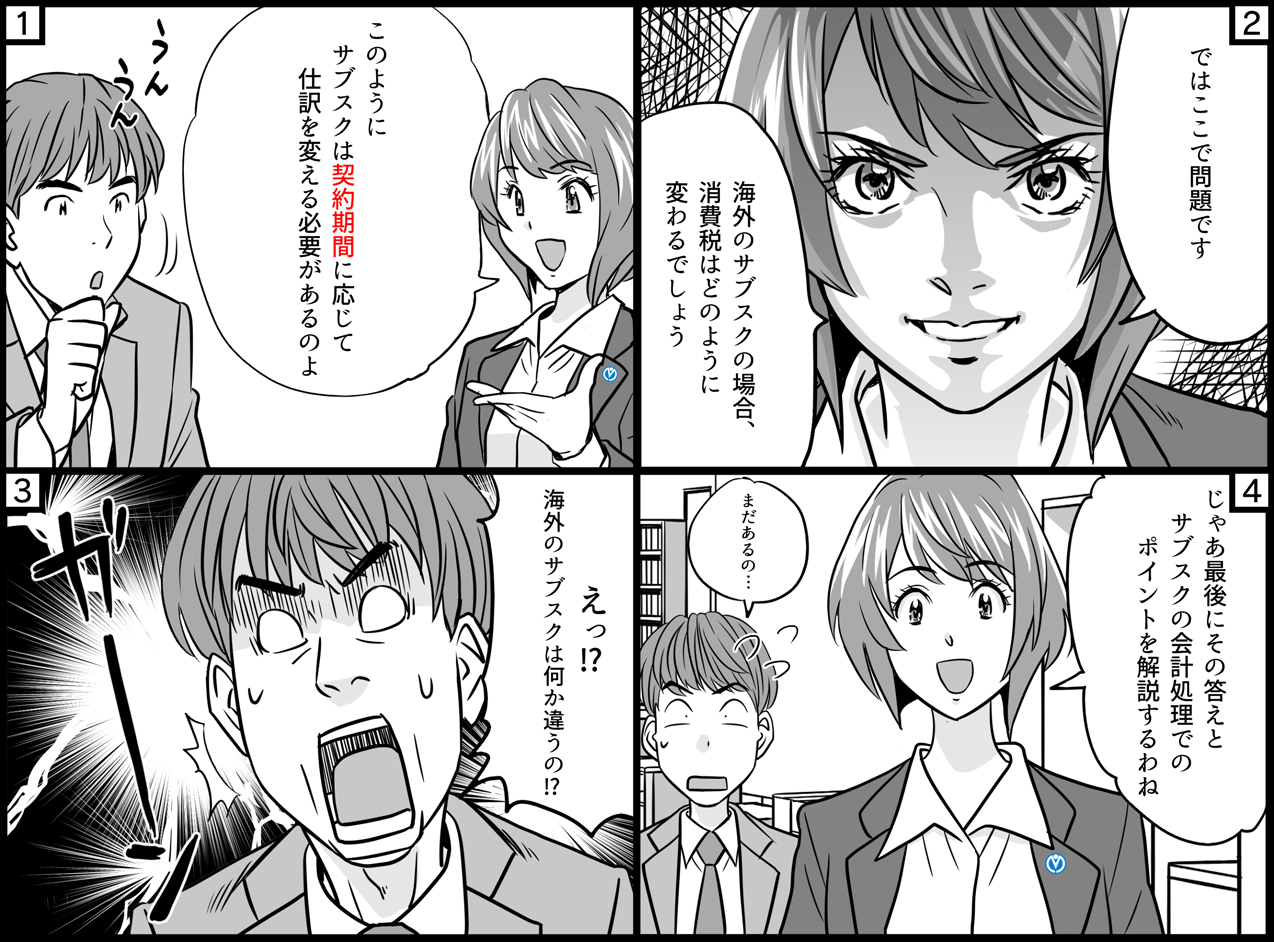近年では、個人や法人を問わず、多様なサブスクリプションサービスが普及し、企業での利用機会も増えています。
一方で、サブスクリプション契約に伴う会計処理に戸惑う経理担当者も多いのではないでしょうか。
業務に関連するものであれば費用として計上できますが、商品やサービスの内容に応じて適切な勘定科目を選ぶ必要があり、処理が複雑化するケースも少なくありません。
今回の記事では、サブスクリプションに用いる勘定科目や具体的な仕訳例を解説します。
サブスクリプションとは
サブスクリプションとは、一定の月額または年額の料金を支払うことで、継続的に特定のサービスや製品を利用できる契約形態です。
契約期間中はサービスを自由に利用でき、必要に応じて解約が可能である柔軟性が特徴です。
初期費用を抑えて必要な期間だけ利用できる点が評価され、企業でも導入が進んでいます。
代表的なサブスクリプションの例としては、Appleが提供する保証サービス「AppleCare+(アップルケアプラス)」が挙げられます。
Apple製品には、購入後1年間のハードウェア保証と90日間の無償テクニカルサポートが標準で付いています。
さらにAppleCare+に加入することで、保証とサポート期間が延長され、過失による損傷や盗難・紛失への補償などが追加されます。
サブスクリプションの会計処理に使う勘定科目
業務に関連するサブスクリプションの料金は、費用として計上できます。
ただし、どの勘定科目を使用すべきかについては、法令上で明確に定められているわけではありません。
そのため、契約内容や用途に応じて、適切な勘定科目を選ぶ必要があります。
サブスクリプションの会計処理でよく用いられる勘定科目には、以下のようなものがあります。
| 勘定科目 |
内容 |
サブスクリプションの具体例 |
| 修繕費 |
ソフトウェアやハードウェアの保守契約に関連するサービス |
AppleCare+ |
| システム使用料 |
インターネットや通信に関連するサービス |
クラウド会計ソフト |
| 支払手数料 |
アプリやソフトウェアなどの利用料 |
クラウドストレージ |
| 消耗品費 |
事務用品やソフトウェアのサブスクリプションに関連するサービス |
文房具の定期購入 |
| 広告宣伝費 |
マーケティング活動に関連するサービス |
SEOツール |
| 福利厚生費 |
社員向けサービスやプログラムに関連するサービス |
オンライン学習サービス |
| 雑費 |
他の勘定科目に当てはまらない少額の経費 |
ー |
会計業務を効率化!
かんたんクラウド会計
電子帳簿保存法・電子取引に対応!スタートアップの方、中小企業・小規模事業者の方に最適!クラウドだからこそ実現するプロから選ばれる会計・給与ソフトをだれでも簡単に!
サブスクリプションの仕訳例
ここでは、サブスクリプションに関する具体的な仕訳例を紹介します。
今回は、クラウドストレージサービスを利用したケースを想定し、「支払手数料」を勘定科目として処理する例について解説します。
月額プランの場合
月額制のサブスクリプションサービスを利用している場合は、毎月の支払いごとに費用を計上します。
例えば、月額5,000円のプランでクラウドストレージを利用している場合、以下のように仕訳します。
| 借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
| 支払手数料 |
5,000 |
普通預金 |
5,000 |
一括払いで契約期間が1年以下の場合
契約期間が1年以下のサブスクリプションを一括払いで支払った場合、会計上はサービスの提供期間にわたって費用が発生すると考えられるため、原則として「前払費用」として処理します。
その後、契約期間に応じて毎月費用として按分し、計上していきます。
例えば、1年契約のサブスクリプションを一括で12万円支払った場合、以下のように仕訳します。
初回の支払時
| 借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
| 前払費用 |
120,000 |
普通預金 |
120,000 |
毎月の費用計上(1カ月分:10,000円)
| 借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
| 支払手数料 |
10,000 |
前払費用 |
10,000 |
ただし税務上では、継続的に提供される1年以内の契約サービスに同様の処理を行う場合、「短期前払費用の特例」の適用が認められます。
この特例を利用すれば、前払費用として計上した金額の全額を、支払った年度の損金に算入することができます。
「短期前払費用の特例」の要件
- 継続的に役務の提供を受ける契約であること
- 支払日から1年以内にサービス提供が完了すること
- 毎期継続して同様の会計処理・税務処理を行っていること
※参考資料:国税庁「短期前払費用の取扱いについて」
一括払いで契約期間が1年以上の場合
契約期間が1年以上にわたるサブスクリプションを一括で支払った場合は、まず支払時に「前払費用」として資産計上し、その後、契約期間に応じて費用を分割して計上します。
例えば、2年契約で24万円を一括払いした場合、以下のように仕訳します。
初回の支払時
| 借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
| 前払費用 |
240,000 |
普通預金 |
240,000 |
毎月の費用計上(1カ月分:10,000円)
| 借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
| 支払手数料 |
10,000 |
前払費用 |
10,000 |
会計業務を効率化!
かんたんクラウド会計
電子帳簿保存法・電子取引に対応!スタートアップの方、中小企業・小規模事業者の方に最適!クラウドだからこそ実現するプロから選ばれる会計・給与ソフトをだれでも簡単に!
サブスクリプションを会計処理する際のポイント
サブスクリプションの会計処理を行う際のポイントを詳しく解説します。
消費税法上の課税区分の確認
消費税法上、サブスクリプション契約における課税区分は、サービス提供者の所在地や取引内容によって異なります。
主に以下の2つのケースに分けて対応が必要です。
国内事業者から提供されるサブスクリプション
日本国内の事業者から提供されるサブスクリプションサービスには、通常、消費税(10%)が課税されます。
なお、仕入税額控除の可否などは相手先がインボイス発行事業者かどうかによって異なります。
海外事業者から提供されるサブスクリプション
国外の事業者から提供される電子サービス(SaaS・クラウドサービス・オンライン広告など)には、リバースチャージ方式が適用されます。
リバースチャージ方式とは、国外事業者が消費税を徴収するのではなく、サービスを受ける国内事業者が消費税を申告・納付する仕組みです。
原則として、消費税は販売側(消費税を預かった事業者)が申告・納税を行いますが、リバースチャージ方式では、購入側が国外事業者に代わって消費税を納付します。
この時、国内事業者が支払う消費税に関しては仕入税額控除の処理が必要になります。
一方で、その金額と同額の借り受け消費税が発生することになるため、結果的にリバースチャージ方式による仮払消費税と仮受消費税の金額は相殺されることになります。
資産計上が必要かの判断
サブスクリプション契約が1年以上にわたる場合や、金額が大きい場合には、「費用」として一括処理するのではなく、「資産」として計上すべきかを検討する必要があります。
これは、長期契約により継続的なサービス提供を受ける形となるため、会計基準によっては「前払費用」として一時的に資産計上し、契約期間に応じて分割で費用化する処理が求められるケースがあるためです。
一般的には「契約期間が1年以上」「支払金額が10万円以上」を目安に資産計上を検討することが多いですが、実際の判断は自社の「会計処理規程」などに従う必要があります。
判断に迷う場合や扱いが不明確な場合は、税理士や会計士などの専門家に相談しておくと安心です。
インボイス制度への対応
2023年10月から導入されたインボイス制度により、消費税の仕入税額控除を受けるためには、取引先から適格請求書(インボイス)を受け取る必要があります。
取引相手がインボイス発行事業者でない場合は、原則として仕入税額控除を受けることができません。
経過措置として、2026年9月までは仕入税額の80%、2026年10月~2029年9月までは50%の控除が認められていますが、2029年10月以降は控除が一切できなくなります。
そのため、毎月の定額請求を受けるサブスクリプション契約においても、取引先がインボイスを発行できるかどうかが重要です。
もし取引先がインボイスに対応していない場合、以下のような対応が考えられます。
- 取引先にインボイス登録を依頼する
- インボイス対応済みの他社サービスに切り替える
- 消費税の仕入税額控除をあきらめる
事前に取引先のインボイス対応状況を確認し、必要に応じた対策を講じておくことが重要です。
※関連記事:インボイス制度で売り手と買い手がするべきこととは?
※本記事の内容は掲載日時点での情報です。
会計業務を効率化!
かんたんクラウド会計
電子帳簿保存法・電子取引に対応!スタートアップの方、中小企業・小規模事業者の方に最適!クラウドだからこそ実現するプロから選ばれる会計・給与ソフトをだれでも簡単に!
**********
サブスクリプション契約の普及に伴い、会計処理の重要性も高まっています。
勘定科目の選定や仕訳の方法、資産計上の判断、インボイス制度への対応など、経理担当者が押さえるべきポイントは多岐にわたります。
まずは自社で利用しているサブスクリプションを洗い出し、処理方法が適切かを確認することから始めましょう。