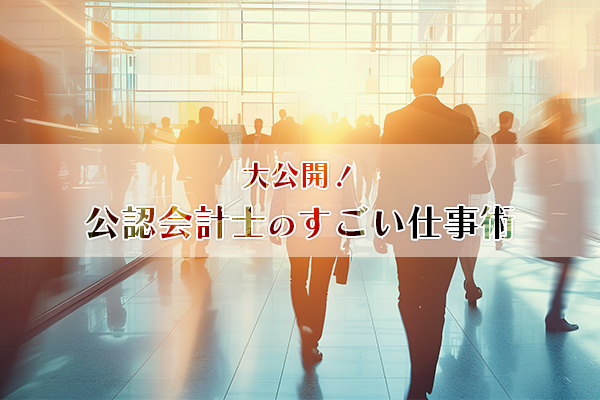2.ケースで考える 資料の体系化
まずは、ある監査現場での出来事を描いた次の【シーン1】をご覧ください。ここでは監査現場を題材にしていますが、企業の経理部門やその他様々な資料を取り扱う部署でも類似する事象はあると思いますので、適宜ご自身の業務に関わらせてアレンジして頂ければと思います。【シーン1】
T社からは。貸借対照表や損益計算書、各勘定科目の明細表や関連証憑などの資料を入手し、それぞれの勘定科目の監査を行っています。
数日が経過し、いよいよ監査の終盤を迎えました。
現場主任の会計士Mさんは、各監査スタッフが必要な資料を入手し、必要・十分な検証がされているか、見つかった問題点は何かなどを確認するため、各スタッフが作成した監査調書をレビューし始めました。
ところが、各スタッフは好き勝手な順番で資料を保存したり、ファイル名を付けたりしています。Mさんには、どこにどの資料があるのかも分からない状態で、中には同じ資料がダブっていることもあり、必要・十分な検証をしたのかも分からなければ、見つかった問題点が何かも分かりません。
「はぁ~」
Mさんからはため息が漏れてしまいました。
【シーン1】では1つの監査先企業での出来事として問題の一端を描きましたが、実際の監査では多くの監査先企業があり、監査チームのメンバーも監査先企業ごとに大きく入れ替わります。それぞれの業務では、間違いは許されませんし、効率化も求められます。こうした状況で、もしも監査調書の作成を各人任せにしていたら、本人には良くても、組織的な観点からすると、【シーン1】で描いたように不都合は大きなものになってしまうのです。
こうした問題が起こらないように、実際の監査では監査調書の作成については、共通する留意事項がありました。
“資料の体系化”の仕組みと言ってもいいものでしたが、これは監査に限らず、各種決算資料を取り扱う経理部門などにも適用できるのではないかと思います。以下、体系化に当たって留意すると良い点をいくつか挙げておくことにします。
(1)見やすさ・利用のしやすさなど、資料の順番を考えてルールを決める
入手・作成した資料を、実際に見たり利用したりするときのことを想定した上で、見やすさ・利用のしやすさなどの観点から、資料の順番を考えて保存・ファイリングのルールを決めるようにします。資料を見たり利用したりする人は、資料を入手・作成した本人以外のことも多いので、資料を入手・作成する人の視点だけで検討するのではなく、見る人・利用する人の視点を入れることが大事です。例えば、監査の場合で簡単に説明しましょう。監査では個々の勘定科目の検証をする複数のスタッフが監査の過程・結果を記した監査調書を作成し、それを各スタッフの取りまとめ役である現場主任、さらにはその上司に当たるチームの責任者、さらにはチーム以外のチェック担当者などが確認することになります。
それでは、どうすれば確認がスムーズに進むのでしょうか。いきなり詳細な原始帳票を見るのではなく、まずは、実際の決算数値がどうなっているのか、検証の結果はどうだったのかを確認することになります。どんな検証をしたのか、その具体的な証跡はどうなっているかはそれよりも後になります。そのため、実は監査調書は次のような順番にするように決められていました。
①リードシート
各勘定科目の決算数値を、現金預金関係・売上債権関係・棚卸資産関係などにグルーピングしたもので、各担当者にとっての検証のゴールと言えるもの。
②要約資料
当該勘定科目グループに関する検証結果として、比較増減分析結果、発見された会計上の問題点や内部統制上の問題点、翌期の留意事項などをまとめたもの。
③手続書
当該勘定科目グループに関する決算数値を検証するために実施すべき検証手続を記載したもの。各担当者はこれに従って検証業務を実施する。
④個別の検証資料
各勘定科目に関して実施した検証の証跡を記載したもので、監査先企業から入手した各種資料やそこから抜粋したデータなどに対する、具体的な検証内容やその結果などが記録される。
「④個別の検証資料」についてはさらに、その中の資料の並び順にも留意する必要があります。例えば、同じ売掛金の資料であっても、その中身の詳細度合いが異なります。こういった場合、より集約された情報は前の方に、より詳細な情報は後ろの方になるように並べます。前から後ろへとブレイクダウンしていく流れにするということです。
(ブレイクダウンの流れにする)
例えば、次のような順に資料を並べることが考えられます。
第1階層:決算書の表示科目(勘定科目)
>第2階層:支店別・部署別集計や項目別集計など
>第3階層:相手先別明細など
BS項目やPL項目に関連する資料の体系化の例を示すと【図表1】のとおりです。
【図表1】関連資料(ファイル・フォルダ)の体系化の例
BS項目
| File № | 勘定区分 | 階層1 | 階層2 | 階層3 |
| 010000~ 010999 |
現金預金 | 現金 当座預金 普通預金 定期預金 ・・・・・ |
預金: 銀行口座別 |
|
| 020000~ 020999 |
売上債権 | 売掛金 受取手形 |
営業所別 | 得意先別 |
| 030000~ 030999 |
棚卸資産 | 原材料 仕掛金 製品 商品 ・・・・・ |
製品: 製品グループ別 |
種類別 |
| 040000~ 040999 |
その他流動資産 | |||
| ・・・・・ | ・・・・・ |
PL項目
| File № | 勘定区分 | 階層1 | 階層2 | 階層3 |
| 310000~ 310999 |
売上高 | 事業別 | 営業所別 | 得意先別 |
| 320000~ 320999 |
売上原価 | 事業別 | 営業所別 | |
| 330000~ 330999 |
販管費 | 勘定科目別 | 月別 | 内訳項目別 |
| ・・・・・ | ・・・・・ |
(2)ファイルやフォルダのナンバリングのルールを決める
最近は紙媒体の資料が減少し、ペーパーレス化が進んでいます。また、紙媒体の資料もPDFなどで画像化するなどして保存することもできます。ただし、電子ファイルで保存する場合も、各自が好き勝手にファイル名やフォルダ名を付けて保存していたら、後から目的のファイルに素早くアクセスするのが難しくなってしまいます。場合によってはいつまでもアクセスされないまま埋もれてしまうファイルも出てくるでしょう。そうならないためには、まず、残すべき資料の全体像を念頭に置き、どのような順番で保存するのが良いかなどの構造を検討した上で、電子ファイルやそれらを格納するフォルダのナンバリングのルールを決めることが効果的です。
例えば、関係資料のファイル名・フォルダ名の頭に必ず6桁の数値を入れるとともに、内容を表す適切なファイル名・フォルダ名を付けることとします。売上債権関係は上3桁を必ず「020」(=「020XXX」)とし、下3桁については「000」(=「XXX000」)はリードシート、「010」(=「XXX010」)は結果要約とするといった具合に、ナンバリングのルールを決めるのです。6桁というのはあくまでも例示ですので適切な桁数を設定することになります。
各資料に付されたナンバーは、ある資料の元になった資料が何なのか、詳細を記載した資料は何なのかを示す際にも効果を発揮します。例えば、「詳細は資料番号✕✕を参照」といった記載があれば、根拠資料がどこにあるのかがすぐに分かるのです。なお、この点については、本連載『公認会計士の仕事術-第4回 「見える化」でミス削減』の中の「リファレンス」として具体的に説明していますので、そちらもご参照ください。
(3)重要事項の要約資料を作成する
私が携わっていた財務諸表の監査においては、膨大な量の監査資料を作成・保存することになります(ほとんど電子化されています)。仮に当該監査先企業の監査責任者がすべての資料に目を通して、初めてどこにどんな重要な問題点があるのか(あったのか)が分かるというのではスムーズに仕事が進みません。勘定科目グループごとに結果を要約した資料があることで、まずはそこに目を通して重要事項を要領よく把握することができるわけです。翌年度に別の担当者が監査をする場合でも、前期においてどこにどんな問題があったのかを要領よく把握することができます。要約資料を作成することで、誰が見てもすぐに重要事項が把握できるのです。
【図表2】重要事項の要約資料の例(売上債権の場合)
1.比較増減分析の結果
受取手形:特記すべき著増減等なし
売掛金 :対前期末比XX千円増(調書番号XXを参照)
主として、・・・・・に伴う増加
主な相手先:〇社 XX千円増・・・・・による増加
□社 XX千円増・・・・・による増加
2.会計処理上の問題点
滞留売掛金に対する貸倒引当金計上不足(調書番号XXを参照)
(借方)貸倒引当金繰入額(販管費)XX/(貸方)貸倒引当金(流動)XX
3.内部統制上の問題点
与信管理の仕組みの不備について:・・・・・・・・・・(調書番号XXを参照)
滞留売掛金の把握漏れについて :・・・・・・・・・・(調書番号XXを参照)
4.組替・注記事項等
関係会社に対する売掛金 XX千円増(調書番号XXを参照)
5.翌期留意すべき事項等
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(4)数値は比較形式にする
財務資料には様々な数値が出てきますが、そうした数値はできる限り比較形式にしておくことをお勧めします。例えば、売掛金の支店別集計の数値が1期分だけあっても、そこから読み取れることは限られますが、これが2期分以上の比較形式になっていれば、その増減が見えるので、格段に読み取れる情報が増します。(5)必要でない資料等を残しておかない
財務諸表の監査をしていると、監査先企業から様々な資料やデータを入手します。ただし、それらのすべてを保管しておく必要はありません。それどころか、必要でない資料まで保管されていると、担当者自身も、それをチェックする管理者も、本当に見るべき資料がどれなのか分からなくなってしまいます。また、資料を残すにしても、必要な部分だけを抜粋して残すといったことも考える必要があります。例えば、得意先別の売掛金明細があったとして、その全部ということになると膨大な量になってしまいますが、そのうち検証対象となった得意先の残高部分だけを抜粋し、他は「others」などとしてその合計額だけを残しておくといったことが考えられます。
そして、財務資料などでよく使われるExcelなどの表計算ソフトでは、複数のsheetが作成されることがあります。この場合、例えば3枚のsheetが保存されていても、そのうちの2枚は何の情報も入力されていない空のsheetだということもよくあります。こうした場合、空のsheetが保存されているとわざわざそれに目を通さなくてはならないといったことが生じ得ますので、空のsheetは必ず削除するといったことを徹底するよう決めておくと良いでしょう。
さて、【シーン1】で描いたある監査現場の様子ですが、資料の体系化を図った結果、改善が進んだようです。
【シーン2】
現場主任の会計士Mさんは各監査スタッフの監査の状況を確認するため、各スタッフが作成した監査調書をレビューし始めました。
どのスタッフも資料のファイルの仕方が統一されており、どこにどの資料があるのかも一目瞭然です。監査の過程で見つかった会計上の問題点や内部統制上の問題点、BS項目・PL項目の増減理由なども明らかになっています。
資料の体系化を図った結果、以前起きていた様々な不都合が改善されました。
・どこにどの資料があるのかがすぐ分かるようになった。
・資料のモレやダブリにすぐ気づくようになった。
・要約資料を整備し、重要事項がつかみやすくなった。
・必要のない資料まで保管せず、資料がスッキリした。
3.資料の体系化を図って、組織効率を上げる資料保存の仕組みを整えよう
今回は、資料の体系化を図ることで、必要な資料、重要な情報がすぐに見つかり、また資料のモレやダブリにもすぐ気づくことができることを、ケースを使って説明しました。日常の業務を行う中では、様々な資料を入手したり、作成したりしますが、各担当者任せにすることなく、組織的な観点から組織効率を上げる資料保存ができるように、資料体系のルールを定めることが大事です。今回の記事を通じて、資料を体系化する際のポイントを整理しましたので、今後の業務を進める上での参考にして頂ければ幸いです。