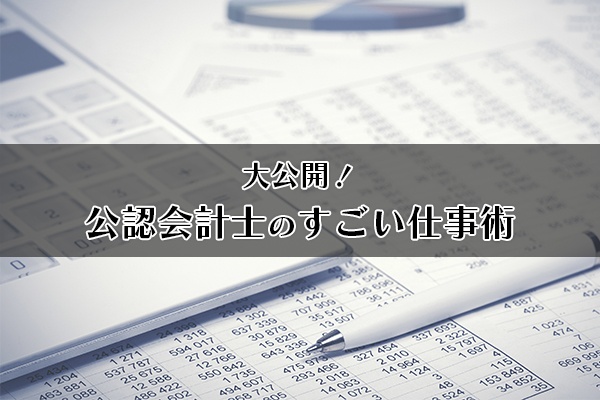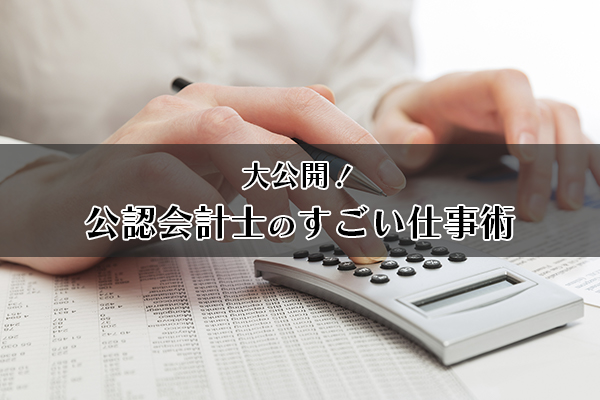2.ケースで考える ~あるはずのものが本当にあるのかをチェックする方法(その2)
まずは、経理部長と経理スタッフのやり取りの様子を描いた【シーン1】をご覧ください。【シーン1】(前回と同じ)
経理部長「何か先月末の売掛金の残高、いつもより多いな。多過ぎるんじゃないか?本当にこんなに売掛金があるの?」
Sさん「確かに多いですね。少々お待ちください……」
とは言ったものの、Sさんはどう対応したら良いものか、すぐには思い付かないのでした。
- 比較分析
- 帳簿上の相関関係のチェック
- 勘定残高と内訳明細資料との整合性チェック
- 現物があるものは現物を直接チェック(実査・棚卸)
そして、詳細チェックとして「(4)現物があるものは現物を直接チェック(実査・棚卸)」や、今回説明する(5)から(7)の方法などの各種方法があります。
(4)の実査・棚卸は現物があるもののチェックに、(5)の残高証明の入手、残高確認などは現物がないもの(債権債務、預金など)のチェックに使います。「(6)事後の状況フォロー」や「(7)帳簿以外の関連資料等への着目」は、(4)(5)でカバーできないもののチェックや、(4)(5)の代替としてのチェックに使ったり、他の方法と併用することでチェックを強化するのに使ったりします。チェック対象に適した方法を適宜選択して使ってみてください。
それでは以下、前回説明しきれなかった(5)から(7)について具体的に説明していきます。
(5)取引相手からの回答等をチェック(残高証明の入手、残高確認など)
目に見えるものであれば、その現物を実際に確かめることができますが、目に見える現物がないものもあります。この場合はどのようにして実在性をチェックしたら良いでしょうか。現物がないものとしては、例えば、預貯金、証券会社の口座で管理されている有価証券、売掛金や貸付金等の債権、買掛金や借入金等の債務、などを挙げることができます。
①残高証明の入手
預貯金の実在性チェックのケースについては残高を証明する資料等を確かめることが考えられます。具体的には取引金融機関が発行した残高証明書が該当します。預金通帳の記録をチェックすることもあり得ます。証券会社の口座で管理されている有価証券であれば、証券会社が発行した保管有価証券の明細資料が該当します。②残高確認
「残高確認」というのは、取引相手に対して当社に対する債権や債務がいくらあるのかを聞く方法です。当社の売掛金残高の実在性を確かめようとするケースであれば、取引相手である得意先側が当社に対していくらの買掛金残高を持っているのかを聞くことになります。当社だけで完結せず、第三者(取引相手)から回答をもらうので強力なチェックになります。その一方で、先方から得た回答が正しいとは限りませんので、自社と相手先の残高を照合して、差異があれば、差異の内容を分析し、誤りがあれば正しい数値に修正するなど、手間がかかります。
(例)
3月末におけるA社に対する売掛金の残高確認を行った結果、以下のように、先方の回答との間に差異があったとします。
| 当社側: | 3月末の得意先A社に対する売掛金残高 | 3,000,000円 | |
| A社側: | 3月末の当社に対する買掛金残高 | 2,000,000円 | |
| 差異 | 1,000,000円 |
- 当社側・A社側とも問題のない差異
- 当社側に問題のある差異
- A社側に問題のある差異
当社側に問題のある②については当社の処理を正しいものに修正する必要があり、A社側に問題のある③についてはA社側の処理を正しいものに修正して頂く必要があります。このように、残高確認を実施することによって、正しい(実在性のある)売掛金残高を確かめることができます。
実際には、継続的に何回も取引を行い、また回収が行われた結果として、これだけの売掛金残高になっているわけなので、取引の明細単位で当社側とA社側の残高を照合していくことになります。
このように残高確認には手間がかかりますので、取引先の数が多くなるとなかなか大変です。したがって、特に重要な残高のある得意先や、予定どおりに回収できていない得意先など、対象を絞った上で実施することが考えられます。
(6)事後の状況フォロー
事後の状況をフォローするのも実在性チェックの方法の一つです。経理の世界では、架空の資産や誤って過大に計上されている資産が存在するというのは大きな問題です。こうした資産が存在すると、収益の計上額が多くなり(あるいは費用の計上額が少なくなり)、過大に利益を計上してしまっているかもしれませんし、早期に回収できると思ってその後の支払いのための資金として当てにしていたところ、想定外に資金繰りに苦慮するといった事態にもなりかねません。
このような実在しない債権等がないかをチェックするための強力な方法は、その後の回収状況をチェックすることです。
当期末のB/Sに計上されている売掛金について、翌期に回収されていたとすると、それは確かに売掛金が実在することの裏付けとなり得ます。したがって、計上された売掛金についてはその後の回収状況をフォローすることがとても有用です。言い換えれば、予定どおりに回収できていない売掛金(あるいは滞留している売掛金)の有無をチェックできる体制を整えることが大切で、いつまで経っても回収されない売掛金があるとすれば、架空の売掛金や誤って過大に計上してしまった売掛金が、B/S上に残っている可能性もあります。
(7)帳簿以外の関連資料等への着目
実在性をチェックする際、(4)で説明した実査・棚卸や、(5)で説明した残高証明の入手・残高確認などでカバーできれば良いのですが、これらはすべての対象に実施できるわけではありません。また、実施できるタイミングが限定されることも少なくありません。そこで、これらの代わりになるような方法も必要になりますが、その方法として、帳簿以外の関連資料、特にその計上の際の関連資料に目を向けることが考えられます。まず挙げられる資料としては、取締役会や経営会議などの議事録や、稟議書等の決裁関係の資料です。つまり、各種の案件の審議をしたり、決裁をしたりした資料に目を通すことです。会社によって、審議や決裁の仕組みは違うでしょうが、これらの資料があることは、実在性を裏付ける上での一つの材料となります。逆にこうした資料があるはずなのにないとしたら、実在性に疑義が生じるかもしれません。この場合の観点は、「資料等」から「帳簿」への流れではなく、あくまでも「帳簿」から「資料等」への流れであることがポイントです。
(注)以前に取り上げた網羅性チェックの場合は、「資料等」から「帳簿」に当たるという流れであり、実在性チェックと網羅性チェックとでは流れが逆であることにご留意ください。
また、特定の取引の実在性に疑義が生じ、裏付けをとるために計上時の根拠資料を再度確かめるようなケースでは、計上根拠となった請求書(控)や納品書(控)、注文書、契約書などをチェックすることも考えられます。【シーン2】
あれから半年が経った今のSさん。残高比較や回転期間分析などをしっかり実施し、著増減理由もしっかりつかんでいます。また、従来は行われていなかった売掛金の残高確認を定期的に実施することも提案しました。残高確認の結果、大口の得意先に対する売掛金について、過去の計上誤りによって生じた実在性のない残高が含まれていたことが判明しました。
経理スタッフとして成長著しいSさん、周りの人たちからも期待される存在となっています。
3.おわりに ~実在性チェックの力を鍛えよう
前回と今回でお伝えした実在性チェックのための各種の方法は、私が財務諸表監査を行う中で経験してきたものを念頭に、整理してみたものです。経理部門のスタッフや経理部長の方々は、誤ったものを帳簿に計上しないという意識を絶えず持っておくことが大切です。そのためには帳簿に計上する際、その根拠となる資料等にも十分に注意を向ける必要があるでしょう。また、定期的に現物を確かめたり、取引相手からの回答等を入手・照合したりといったことが必要です。
実在性チェックの方法は一つではありません。上述したように様々な方法がありますし、これら以外のものもあることでしょう。
経理に関わる業務を念頭に実在性チェックの話を進めましたが、経理部門以外の方も含めて、是非、読者の皆様がご自身に関わる業務を行われる際に、実在性チェックの視点を活用して頂ければ幸いです。