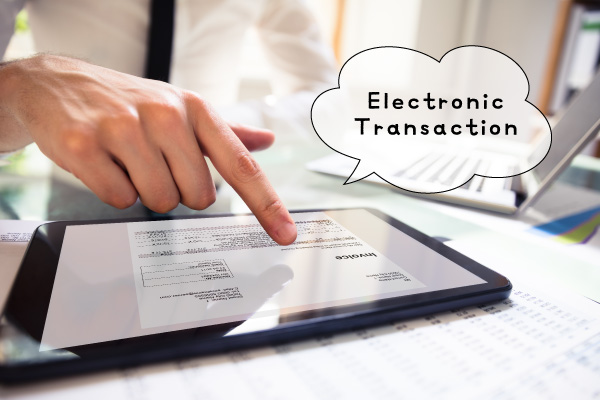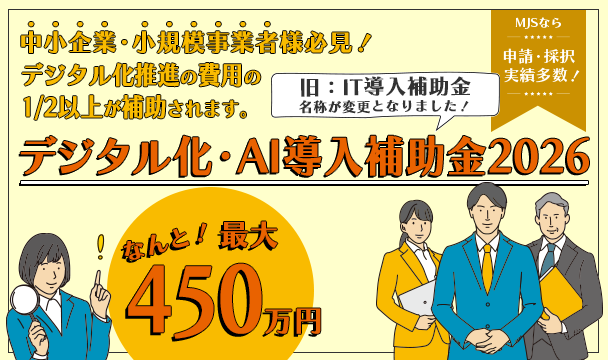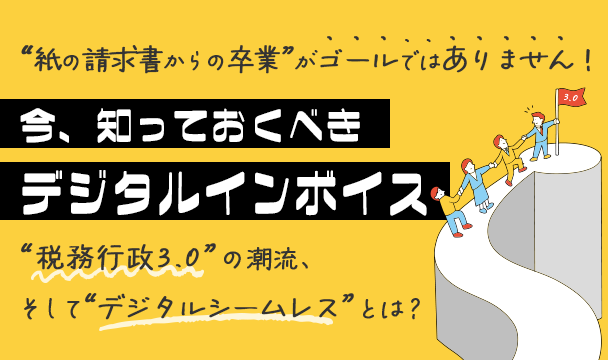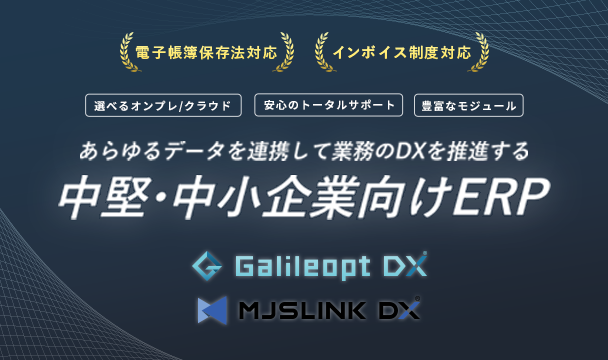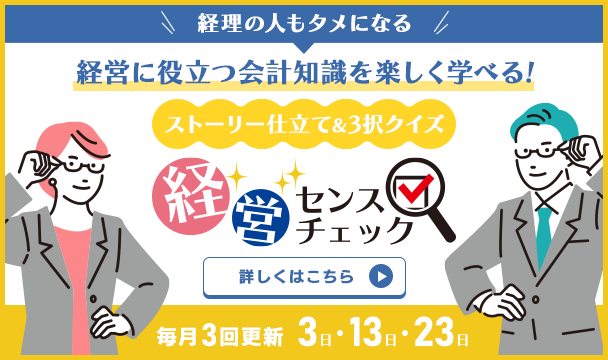2025年4月から導入された「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」により、育児休業制度がさらに充実します。
一方で既存の育児休業給付金の支給対象期間延長手続きについては必要書類が増え、審査がより厳しくなりました。
今回の記事では、育休をスムーズに取るために、これまでの育児休業制度と併せて改正のポイントを解説します!
育児休業の基礎知識と既存の制度の概要
「育児休業制度」とは、従業員が出産や育児の理由で仕事ができない時に一時的に会社を休業できる制度で、働きながら子育てをする家庭にとって重要な支援策の一つとなっています。
育児休業(育休)の取得は育児介護休業法で定められた労働者の権利であり、勤め先の企業が拒否することはできません。
しかし、企業の就業規則によっては育休中の従業員の収入が減ってしまうこともあるため、従業員が雇用保険の被保険者で一定の要件を満たす場合には給付金が支給されるようになっています。
従来の主要な制度には「育児休業給付金」と「出生時育児休業給付金」があります。
|
取得可能期間 |
給付金 |
| 育児休業給付金(育児休業給付制度) |
原則として、子どもが1歳になるまで取得可能。(2回まで分割取得可能/保育所などに入所できない場合最長2歳まで延長可能)。
パパ・ママ育休プラスを活用する場合、最長で子どもが1歳2カ月になるまで延長可能。 |
一定の要件を満たす場合、受給可能。
育休の最初の半年(180日)までは休業開始時の賃金の67%程度、181日目からは休業開始時の賃金の50%程度が支払われる。
休業開始時の賃金は、休業開始前6カ月の賃金を日割りで計算した金額。 |
| 出生時育児休業給付金(産後パパ育休制度) |
通常の育休とは別に、子どもの出生後8週間以内に最大4週間まで取得可能(2回まで分割取得可能)。 |
一定の要件を満たす場合、受給可能。
受給金額は育児休業給付金の考え方と同じ。ただし休業期間の日数の上限は28日とする。 |
※パパ・ママ育休プラスとは、両親がともに育休を取得する場合、子どもが1歳2カ月に達するまで育休可能期間が延長される制度です。
育休により、従業員は家族と過ごす時間を確保して安心して育児に取り組む環境をつくることができます。
企業にとっても、職場満足度の向上や、長期的な雇用の安定化といったメリットがあるため、近年では多くの企業が取得促進に取り組んでいます。
※関連記事:【改正育児休業法対応】育児休業制度の申し入れがあった際の企業の対応とは?
組織の人的資源を最大限に活用!
給与・人事システム
複雑な支給形態を網羅!勤怠管理などのシステムとも連携することで、給与・賞与計算を自動化できます。また、従業員のあらゆる情報を適切に管理することで、組織の人的資源を最大限に活用することができます。
【2025年4月創設】出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金
今回の改正では、先述した「育児休業給付金」と「出生時育児休業給付金」に加えて「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」が創設されました。
出生後休業支援給付金
出生後休業支援給付金とは、雇用保険の被保険者が、子どもの出生後8週間の期間内で合計4週間分を限度に産後パパ育休(出生時育児休業給付金による育休)を取得した場合、一定の要件を満たすことで給付金の支給を受けられる制度です。
支給要件
出生後休業支援給付金は、以下の要件を満たす場合に、出生時育児休業給付金に加算する形で支給されます。
-
雇用保険の被保険者が、同一の子どもにおける産後パパ育休を出生後8週間以内に通算して14日以上取得すること。
- 2025年4月1日より前から継続して産後パパ育休を取得している場合、2025年4月1日以降に14日以上取得している必要があります。
- 産後パパ育休の期間中に育児休業給付金による育休を取得した場合、その日数も通算されます。
-
配偶者が、産後休業後8週間以内に通算して14日以上育休を取得すること。
- 配偶者がいない場合や、自営業者、フリーランス、専業主婦などである場合には、上記の要件は不要となります。
支給額
出生後休業支援給付金の支給額 = 休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数(上限28日)× 13%
出生時育児休業給付金では休業開始時賃金日額の67%相当額が支払われるため、出生後休業支援給付金と合わせると、休業開始時賃金日額の80%相当額の給付金が支給されることになります。
これらの給付金からは社会保険料等の控除が行われないことから、実質的に休業前の賃金の手取りが保証されることになります。
支給期間
最大28日間となります。
育児時短就業給付金
育児時短就業給付金とは、雇用保険の被保険者が、2歳未満の子どもを養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合、賃金が低下するなど一定の要件を満たした際に給付金の支給を受けられる制度です。
支給要件
育児時短就業給付金は、以下の受給資格をいずれも満たす従業員が、要件を満たす月について支給されます。
受給資格
- 2歳未満の子どもを養育するために、1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業する被保険者であること。
- 育児休業給付の対象となる育休から引き続き、同一の子どもについて育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12カ月あること。
各月の支給要件
- 初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者である月
- 1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
- 初日から末日まで続けて、育児休業給付または介護休業給付を受給していない月
- 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月
支給額
育児時短就業給付金の支給額 = 支給対象月に支払われた賃金額 × 10%
支給額は原則として時短勤務中の支払賃金の10%相当額となりますが、時短後の賃金と給付金の支給額の合計が時短前の賃金を超えないように、一定の調整が行われることとなります。
支給期間
原則として、育児時短就業に係る子どもが2歳になるまでとなります。
※参考資料:厚生労働省「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」
組織の人的資源を最大限に活用!
給与・人事システム
複雑な支給形態を網羅!勤怠管理などのシステムとも連携することで、給与・賞与計算を自動化できます。また、従業員のあらゆる情報を適切に管理することで、組織の人的資源を最大限に活用することができます。
【2025年4月改正】育休の延長手続きにおける変更点
育児休業給付金では、子どもを保育所などに入れることができなかった時のために支給対象期間を延長することができます。
原則の期間は子どもが1歳になる日までですが、支給対象期間を延長することにより1歳6カ月または2歳に達する日まで、育児休業給付金の支給を受けることができます。
延長要件は以下1から3のすべてを満たすこととなります。
- あらかじめ市区町村に対して保育利用の申し込みを行っていること
- 速やかな職場復帰のために保育所などの利用を希望していることを公共職業安定所(ハローワーク)長が認めていること(以下のすべてを満たす必要あり)
- 原則として子どもが1歳に達する日の翌日以前の日を入所希望日として入所申し込みをしていること
- 申し込んだ保育所などが、合理的な理由なく、自宅から片道30分以上かかる施設のみとなっていないこと
- 市区町村に対する保育利用の申し込みにあたり、入所保留となるように希望する旨の意思表示をしていないこと
- 子どもが1歳に達する日の翌日時点で保育所などの利用ができる見込みがないこと
【2025年4月改正】延長手続きの必要書類
2025年4月から、育児休業給付金の支給対象期間延長手続きについても改正が行われます。
これまで育児休業給付金の支給対象期間延長に必要な書類は市区町村が発行する入所保留通知書のみでした。
これに加えて、2025年4月以降は、保育所などの利用申し込みが行われたことを証明する書類も必要となります。
書類の具体例は以下の通りです。
- 市区町村が発行する、保育所などの利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など従前と同様のもの)
- 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
- 市区町村に保育所などの利用申し込みを行った時の申込書の写し
今回の改正により、これまでは入所保留通知書のみで認められていたものが、今後は支給期間を延長する理由や申し込みの状況なども踏まえたうえでの審査が行われることになり、要件が厳格化されたといえます。
必要書類の詳細については、厚生労働省のホームページも併せてご確認ください。
※参考資料:厚生労働省「育児休業給付金の支給対象期間延長手続き」
企業の対応ポイント
従業員が育休の延長希望を申請した場合、企業は給付金支給の延長申請を行う必要があります。
改正後は、給付金延長のために、保育所などに入所する意思がないにもかかわらず申し込みを行っていないかなど、厳しい審査が行われます。
企業担当者としても、改正の内容に合わせた対応を従業員に事前に周知しておくことが重要です。
また、従業員からの申請時はハローワークに提出する前に以下のような点に注意しましょう。
- 保育所への入所希望日が適切であるかどうか
- 通勤経路上や自宅から適切な距離にある保育所に申し込んでいるか
- 保育所への入所内定辞退や入所保留を希望する旨の意思表示をしていないか
虚偽の申請と判断されると、給付金の返還を求められたり、罰金が課されたりする可能性もあります。
企業担当者としても従業員が延長手続きの必要書類への情報記入を正しく行うことができているかしっかりと確認することが必要です。
※本記事の内容は掲載日時点での情報です。
組織の人的資源を最大限に活用!
給与・人事システム
複雑な支給形態を網羅!勤怠管理などのシステムとも連携することで、給与・賞与計算を自動化できます。また、従業員のあらゆる情報を適切に管理することで、組織の人的資源を最大限に活用することができます。
**********
2025年4月の改正内容について、企業担当者として従業員に周知を行うことが大切です。
出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金など新たな制度の内容や、厳格化された給付金の延長要件については確認が漏れることのないよう抑えておきましょう。