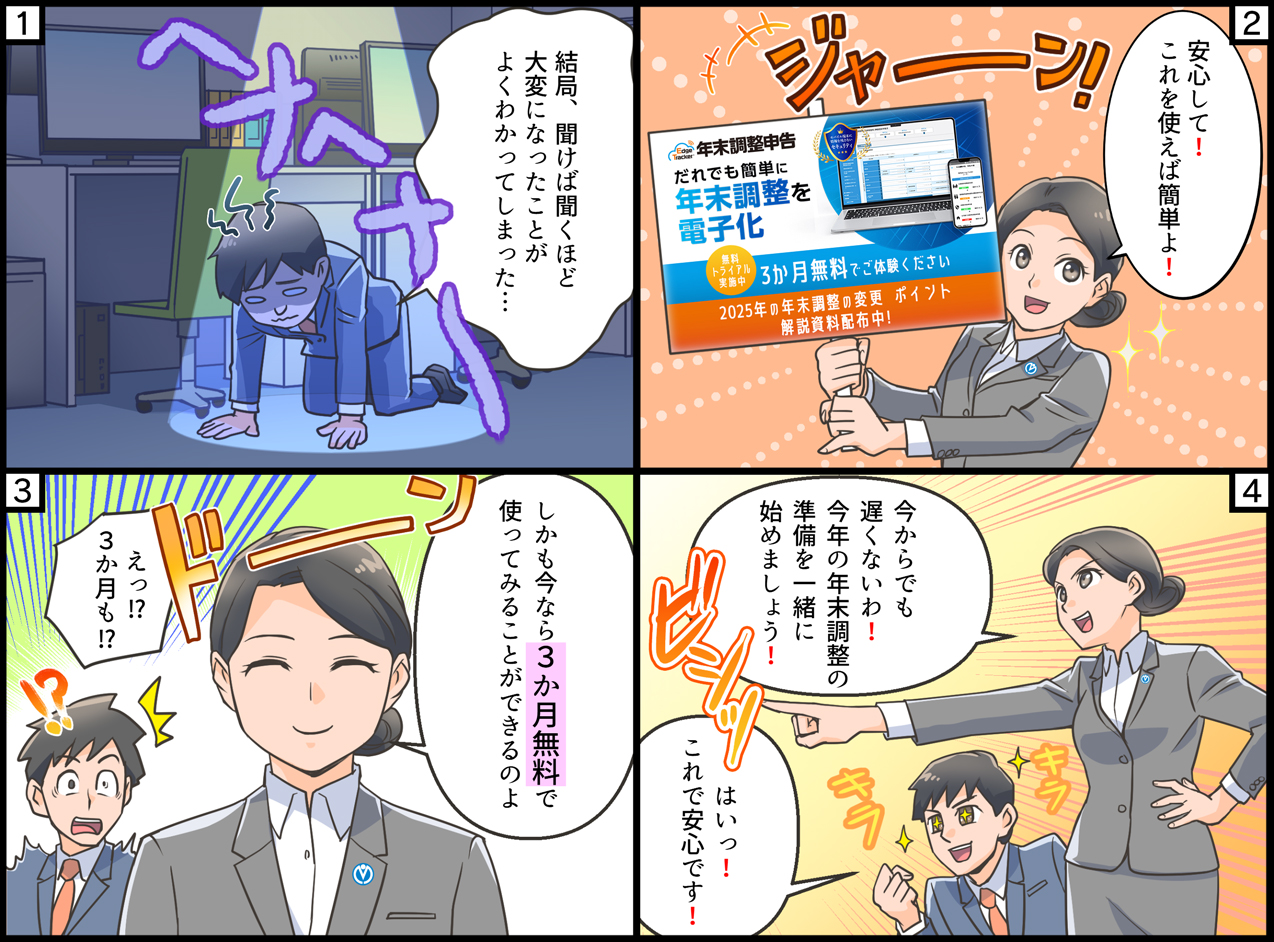年末調整とは、会社員などの給与所得者が毎月の給与からあらかじめ差し引かれている源泉所得税について、1年間の合計で正しく計算し直し、その過不足額を年末の給与で清算する制度です。
通常、毎月の給与では概算で所得税が引かれており、年末に実際の年間収入や控除額を反映させて再計算されます。
その結果、所得税を納付しすぎていた場合は還付(返金)され、足りなかった場合は追加で徴収されます。
基本的な年末調整の対象者は、年末時点で会社に在籍しており、年内に退職していない給与所得者です。
提出が必要となる主な申告書は以下の4種類です。
| 提出書類 |
内容 |
| 扶養控除等(異動)申告書 |
所得税の扶養控除など各種控除を受けるために、給与所得者は基本的に提出が必要となる書類。 |
| 基礎控除申告書 |
所得が一定以下であれば、誰でも適用される「基礎控除」を申告する書類。 |
| 保険料控除申告書 |
生命保険料・地震保険料・介護医療保険料などを支払っている人が、控除を受けるために提出する書類。 |
| 住宅借入金等特別控除申告書 |
住宅ローン控除の適用がある人が控除を受けるために提出する書類。 |
今なら3ヶ月無料トライアル実施中!
Edge Tracker 年末調整申告
だれでも簡単に年末調整を電子化!年末調整業務の改善とコストダウンで、従業員と管理部門の業務効率化を実現するクラウドサービスです。直感的でストレスフリーな操作性を3ヶ月無料で体験ください。
2025年(令和7年分)の年末調整では大きく4点が改正され、事務処理の負担が増すことが予測されます。
それぞれの内容と実務での注意点を解説します。
基礎控除の見直し
基礎控除とは、所得税の計算において納税者の合計所得金額から一定額を差し引ける控除の一つです。
主に、生活に必要な最低限の所得に課税されないよう配慮する目的で設けられています。
改正により、2025年分・2026年分の基礎控除額については、合計所得金額に応じて段階的に引き上げられる仕組みに変更されました。
所得が低いほど、控除額が大きくなる制度となっています。
合計所得金額
(給与のみ換算) |
基礎控除額 |
| 改正前 |
改正後 |
| 2,350万円超 |
48万円 |
変更なし
(48万円) |
| 655万超~2,350万円 |
58万円 |
| 489万超~655万円以下 |
63万円 |
| 336万超~489万円以下 |
68万円 |
| 132万超~336万円以下 |
88万円 |
| ~132万円以下 |
95万円 |
源泉徴収では従来の48万円をベースに計算しているケースがほとんどと思われるため、年末調整の際は改正後の基礎控除額を反映し、精算処理を行う必要があります。
控除額は従業員の年間の合計所得金額(見積額)に応じて変わるため、従業員から提出される「基礎控除申告書」の確認が重要となります。
正しい控除額を適用しなければ、還付漏れや徴収不足のリスクが生じるため、不備があれば速やかに再提出を依頼しましょう。
給与所得控除の見直し
給与所得控除とは、会社員やパート・アルバイトなどの給与所得者の収入から一定の金額を控除できるもので、所得税の負担を軽減する目的があります。
2025年からは給与所得控除の最低額が55万円から65万円へと10万円引き上げられ、年収190万円までは一律に65万円の控除を受けることができるものとなりました。
| 給与収入 |
改正前の控除額 |
改正後の控除額 |
| 180万円超~190万円以下 |
年収 × 30% + 8万円 |
65万円 |
| 162万5千円超~180万円以下 |
年収 × 40% − 10万円 |
| ~162万5千円 |
55万円 |
※年収190万円超の給与所得者については、控除額に変更はありません。
これまでは「基礎控除48万円+給与所得控除55万円」で103万円が非課税ラインとされていましたが、今回の見直しにより、基礎控除が95万円、給与所得控除は65万円となり、実質的な非課税ラインは160万円にまで引き上げられます。
つまり、これまで「103万円」だった所得税の年収の壁が「160万円の壁」へと変わり、特にパート・アルバイトなど低収入の従業員の非課税枠が大きく拡大されます。
年末調整では非課税となる従業員が増える可能性があるため、対象者の確認と計算ミスに注意しましょう。
特定親族特別控除の創設
2025年分から、新たに「特定親族特別控除」という所得控除制度が導入されました。
以下の一定の要件を満たす扶養親族がいる場合に適用されます。
- 年末時点で19歳以上23歳未満の親族(里子も含む)
- 配偶者や事業専従者ではないこと
- 合計所得金額が58万円超~123万円以下
特定親族の所得金額に応じて、控除額が以下のように段階的に設定されています。
| 特定親族の合計所得金額 |
控除額(所得税) |
| 120万円超~123万円以下 |
3万円 |
| 115万円超~120万円以下 |
6万円 |
| 110万円超~115万円以下 |
11万円 |
| 105万円超~110万円以下 |
21万円 |
| 100万円超~105万円以下 |
31万円 |
| 95万円超~100万円以下 |
41万円 |
| 90万円超~95万円以下 |
51万円 |
| 85万円超~90万円以下 |
61万円 |
| 58万円超~85万円以下 |
63万円 |
特定親族特別控除を年末調整で適用するためには、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必要です。
提出漏れを防ぐため、従業員への周知を徹底しましょう。
また、提出された申告書に基づき、控除対象となる親族が要件を満たしているかどうかをしっかり確認することが重要です。
扶養親族の所得要件の見直し
基礎控除の見直しに合わせて、扶養親族などに関する「所得要件」も引き上げられました。
これにより、これまで控除対象外だった従業員が新たに対象となる可能性があります。
| 対象 |
改正前(合計所得金額) |
改正後(合計所得金額) |
- 扶養親族
- 同一生計配偶者
- ひとり親の生計を一つにする子
|
48万円以下 |
58万円以下 |
|
|
48万円超~133万円以下 |
58万円超~133万円以下 |
|
|
75万円以下 |
85万円以下 |
所得要件の緩和により、前年と同じ収入水準でも新たに扶養控除の対象となるケースが出てくる可能性があります。
対象となる可能性がある従業員には、「扶養控除等(異動)申告書」の再提出を依頼し、扶養判定の見直しを行いましょう。
2025年の年末調整に向けた対策
上記の改正により、年末調整の事務処理は例年以上に複雑化することが考えられます。
控除額の判定や申告書類の確認を人手で行うのは大きな負担となるため、年末調整システムの活用が有効です。
申告内容の一元管理や、控除額の自動計算およびチェック機能などにより、ミスや漏れも防止できます。
担当者の負担軽減と正確性の確保のため、早めに導入を検討すると安心です。
今なら3ヶ月無料トライアル実施中!
Edge Tracker 年末調整申告
だれでも簡単に年末調整を電子化!年末調整業務の改善とコストダウンで、従業員と管理部門の業務効率化を実現するクラウドサービスです。直感的でストレスフリーな操作性を3ヶ月無料で体験ください。
還付金とは、毎月の給与からあらかじめ控除されていた所得税について、年末調整の結果、引きすぎていたと判明された場合に返ってくるお金のことです。
通常は年初時点の情報から大きな変更がなければ、還付が発生することはあまりありません。
しかし、2025年は期中に税制改正が行われたため、年末調整時に改めて計算が必要となり、その結果として還付金が発生するケースがあります。
例年よりも「還付作業」がより重要なポイントとなるため、ここでは計算の流れを詳しく解説します。
還付金の計算手順
還付金の計算は、以下の手順で行います。
- 年間の給与収入を集計
その年の1月から12月までの給与明細を基に、年間の総支給額(賞与を含む)を集計します。
- 給与所得額を算出
給与収入から給与所得控除額を差し引き、給与所得を算出します。
- 課税所得金額を算出
給与所得から各種所得控除(基礎控除・扶養控除など)を差し引き、課税所得を算出します。
- 所得税額を算出
課税所得に所得税率をかけて、実際に納めるべき所得税額を算出します。
- 還付金を算出
年末調整前に源泉徴収されていた税額と、上記で算出した正しい税額を比較します。払いすぎていた場合、その差額が還付金として返ってきます。
還付金の算出の計算例
ここでは、年末調整の流れに沿って具体的に計算してみます。
前提条件は以下の通りです。
| 年間の給与収入 |
3,000,000円 |
| 基礎控除 |
880,000円 |
| 社会保険料控除 |
約450,000円 |
| その他の控除・扶養 |
なし |
1.年間の給与収入を集計
年間の給与収入を集計します。
この例では300万円と算出されています。
2.給与所得額を算出
給与収入から給与所得控除額を差し引き、給与所得額を算出します。
給与所得控除は給与収入に応じて段階的に決まります。
給与収入
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
|
給与所得控除額 |
| 8,500,001円以上 |
1,950,000円(上限) |
| 6,600,001円~8,500,000円まで |
収入金額 × 10% + 1,100,000円 |
| 3,600,001円~6,600,000円まで |
収入金額 × 20% + 440,000円 |
| 1,800,001円~3,600,000円まで |
収入金額 × 30% + 80,000円 |
| 1,625,001円~1,800,000円まで |
収入金額 × 40% – 100,000円 |
| 1,625,000円まで |
550,000円 |
※参考資料:国税庁「給与所得控除」
今回の場合は、収入が300万円で「1,800,001円~3,600,000円まで」に該当するため「給与収入 × 30% + 80,000円」で計算します。
給与所得控除
3,000,000円 × 30% + 80,000円=980,000円
給与所得
3,000,000円 – 980,000円 = 2,020,000円
3.課税所得金額を算出
給与所得から各種所得控除を差し引き、課税所得を算出します。
課税所得
2,020,000円 – 880,000円 – 450,000円 = 690,000円
4.所得税額を算出
課税所得に所得税率をかけて、実際に納めるべき所得税額を算出します。
例の場合、課税所得は69万円なので以下の表から税率は5%となります。
| 課税される所得金額 |
税率 |
控除額 |
| 40,000,000円 以上 |
45% |
4,796,000円 |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで |
40% |
2,796,000円 |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで |
33% |
1,536,000円 |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで |
23% |
636,000円 |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで |
20% |
427,500円 |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで |
10% |
97,500円 |
| 1,000円 から 1,949,000円まで |
5% |
0円 |
※参考資料:国税庁「所得税の税率」
所得税額
690,000円 × 5% = 34,500円
5.還付金を算出
算出した正しい税額と、毎月の給与から天引きされている源泉所得税額を比較して差額を計算します。
源泉徴収税額が40,000円の場合
34,500円 – 40,000円 = -5,500円
源泉徴収税額が30,000円の場合
34,500円 – 30,000円 = 4,500円
上記の通り、源泉徴収税額が40,000円なら5,500円が還付金となり、30,000円なら追加で約4,500円納付する結果となります。
還付金の支給時期
年末調整によって還付金が発生した場合は、通常12月の給与支給時に還付額を加算して振り込みます。
ただし、年末調整の処理が12月に間に合わない場合には、翌年1月の給与にて還付を行うことになります。
※本記事の内容は掲載日時点での情報です。
今なら3ヶ月無料トライアル実施中!
Edge Tracker 年末調整申告
だれでも簡単に年末調整を電子化!年末調整業務の改善とコストダウンで、従業員と管理部門の業務効率化を実現するクラウドサービスです。直感的でストレスフリーな操作性を3ヶ月無料で体験ください。