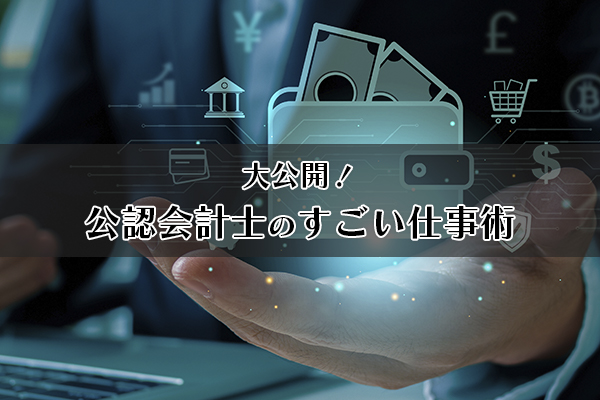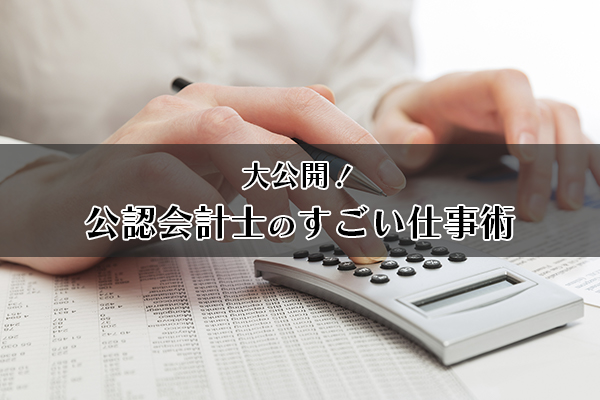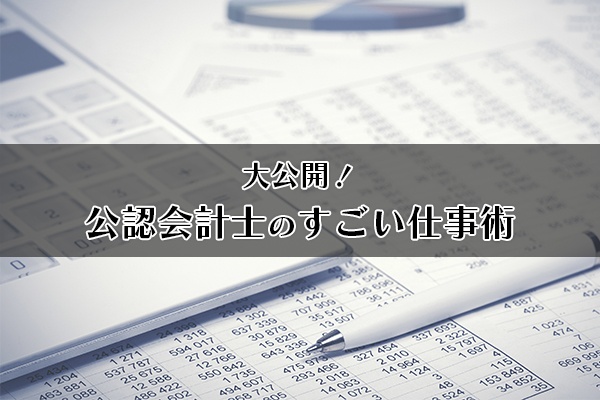今回から3回にわたって、現金実査を題材にしながら、そこから学べる経理の心得についてお話ししたいと思います。
2.ケースで考える ~現金実査からの学び
まずは、ある経理財務部での様子を描いた【シーン1】をご覧ください。【シーン1】
そして、いよいよ期末日を迎えました。経理財務部長が現金を実際に数えてみたところ、試算表の現金残高と全く合わないではありませんか。
経理財務部長「なんでこんなに差があるんだ!ただでさえ忙しい決算時期だというのに、調査には結構な時間がかかってしまうかもしれない……」
| 経理の心得1 | ストックの視点を大切にする |
それでは、フローとストックの関係について、簡単な設例も交えて説明していきましょう。現金の場合であれば、入出金がフロー、現金残高がストックです。現金の入出金取引というのは日常的に行われます。例えば、売上代金を現金や小切手で回収すれば、現金の入金というフローとなりますし、経費の支払いを現金で行えば、現金の出金というフローとなります。
【図表1】現金の入出金と残高(現金出納帳)
| 日付 | 内容 | 入金 | 出金 | 残高 | ||
| X1.3.31 | 100,000 | |||||
| X1.4.1 | ・・・の購入代 | 5,000 | 95,000 | |||
| X1.4.1 | ・・・の交通費 | 3,000 | 92,000 | |||
| X1.4.2 | ・・・からの売上代金回収 | 1,000 | 93,000 | |||
| ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||||
| X1.4.30 | 56,000 | ⇔ | 現金実査額 51,000 |
|||
| ⇓ | ⇓ | ⇓ | ||||
| フロー | ストック | |||||
ある時点の現金残高からスタートして、その後の入出金というフローを正しく記録してさえいれば、本来は各時点の現金残高というストックも確定するはずです。【図表1】で言えば、X1年3月31日時点の現金残高100,000円からスタートし、出金や入金の取引がある都度、それを正しく記録することで、各時点での現金残高も「残高」欄のところに自動的に計算できています。
そうだとすると、フローを正しく確定することこそが大事であって、別にストックを確定することなんて大した話ではないように思えなくもありません。
しかし、実際にはフローだけに着目していると失敗することになります。何故なら、入出金の記録がモレてしまったり、誤った金額で記録してしまったりすることもあり、フローだけに目を向けていると、こうした誤りが発生してもなかなか気付くことができないからです。そうならないために、フローの記録から算出されるストックと、実際のストックとをタイムリーに照合するようにするのです。その結果、万が一差異が発生すれば、それにすぐに気付くことができますし、差異が発生した原因を調査することで、フローの記録が誤っているなどの問題に気付くことができるのです。
例えば、【図表1】のように、X1年4月の入出金を記録していった結果、X1年4月30 日の現金残高が56,000円と計算されたとします。一方、4月30日に実際に金庫に保管されている現金を数えてみたところ、残高が51,000円しかありませんでした。実際の現金残高が5,000円少ないのです。
この差異の原因を調べたところ、次のことが判明しました。
【図表2】差異の原因の調査結果
| No | 差異の内容 | 差異金額 |
| ① | 4月15日の会議のときの飲料代支払いの計上モレ 3,000円 | △ 3,000 |
| ② | 4月20日の消耗品購入代支払いが 2,500円のところを 1,500円と記録 | △ 1,000 |
| ③ | 4月25日に未払費用を計上するところを現金支払いとして処理 | 1,000 |
| ④ | 不明差額(現金過不足) | △ 2,000 |
| 計 | △ 5,000 |
(注)△ : 現金出納帳の残高より実際の現金残高の方が少ない。
①は実際には支払時に現金が3,000円減っているはずなのに、現金出納帳(あるいは会計仕訳)上ではその計上がモレてしまっており、実際の現金残高の方が3,000円少ないという状況です。
また、②は実際の支払いが2,500円であったのに1,500円の支払いとして現金出納帳に記録したため、実際の現金残高の方が1,000円少ないという状況です。
③はまだ支払いがなされていない費用を未払費用計上すべきところを、支払いがあったものとして現金出納帳に記録してしまったため、実際の現金残高の方が1,000円多いという状況です。
残りが、まだ差異の内容が判明していない不明差額ということです。
現金を実査してストックを確かめなければ、①の費用計上モレや、②の費用計上金額誤り、③の未払いを支払済として処理した誤りなどの問題があることに気付くのはなかなか大変だったでしょう。もちろん、フローの方に着目して、毎回毎回すべての入出金処理に誤りがないかを確認し直せば、気付くことができるかもしれません。しかし、これではとても大変ですし、非効率です。むしろ、まずストックを確かめることによって、そこで見つかった問題を取っ掛かりとして、詳細な調査が必要なのかどうかを判断する方が効率的です。
また、フローだけに着目していたら、④の不明差額(現金過不足)が生じていることにも気付かなかったでしょう。④についてはある意味、現金(現物)の管理に関する弱点を現しているとも言えます。これは、どんなにフローの部分を間違いなく処理したとしても、現物の管理がしっかりできていなければ生じ得るものと言えます。
なお、①から③については、正しい処理に修正する必要があります。また、④の不明差額については、入出金の処理誤り、盗難、紛失などの可能性があり、重要性も踏まえてさらなる調査をするかどうかを検討することになるでしょう。
また、①から④として挙がった「差異の内容」について、さらにそれが生じた原因を追及していくことが重要です。原因を追及していくことで、日頃の入出金取引の処理に関する弱点が見えてきたり、現金(現物)の管理に関する弱点が見えてきたりするはずだからです。こうした弱点を放置していたら、今後も同じような問題が繰り返されることになります。したがって、見つかった弱点を放置することなく改善していくこともまた、大事な業務となるでしょう。
これらのことから、「フローだけを見るのではなく、ストックの視点を大切にし、それを使ってフローを検証してみる」ことの重要性がお分かり頂けると思いますので、ストックの視点を大切にすることを、経理業務を行う上でも是非とも念頭に置いて頂きたいと思います。
【シーン2】
期中のある日のこと。現金実査の結果、帳簿残高との間に差がありました。入出金業務担当スタッフSさんに調べてもらったところ、すぐに原因が分かりました。昨日の現金実査の段階では差異は生じておらず、今日の入出金取引から差異が生じたと考えられるからです。
スタッフSさん「今日の経費精算の処理に一部誤りがありました。すぐに誤りを修正します」
処理誤りを皆無にすることはできないかもしれませんが、万が一誤りが発生しても、タイムリーにそれに気付き、誤りを修正することができるようになったようです。
3.おわりに ~現金実査から経理の心得を学ぼう
今回から3回にわたってお伝えする「現金実査から学ぶ、経理の心得」は、私が財務諸表監査で現金実査を行う中で経験してきたものを念頭に、経理の心得として整理してみたものです。中でも、今回取り上げた「ストックの視点を大切にする」ことは、経理部門のスタッフや経理部長の方々にとって、最も重要ではないかと思います。入出金(フロー)の記録に生じる誤りを効率的に発見できたり、現金(現物)の管理に関する弱点が見えてきたりといった効果が期待できるからです。
そして、ストックの視点は何も現金実査に限りません。「売上取引」というフローに対する「売掛金」というストック、「棚卸資産の入出庫」というフローに対する「棚卸資産」残高など、フローにはストックが付き物です。現金と売掛金や棚卸資産ではストックを確定するタイミングや頻度は異なるでしょうが、今回ご紹介した「ストックの視点を大切にする」ことの重要性は、これらにも通じるはずです。
是非、読者の皆様が、「ストックの視点を大切にする」ことを念頭に置きつつ、ご自身に関わる業務を行って頂ければ幸いです。