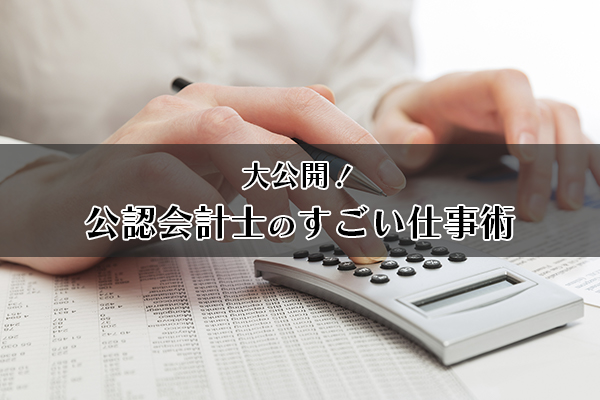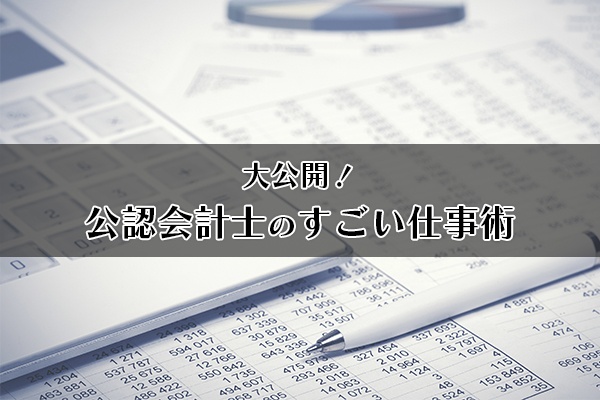網羅性チェックは“モレを見つけるためのチェック”でしたが、実在性チェックは“あるはずのものが本当にあるのかのチェック”です。そのチェック方法について、経理に関わるシーンに当てはめながら考えてみようと思います。網羅性チェックと併せて、実在性チェックも活用して頂ければ、きっと皆様にとって強力な武器になるはずです。
2.ケースで考える ~あるはずのものが本当にあるのかをチェックする方法(その1)
まずは、経理部長と経理スタッフのやり取りの様子を描いた【シーン1】をご覧ください。【シーン1】
経理部長「何か先月末の売掛金の残高、いつもより多いな。多過ぎるんじゃないか?本当にこんなに売掛金があるの?」
Sさん「確かに多いですね。少々お待ちください……」
とは言ったものの、Sさんはどう対応したら良いものか、すぐには思い付かないのでした。
まずはチェックすべき対象の当たりを付けるために概括的なチェックを先に行うことが考えられますので、その方法として「(1)比較分析」と「(2)帳簿上の相関関係のチェック」を取り上げます。いきなり細かいチェックに入る前に、比較的手間のかからない方法として使ってみてください。
その上でさらにチェックが必要であれば、より詳細なチェックを行うことになるでしょう。そこで、詳細チェックの入り口として考えられる方法をその次に取り上げます。それが「(3)勘定残高と内訳明細資料との整合性チェック」です。
その後に、「(4)現物があるものは現物を直接チェック(実査・棚卸)」や、次回説明する他の方法など、実在性をチェックするための各種方法を取り上げることにしますので、次回分も併せてお読み頂き、チェック対象に適した方法を使ってみてください。
(1)比較分析
ある勘定科目の金額について実在性をチェックする上では、計上額の比較分析を行うことが基本となることは、網羅性のチェックの場合と同様です。典型例としては、対前期比較や月次推移分析が挙げられます。【シーン1】ではいつもより残高が多い・少ないといった比較を行っている様子が描かれています。もしも、前期の残高と比較して著しく多い、他の月と比較して著しく多いといったことがあれば、本当にそれだけの残高があるのかという意識を持つことが必要かもしれません。
(2)帳簿上の相関関係のチェック
帳簿上に計上されている金額を使って、他の勘定科目の帳簿金額との相関関係をチェックすることは、大局的に実在性をチェックするのに効果を発揮する方法の一つです。例えば、試算表上の売掛金残高と売上高(あるいは売上原価)との相関関係を見るために、売掛金の回転期間という経営指標をチェックすることができます。
売掛金回転期間 = 売掛金残高 ÷ 売上高
そうすると、売掛金の残高と売上高との相関関係を見る「売掛金回転期間」には、あまり変化がないといった状況が想定されます。ところが、前期と当期の回転期間を比較した結果、当期は前期よりも大幅に長くなっていたとしたらどうでしょう。もしかすると(故意か誤りかは別として)、「架空の売掛金が計上されてしまっている」などといったことが起きているかもしれないのです。
回転期間のような経営指標を使って、帳簿上の相関関係をチェックし、そこに大きな変化が現れているとすると、そこには実在性に疑義のある残高が潜んでいるかもしれないのです。
(3)勘定残高と内訳明細資料との整合性チェック
勘定残高と内訳明細資料との整合性をチェックすることも、実在性チェックの一つです。例えば、「試算表上の売掛金残高」と、得意先別の売掛金残高を管理する「内訳明細資料の合計残高」とが整合しているかをチェックすることが考えられます。本来であれば、これらは一致して当然なのですが、営業担当者が手元で管理している台帳の売掛金残高を合計しても、試算表の残高よりも少なくなっていて、中身のはっきりしない残高が試算表上に計上されているといった場合などには両者の間に不整合が生じます。このように、両者の整合性をチェックした結果、実在性に疑義のある資産が見つかることもあり得ます。
また、勘定残高と内訳明細資料とが整合していたとしても、内訳資料の中に、「その他」や「諸口」など、内容が不明瞭なものがある場合には、実在性に疑義がある場合もありますので、そうしたものがないか、ある場合は適正なものかをチェックすることが必要になることもあるでしょう。
(4)現物があるものは現物を直接チェック(実査・棚卸)
実在性をチェックする方法の中でも最も強力なのが、現物を直接チェックする方法です。特に資産については、本当にあるのかどうかをチェックしようと思ったら、「百聞は一見に如かず」で、とにかく現物に当たることが大事です。例えば、現金の入出金を行い、その入出金を現金出納帳に記録しているとします。現金出納帳には入出金の記録の他、現金残高も載っているはずです。ただし、現金出納帳という帳簿上の現金残高分の現金が本当にあるのかどうかは分かりません。本当にあるかを確かめようと思ったら、実際に金庫等に保管されている現金を数えることになるでしょう。
また、期末日の試算表上の「受取手形」残高が本当にあるかを確かめようと思ったら、当日、金庫等に保管されている受取手形を実際に見て、その金額を合計することで実在性をチェックできます。
このように、帳簿や試算表等に載っている資産の数量や金額について、現物の数量や金額を確かめることを「実査」(じっさ)と言います。先に挙げた現金や受取手形の他に、定期預金証書や、株券等の有価証券、器具備品や機械装置等の有形固定資産なども実査の対象となります。
また、商品・製品や原材料等の棚卸資産も、現物の数量や金額を確かめて実在性をチェックします。例えば、商品の入出庫を行い、その入庫・出庫を商品受払帳に記録しているとします。商品受払帳には入出庫(数量や金額)の記録の他、残(数量や金額)も載っているはずです。ただし、商品受払帳という帳簿上の商品残高分の商品が本当にあるのかどうかは分かりません。本当にあるかを確かめようと思ったら、実際に倉庫等に保管されている各商品を数えることになるでしょう。なお、棚卸資産については実査ではなく「棚卸」(たなおろし)と言われます。
いずれにせよ、現物を目で見ることのできる有形の資産について、その実在性を確かめるには実査・棚卸を行うことが最も強力な手続きです。
□実査
現金、定期預金証書、受取手形、株券、有形固定資産など
□棚卸
棚卸資産(商品、製品、原材料、仕掛品など)
3.おわりに ~実在性チェックの力を鍛えよう
実在性チェックの視点は網羅性チェックの視点と対になる視点であり、網羅性チェック同様、経理上も大切です。今回と次回で、この実在性チェックについて詳しく説明することとし、実在性チェックの方法のうち、今回はまず、(1)比較分析、(2)帳簿上の相関関係のチェック、(3)勘定残高と内訳明細資料との整合性チェック、 (4)現物があるものは現物を直接チェック(実査・棚卸)、の4つを説明しました。これ以外にもとても重要な実在性チェックの方法があるのですが、残りは次回取り上げることとしたいと思います。次回の説明と併せて、経理上も大切な実在性チェックの方法を知って頂き、その力を鍛えて実務に活かして頂けますと幸いです。