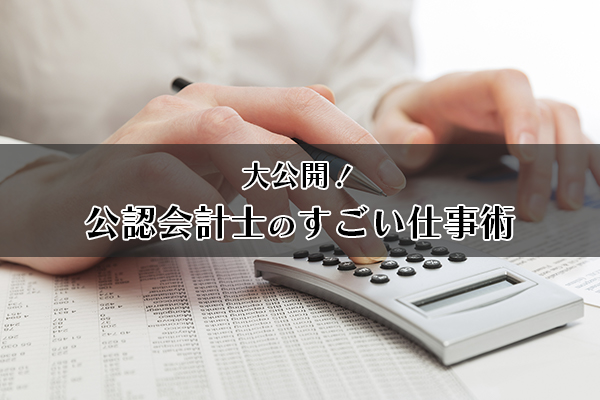2.ケースで考える ~「モレ」を見つける難しさとその対処法(その2)
まずは、経理部長と経理スタッフのやり取りの様子を描いた【シーン1】をご覧ください。【シーン1】(前回と同じ)
経理部長「何か先月末の未払金の残高、いつもより少ないな。本当にこんなに少ないの? 計上がモレているんじゃないか?」
Tさん「確かに少ないですね。少々お待ちください……」
とは言ったものの、Tさんはどう対応したら良いものか、すぐには思い付かないのでした。
- 比較分析
- 勘定残高と内訳明細資料との整合性チェック
- マイナス残高のチェック
- 帳簿上の相関関係のチェック
- 事後の状況フォロー
(6)オーバーオール・チェック(概算チェック)
オーバーオール・チェックというのは、何らかの方法を使って概算額を算出し、それと実際の帳簿計上額とを比較することによって、両者の間に異常な差異がないかをチェックする手法です。数値を何となく眺めていても、なかなか異常点には気付かないものですが、オーバーオール・チェック(概算チェック)の手法を活用すると、異常値に気付きやすくなります。ポイントは概算でのチェックだということです。精緻に計算してチェックしようとすれば、どうしても相当の時間がかかってしまいますが、異常点を見つけるには、いきなり精緻な計算をするのではなく、まずは概算チェックで異常があるのかをスピーディーにチェックすることが有効です。
ここでは、支払利息計上額のチェックを例に、オーバーオール・チェックの仕方を示すことにします。「支払利息の概算額」は、以下のように算出することができます。
借入金平均残高 × 平均利率
他にも様々なオーバーオール・チェックがありますので、詳しくは『公認会計士の仕事術-第31回』をご参照ください。
(7)連番チェック
モレが生じたときに、それに気付きやすくする方法として、連番チェックも挙げることができます。予め連番を付けておけば、万が一、一部の番号が抜けた場合には、発見がしやすくなるはずです。例えば、支払手形について考えてみましょう。皆様は支払手形のつづりを見たことがあるでしょうか。仕入代金を手形払いする場合、支払手形のつづりから所定の事項(相手先や金額など)を記載した手形を1枚切り離して、仕入先に渡すことになりますが、支払手形には予め連番が付けられています。支払手形を発行する場合には、支払手形のつづりから適当に1枚切り離すのではなく、番号の小さい方から順番に使用していきます。万が一、書き損じをしてしまった場合でも、当該手形を廃棄してしまうのではなく、書き損じてしまった手形を使用できないようにした上で、しっかりと保管しておくようにします。このように、何番から何番までの手形を使用したか、書き損じ等で使用しなかった手形は何番なのかといった連番での管理を行うことで、知らないうちに支払手形が発行されて、簿外の債務になるような事態を防ぐことができます。
領収書などについても同様のことが言えます。売上代金を現金や小切手で回収した場合、得意先に対して領収書を発行することになりますが、領収書のつづりに予め連番を付け、使用状況を管理することで、知らないうちに営業担当に領収書が使用されて売上代金を横領されてしまうといった事態を防ぐことができます。
(8)帳簿以外の関連資料等(非財務資料等)に着目する
網羅性チェックを帳簿金額だけでチェックするのには限界があります。そもそも帳簿に載っていないもので帳簿に載せるべきものがないかというのが網羅性チェックの視点ですから、網羅性をチェックしようとしたら、帳簿以外の資料にも目を向ける必要があるでしょう。第一に挙げられる資料としては、取締役会や経営会議などの議事録や、稟議書等の決裁関係の資料です。つまり、各種の案件の審議をしたり、決裁をしたりした資料に目を通すことです。会社によって、審議や決裁の仕組みは違うでしょうが、これらの資料には、重要な取引や特別な取引等に関する情報が含まれ、経理処理すべきもの、どのように経理処理すべきか検討を要するものなどが含まれているはずです。審議・決裁の資料に目を通すことで、帳簿への計上がモレていないかをチェックする材料になります。
例えば、設備投資に関わる決裁がされていれば、固定資産への計上や、それに対応する債務の計上が必要になります。決裁がされ、取引が実行されているにもかかわらず、帳簿に載っていなければ、計上モレのおそれがあるわけです。
この場合の観点は、「帳簿」から「資料等」への流れではなく、あくまでも「資料等」から「帳簿」への流れであることがポイントです。議事録等があって、本来であれば帳簿に資産や負債が載っているはずであるにも関わらず、それが載っていなければ、帳簿への計上モレのおそれがあります。
このように、「資料等」から「帳簿」に当たるという流れは、他の資料にも通じます。例えば、契約書や請求書等の資料に目を通し、それに関連する資産や負債が帳簿に載っていることをチェックするといったこともその一つです。
また、第三者から得た回答、例えば、自社の仕入先に対して先方の売掛金残高がいくらあるのかを問い合わせ、その回答をもらうのもその一つです。自社の買掛金残高よりも、仕入先側の売掛金残高の方が大きかった場合、その原因を追及することで、買掛金(仕入)の計上モレが見つかることもあります。
応用編になりますが、ここでの「資料等」には「企業を取り巻く環境等に関する情報」まで含めて考えることもできます。例えば、新型コロナウイルス感染症の拡大で売上が激減し、在庫が膨らんでしまい、当該在庫が不良化してしまうといったこともあり得ます。環境等に関する情報に目を向けることで、在庫の評価減の計上モレがないか注意が必要かもしれないといった予測が働くこともあるでしょう。
【シーン2】
あれから半年が経ち、経理スタッフとして成長著しい今のTさん。
経理部長に言われるまでもなく、仮締めの試算表の段階で残高比較をしっかり実施し、今月計上されるはずのX工場における設備投資の未払計上がまだ済んでいないことに気付きました。また、月々発生するはずのある経費項目の未払計上もまだ済んでいないことに気付きました。
速やかに担当部署に連絡し、計上モレになるのを防ぐことができました。
また、経理部長も、稟議書などに目を通し、会計処理に影響する案件について経理スタッフに共有してくれていることも、計上モレ防止に功を奏しているようです。
3.おわりに ~経理上も大切な網羅性チェック、その視点を活用しよう
前回と今回の2回にわたってお伝えした網羅性チェックのための各種の方法は、私が財務諸表監査を行う中で経験してきたものを念頭に、整理してみたものです。経理部門のスタッフや経理部長の方々は、誤ったものを帳簿に計上しないという意識を持つことが大切ですが、それに加えて、帳簿に載るべきものがモレていないかという意識も持っている必要があります。そのためには帳簿以外の資料等にも注意を向ける必要があるでしょうし、必要な情報が経理部に集まる仕組みを設けることも必要でしょう。また、業務を行う際に、行き当たりばったりで処理をするのではなく、決まったやり方できちんと処理することも、モレ防止に有効です。
網羅性チェックの方法は一つではありません。上述したように様々な方法がありますし、これら以外のものも多々あることでしょう。
経理に関わる業務を念頭に網羅性チェックの話を進めましたが、経理部門以外の方も含めて、是非、読者の皆様がご自身に関わる業務を行われる際に、網羅性チェックの視点を活用して頂ければ幸いです。