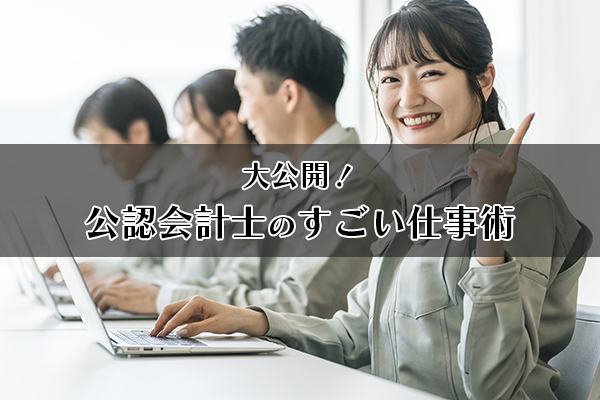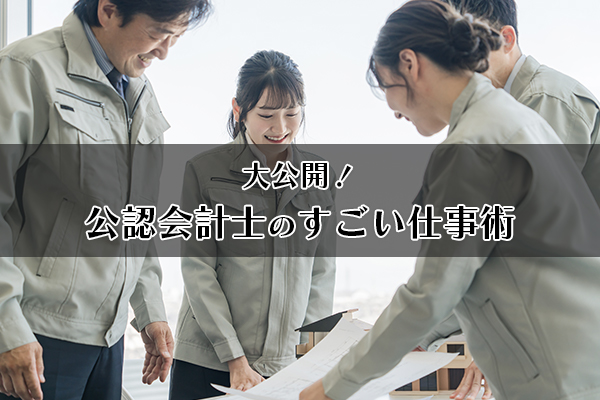「原価管理①」では、人の生産性アップにつながる原価管理の仕組み作りの第一歩として、「実績時間の把握」に絞って話を進めました。
「原価管理②~③」では、実績時間を把握した後のステップである、「実績時間の分析」に話を進め、実績時間が多いのか少ないのかを判断するためのモノサシが必要であること、そして、モノサシの一つとして計画値を挙げ、タイムリーかつ効率的に分析するための仕組みについても説明しました。
「原価管理④」では、実績時間の分析から対応策を検討する際に気を付けたいポイントについて説明しました。
「原価管理④」までは基本的に「時間」に基づく分析についてのみ説明してきましたが、「原価管理⑤」からは、さらに「金額」に基づく分析に話を進め、金額につなげるための土台作りとして、従業員をいくつかのランクに分け、ランクごとの業務単価を設定する方法について説明しました。
今回は、ランクごとの業務単価を設定した結果、どんな分析ができるようになるのかについて説明することにします。
2.ケースで考える ~時間の分析を金額の分析につなげる方法(その2)
ここまでの説明で、実績時間を把握したり、実績時間を計画時間と比較分析したりすることで、人の生産性に関わる課題にたどり着けることがお分かりいただけたものと思います。一方で、時間という非財務数値のみを分析しても、会社の決算数値にどの程度の影響があるのかがよく分からないとも言えますので、時間の分析を金額の分析につなげる方法を考える必要があります。前回説明したとおり、ランクごとの業務単価を設定することで金額の分析につなげる土台ができたとして、次に考えることは金額に基づいてどのような分析ができるのかです。今回は、この点についてケースを使って考えてみることにしましょう。まずは、ある監査法人での出来事を描いた次の【シーン1】をご覧ください。舞台となっているX監査法人は前回以前と同じです。その業務の概要や抱えている問題については、前回以前の各シーンをご参照ください。
【シーン1】
X監査法人の本部では、業務時間の超過が一定時間以上の監査チームをピックアップし、当該監査チームにそれぞれ業務効率化の検討を指示しました。
指示を受けた監査チームは業務時間が計画を超過しないようにするために、どんな業務であろうとどうしても時間がかかってしまいがちな新人スタッフを使う代わりに、経験豊富な中堅以上のスタッフを使うことにしました。
これによって、業務時間は計画内に収めることができたのですが、結果的に監査チームの採算は悪化してしまったようなのです。
業務時間は計画どおりであるにも関わらず、一体、なぜこのような状況になってしまったのでしょうか。
それでは、この点についてもう少し詳しく解説していきましょう。
(1)時間だけの分析と金額も含めた分析の違い
【図表1】は、X監査法人における監査先ごとの業務時間の集計表のうち、監査先T社の部分を抜粋したものです。(注)当該集計表については、「公認会計士の仕事術」の「第34回 人の生産性アップにつながる原価管理②」において具体的に説明していますので、必要に応じてそちらもご参照ください。
X監査法人では、監査先ごと(=監査チームごと)の単位で、その業務に誰が、いつ、どれだけの時間を使うかをブレイクダウンして計画を立てていました。そうすることで、当該業務についての計画時間が、メンバー別・時期別に内訳(タイムシートの提出時期に対応した時期別)に展開でき、【図表1】のようなかたちで、各メンバーのタイムシートによる報告に基づき、業務時間の実績値が出たタイミングでタイムリーに計画値と比較することが可能になっています。
【図表1】監査先ごとの業務時間集計表
監査先:T社
| メンバー | 当月までの累計 (単位:時間) |
||
|---|---|---|---|
| 実績時間 | 計画時間 | 差異 | |
| Kさん | 40 | 10 | 30 |
| Lさん | 50 | 30 | 20 |
| Mさん | 80 | 60 | 20 |
| Nさん | 28 | 100 | △72 |
| 合計 | 198 | 200 | △2 |
【図表1】を見ると、合計実績時間は198時間で、計画時間(200時間)内に収めることができていることが分かります。この情報だけ見た監査法人の本部は、T社にかかる監査チームは今の調子で業務を進めてもらって構わないと判断することでしょう。
しかし、【図表1】にあるのはあくまでも「時間」に関する情報だけであり、金額的なインパクトが分からないということに注意する必要があります。そこで、【図表1】に業務単価に関する情報も追加してみます。きっと見え方が大きく変わってくるはずです。
【図表2】監査先ごとの業務実績時間並びにコスト集計(その1)
監査先:T社
| メンバー | 1時間当たり の業務単価 |
当月までの累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 実績時間 | 計画時間 | 差異 | ||
| Kさん | 8,000円 | 40時間 | 10時間 | 30時間 |
| 320,000円 | 80,000円 | 240,000円 | ||
| Lさん | 6,000円 | 50時間 | 30時間 | 20時間 |
| 300,000円 | 180,000円 | 120,000円 | ||
| Mさん | 4,000円 | 80時間 | 60時間 | 20時間 |
| 320,000円 | 240,000円 | 80,000円 | ||
| Nさん | 2,000円 | 28時間 | 100時間 | △72時間 |
| 56,000円 | 200,000円 | △144,000円 | ||
| 合計 | - | 198時間 | 200時間 | △2時間 |
| 996,000円 | 700,000円 | 296,000円 | ||
【図表2】ではまず、【図表1】に各メンバーの「1時間当たりの業務単価」の記載が追加されています。従業員のランクごとに1時間当たりの業務単価を設定する方法については前回説明したとおりです。ここでは【図表3】のように業務単価が設定されており、Kさん、Lさん、Mさん、Nさんの従業員ランクはそれぞれDランク、Cランク、Bランク、Aランクです。
【図表3】従業員ランクごとの業務単価
| ランク | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1時間当たり の業務単価 |
2,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 8,000円 |
そして、当該業務単価を実績時間や計画時間に乗じることで、非財務情報である「時間」だけでなく、財務情報である「コスト」も示されています。
それでは、ランクごとの業務単価を設定した結果、どんな分析ができるようになるのでしょうか。
上述のとおり、合計時間だけを見ると計画時間(200時間)内に収まっており、順調そうに見えたT社にかかる監査チームですが、問題はコストにありました。【図表2】を見ると、700,000円のコストを計画していたところ、実績は996,000円で、296,000円もオーバーしていることが分かります。実に42.3%ものコストオーバーとなっていたわけです。
これは、最も業務単価の低いNさんの業務時間が計画より少なかったものの、その4倍の単価のKさん、3倍の単価のLさん、2倍の単価のMさんの業務時間が多かったことが影響しています。
このように、「時間」だけで判断すると監査先T社の監査チームの業務には問題がないように見えるのですが、「金額」(コスト)で判断するととんでもない問題業務であったと言え、時間の分析だけでなく金額も分析できるようにすることが望まれます。
(2)問題案件の見つけ方
X監査法人はT社以外にも数多くの監査先を有しており、その中からX監査法人の本部が法人全体の業績に大きな悪影響を及ぼしそうな監査チームの業務を見つけるのは大変です。問題のある監査チームを見つけようとする場合、「時間」がどれだけ計画をオーバーしているかよりも、「金額」(コスト)がどれだけ計画をオーバーしているかに着目するようにします。その場合、例えば、コストオーバーの額が一定水準以上の監査チームや、コストオーバーの率が一定水準以上の監査チームを定期的に洗い出し、本部はその状況を監査チームに確認するなどして、問題があれば改善を促していくようにすることが考えられます。
「公認会計士の仕事術」の「第34回 人の生産性アップにつながる原価管理②」においては、実績時間の分析をタイムリーかつ効率的に実施するための仕組みについて説明しました。これは「時間」の分析のみならず、「金額」の分析にも当てはまります。
①分析のタイミングを遅らせない仕組み
業務のコストがかかり過ぎていないかという問題を早め早めにつかもうとした場合、計画コストと実績コストの比較がタイムリーに実施できるかがポイントになってきます。既に業務の終盤に差し掛かっている段階でいくら分析しても、分析のタイミングが遅くその後に挽回しようとしてもなかなか難しいものがあります。そうならないためには、途中途中の段階で、実績コストがかかり過ぎていないかをチェックすることです。その方法としては次のような方法が考えられます。
計画コストに対する実績コストの割合を出して、計画コストの何%のコストを既に使ったのかを計算し、これを業務の進捗度合いなどと比較してチェックする方法です。
例えば、全体の4割程度しか業務が進んでいないのに、コストが既に6割もかかってしまっているとしたら、コストがかかり過ぎている可能性が高く、早急に対策を講じる必要があるでしょう。
計画を立てる際に、どの段階でどれだけのコストがかかるかまでブレイクダウンしたものにしておく方法です。計画値が月別にブレイクダウンされていれば、月ごとに計画コストと実績コストとの比較が可能です。
②分析の効率を上げるための仕組み
計画値と実績値を比較する場合の「判断基準」を設定しておくと、分析の効率を上げることができます。例えば、「計画コストを何%以上超過している場合」とか、「計画コストをいくら以上超過している場合」といった具合に判断基準を設定し、これに該当する業務(【シーン1】では監査先)をピックアップするのです。もっとも実績コスト自体が少ない場合は影響が小さいので、前述の基準に「実績コストがいくら以上」といった基準を追加したほうが良いかもしれません。つまり、「実績コストがいくら以上、かつ、計画コストを何%以上(orいくら以上)超過している場合」といった具合です。
もし、対象業務がたくさんある場合には、あらかじめ定めた判断基準に該当するものが発生したときに自動的にアラート(警告)が出るようシステムの設定をしておくことで、基準に該当して問題がありそうな案件を効率的にピックアップしてくれるので、見落とさずに済みます。
なお、補足になりますが、監査業務の場合は監査先ごとに監査報酬という収益(売上)が発生します。ここまでの説明では、計画コストと実績コストの比較分析の観点から行ってきましたが、監査先ごとの収益とそれに対するコストが分かれば、監査先ごとの採算もつかめます。実際にはコストは人件費だけではありませんので、人件費以外の経費等も監査先ごとに集計する必要がありますが、監査先ごとに業務の採算がつかめれば、監査法人の本部としては、例えば、一定金額以上の赤字が見込まれる監査先をピックアップして、当該監査チームに採算改善に向けての対策の検討を促すこともできます。
以上を踏まえた結果、【シーン1】に描かれた問題は、【シーン2】のように改善がされました。
【シーン2】
X監査法人の本部では、実績コストが一定金額以上で、かつ実績コストが計画コストを一定金額以上上回ると見込まれる監査チームをピックアップし、当該監査チームにそれぞれ業務効率化の検討などの対応策を出すよう指示しました。
以前は、新人スタッフの業務時間を減らし、代わりに経験豊富な中堅以上のスタッフの業務時間を増やすといった安易な対応策が監査チームにおいて行われることがありましたが、そうしたことはなくなりました。なぜなら、このような対応策では当該監査チームのコストがさらに増加し、当該監査チームの採算を一段と悪化させてしまうからです。
金額に基づく分析を行うようにしたことで、当該監査チームは採算悪化を見落とすことなく、タイムリーに適切な対応を検討することができ、業務終了段階では採算悪化を食い止めることができました。X監査法人の本部の思う方向に監査チームの改善が進み始めたようです。
3.非財務数値である「時間」を、財務数値につなげて分析する
人の生産性アップにつながる原価管理の仕組み作りのうち、1回目では「実績時間の把握」を、2~3回目では「実績時間の分析」について、「実績時間の分析から対応策を検討する際に気を付けたいポイント」など、例を挙げながら説明してきました。そして前回と今回を通じて、非財務数値である「時間」を、財務数値(決算数値)につなげて分析するための仕組みについて説明しました。
今後、原価管理の仕組み作りを検討する上での参考にしていただければ幸いです。