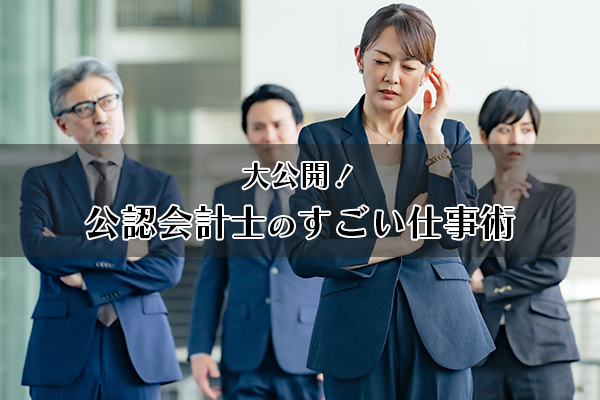2.ケースで考えるオーバーオール・チェック
それではオーバーオール・チェックとは一体どんなものなのでしょうか。いくつかの例を使って見ていくことにしましょう。まずは【シーン1】をご覧ください。【シーン1】
ある日の経理部門でのことです。当期の決算作業の終盤を迎え、S経理部長が損益計算書に目を通しつつ、担当のTさんを呼びました。
S経理部長「Tさん、ちょっといいかな。頼んでおいた販管費の前期比較増減分析なんだけど、どうなってるかな?」
経理担当Tさん「はい。前期と比べて給料手当がだいぶ増えていまして……。各月の給与明細なんかも取り寄せていろいろ調べているんですが、もう少し時間がかかりそうです。」
S経理部長「えっ、給料手当だったらこのくらい増えていて当然じゃないか。だって……。」
【シーン1】では、販管費の「給料手当」の計上額が前期と比べて著しく増加しているため、その原因を突き止めようといろいろな資料を取り寄せ、分析に時間を使い過ぎているTさんの様子を描いています。給料手当の計上額が著しく増加していることを当然だと考えているS経理部長と、分析に時間を使い過ぎているTさんの違いは何だったのでしょうか。実は、S経理部長が習慣にしているのがオーバーオール・チェックと言われるチェックで、給料についてもオーバーオール・チェックをしていたのです。
(1)給料のオーバーオール・チェック
実は【シーン1】でS経理部長は、何となく決算数値を眺めていたわけではなく、自分なりに次のようなチェックをしていたのです。【シーン2】
前期の1人当たり給料月額 × 12か月 × ベースアップ率 × 平均従業員数
M社では当期に営業所を増設するなど従業員数が10%程度増加していました。また、当期は給与規定(給与テーブル)の改訂があって、2%程のベースアップもありました。概算すると前期と比べて12%程度増加すると見込まれました。
実際、全社の給料手当計上額は見込みどおり、前期と比べて12%程度増加しており、著しく増加していることには合理的な説明がつく状況だったのです。
【シーン2】のように、概算でのチェックをして合理的な説明がつくのであれば、いきなり詳細な資料の分析に時間をかけなくても済むのです。
逆に、こういった概算チェックの視点を持っていれば、前期比較して著増減がないからといって異常なしで終わらせずに、著増減がないことの異常性にも気づくことができます。例えば、今回のM社の例に当てはめれば、決算書上の給料手当計上額が前期とほぼ同額だったとしたら、むしろそのほうが異常で、その原因を追及する必要が出てくるということです。その結果、決算月の残業代の計上が漏れていること、一部営業所で未払給料の計上が漏れていることなどの問題が生じていたことが判明することもあり得ます。
なお、実際に給料のオーバーオール・チェックをする際には、「1人当たり給料月額」が異常な金額になっていないかにも留意しましょう。「1人当たり給料月額」は、自分の給料などと照らし合わせてみるとイメージしやすい金額かと思います。高過ぎるのではないか、逆に低過ぎるのではないかといった感覚も持ちやすいので、それらも踏まえて、異常がないかをチェックすると良いでしょう。
【シーン1~2】は卸売業が舞台でしたが、製造業の場合には販管費と製造原価の両方に給料が計上されますので、両者を分けて概算額を算出したほうが良いでしょう。
重要なベースアップがなければ、「ベースアップ率」は無視して構いませんし、人の変動(入退社)が激しくなければ、「平均従業員数」は前期末と当期末の平均値で構いません。
【シーン1~2】では「給料のオーバーオール・チェック」を取り上げましたが、「給料」以外にもオーバーオール・チェックができる場面はいろいろあります。以下、いくつかを紹介することにします。
(2)支払利息のオーバーオール・チェック
「支払利息の概算額」は、例えば以下のように算出することができます。借入金平均残高 × 平均利率
この概算額と実際の支払利息計上額とを比較し、異常な差異がないかをチェックします。
「借入金平均残高」は、前期末と当期末の平均値とすることも考えられますが、ある程度の変動がある場合には毎月末残高の平均値を使うことが考えられます。
「平均利率」は、例えば前期末の借入金残高明細の加重平均利率を算出して使用することが考えられます。
なお、こうしたチェックが面倒であれば、「支払利息計上額÷借入金平均残高」で利率を概算し、異常な利率になっていないかをチェックするだけでも概算チェックの意味があります。
(3)減価償却費のオーバーオール・チェック
「減価償却費の概算額」は、例えば以下のように算出することができます。減価償却資産の平均残高 × 平均償却率
この概算額と実際の減価償却費計上額とを比較し、異常な差異がないかをチェックします。
「減価償却資産の平均残高」は、定額法で償却している場合は減価償却累計額控除前の金額を使用し、定率法で償却している場合は減価償却累計額控除後の金額を使用し、前期末と当期末の平均値とすることが考えられます。
「平均償却率」は、例えば「前期の減価償却費÷減価償却資産の平均残高」で算出することなどが考えられます。当該償却率は耐用年数表に照らして概ね何年の耐用年数に対応するものかをチェックし、会社保有の主な減価償却資産の耐用年数と比較して異常値でないかチェックした上で使用したほうが良いでしょう。実務では税法上の減価償却限度額よりも相当少ない額で減価償却費を計上することもあるので、その場合はおそらく実態よりも長い耐用年数の償却率になっているはずです。
なお、減価償却資産には、建物、建物付属設備、構築物、機械装置、車輛運搬具、工具器具備品などが含まれ、耐用年数にも幅がありますので、これらの種類ごとにオーバーオール・チェックを行うとより精度が増します。
また、製造業では、販管費と製造原価の両方に減価償却費が計上されますので、両者を分けて算出することが考えられます。
(4)税率のオーバーオール・チェック
「概算の税率」は、例えば以下のように算出することができます。法人税等の計上額 ÷ 税引前当期純利益
この概算税率を法定実効税率や前期の概算税率と比較し、異常な乖離がないかをチェックすることも考えられます。
(5)仮受消費税、仮払消費税のオーバーオール・チェック
① 仮受消費税発生額の概算
「仮受消費税の概算額」は、例えば以下のように算出することができます。(売上高 - 輸出売上高)× 消費税率(10%)
この概算額と実際の仮受消費税発生額(期中の貸方計上額合計)とを比較し、異常な差異がないかをチェックします。
② 仮払消費税発生額の概算
「仮払消費税の概算額」は、例えば以下のように算出することができます。(仕入高 + 販管費・製造原価のうち課税対象の科目の合計)× 消費税率(10%)
この概算額と実際の仮払消費税発生額(期中の借方計上額合計)とを比較し、異常な差異がないかをチェックします。
「販管費・製造原価のうち課税対象の科目の合計」を算出するのは面倒かもしれませんが、あくまで概算チェックなので、販管費・製造原価の合計から、消費税がかからない主な科目(例えば、給料・賞与・法定福利費・減価償却費・保険料・租税公課)の額を控除して算出してみることが考えられます。
オーバーオール・チェックをした結果、概算額と実際の計上額との間に著しい乖離が生じていることが分かったとしたら、その原因を追及することにします。その結果、例えば以下のような処理誤りに気づくことができたりします。
・誤って輸出売上に仮受消費税を計上していることに、気づくことができた
・誤って非課税の保険料に仮払消費税を計上していることに、気づくことができた
概算チェックをすることは、数値を扱う部署の担当者にとっても大切ですが、管理者にはより大切ではないかと思います。管理者は、部下の仕事の詳細まではなかなかチェックが行き届かないでしょうし、その必要もないかもしれません。だからこそ、部下の仕事が「だいたい合ってそうだ」ということを確かめることが大切になります。そんなときに、オーバーオール・チェックを活用してみてはいかがでしょうか。
3.オーバーオール・チェックを使って、「木を見て森を見ず」を回避しよう
今回は、「だいたい合ってそうだ」、あるいは逆に「これっておかしいのではないか?」という感覚をつかむために役立つオーバーオール・チェックをご紹介しました。オーバーオール・チェックをして、重要な間違いなどがなさそうかを確認するようにすれば、大きな過ちを見過ごすことも減らせるでしょうし、必要以上に詳細なチェックに時間をかけることなく業務効率を上げることもできるでしょう。
今回取り上げた「オーバーオール・チェック」を是非参考にして頂ければ幸いです。