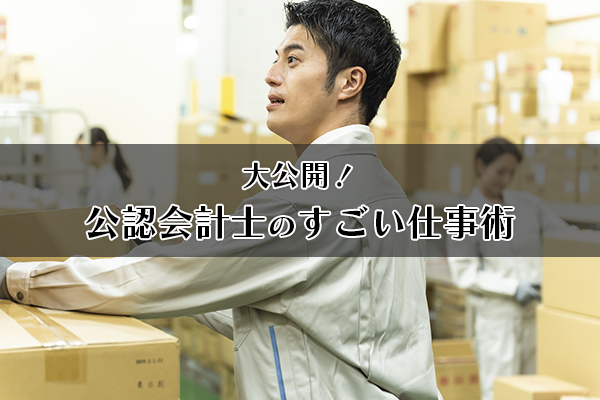2.ケースで考える ~実地棚卸に関わる不正からの学び(その4)
本稿では、実地棚卸に関わる不正について検討を進めるに当たり、実地棚卸に関連したいくつかの不正の例を挙げた上で、主としてどの段階で行われる不正なのかという観点で【図表1】の(1)から(3)のように整理しています。【図表1】実地棚卸での段階ごとの不正の例
- サンプル品・預かり品など、在庫でないものを在庫に含める(①)
- 実地棚卸でのカウントの際に、現物の数量よりも多い数量を記入する(②)
- 意図的に同じ商品をダブルカウントする(③)
- カウントの単位(個、Kg、1箱の入り数など)を操作する(④)
- タグ方式を採用している場合に、架空のタグを追加する(⑤)
- 実地棚卸の際にタグに記入した実地棚卸数量を、事後修正する(⑥)
(2)実地棚卸中、カウントに操作を加えるパターンの不正(前回のつづき)
上記②から⑤の不正は、「実地棚卸中、カウントに操作を加えるパターン」に分類できます。②から⑤の不正が行われると、いずれも「在庫の現物」と「カウント結果の記録(一覧表やタグ)」とが一致しないことになります。ここで次の【シーン1】をご覧ください。舞台となっているF社は前回までと同じです。
【シーン1】
F社の営業担当Yも在庫の水増しをしようと企んでいる1人ですが、営業担当Yは今回の実地棚卸のカウント実施者にはなっていません。そこで営業担当Yが考えた在庫水増し策の1つは次のようなものでした。
実地棚卸でのカウント作業が終わり、タグの回収作業が始まりました。
営業担当Y「俺が用意しておいた架空のタグを紛れ込ませちゃおう」
営業担当Yは、今回使用しているタグに似た用紙を何枚か手許に用意していました。1枚には商品Qが100個、もう1枚には商品Rが150個、もう1枚には商品Sが180個などと記入してあります。いくつかの商品の在庫をカウントしたように見せかけたタグを、回収中のタグの中にそっと紛れ込ませたのです。
当該不正が起きやすい状況と対処法
私が監査現場で経験してきたことも踏まえて考えてみると、当該不正が起きやすい状況として以下のようなことが挙げられます。実地棚卸の対象物である在庫自体の管理が適切になされており、かつカウント担当者が正しくカウントしたとしても、在庫水増しなどの操作を行い得る場面はまだあります。特に操作がされやすいのが、カウント結果を表す書類等に手を加えるケースです。ここで言う書類等とは、一覧表方式であれば一覧表、タグ方式であればタグが該当します。実地棚卸時にはこれらの書類等にカウント結果を記入していき、カウント終了後に回収され、これをもとに実地棚卸数量の集計がされることになります。
【シーン1】には営業担当Yが架空のタグを用意して、正しくカウントしたタグの中に紛れ込ませた様子が描かれています。では、この不正にはどのように対処したら良いでしょうか。
まずは、正規のタグ以外のタグを使用させないようにします。そして、万が一正規のタグ以外のタグが使用された場合はそれを発見できるようにしておくことです。読者の皆さんなら、どのような方法をとりますか。
実はタグに連番を付けて管理するという方法が効果を発揮します。ただし、単にタグに連番を付せばいいという話ではありません。タグの配布時や回収時において、それぞれ適切な管理が必要になります。
まず、タグの配布時の管理について、簡単な例を挙げて説明します。例えば、第1倉庫のカウント担当者Aには、NO.001から300までの番号が付されたタグ(計300枚)を配布し、第2倉庫のカウント担当者Bには、NO.301~500までの番号が付されたタグ(計200枚)を配布し、第3倉庫のカウント担当者Cには、NO.501~700までの番号が付されたタグ(計200枚)を配布します。予備で用意した未配布のタグ(NO.701~800)もあります。全部で何番から何番までのタグを発行したのか、これらのタグを誰に(どこの棚卸用に)配布したのかを実地棚卸の管理者は記録しておきます。
【図表2】タグの配布状況
| タグNO | 枚数 | 対象倉庫 | 担当 |
|---|---|---|---|
| 001~300 | 300枚 | 第1倉庫 | A |
| 301~500 | 200枚 | 第2倉庫 | B |
| 501~700 | 200枚 | 第3倉庫 | C |
| 701~800 | 100枚 | (予備) |
配布したタグについては、カウントに使用して現物商品に貼り付けたタグ、書き損じをしてしまったタグ、使用されなかったタグが出てきます。タグへの記入は修正ができないようにボールペンなどで行うのが原則ですが、万が一記入し間違えてしまった場合でも、タグを勝手に廃棄してはいけません。書き損じのタグとして、大きく✕印を付けるなどして無効なタグであることを明確にした上で、残しておきます。カウントの際に使用されなかったタグもその番号を明確にし、廃棄せずに残しておきます。
カウントに使用し現物商品に貼り付けたタグは、カウント担当者以外の者がカウントの正確性のチェックが済むまでそのままにしておき、チェックが終わってからすべて回収します。タグは2枚複写式になっているケースが多く、一旦2枚とも現物商品に貼り付け、チェックが済んだ後で1枚だけを現物商品からはがして回収します。
そして、実地棚卸の管理者はすべてのタグが回収されたことを連番で確認し、勝手に改ざんされることのないよう、すべてのタグを適切に管理します。こうした一連の管理を「タグコントロール」などと呼びます。
ここで【シーン1】を振り返ってみましょう。営業担当Yは、今回使用しているタグに似た用紙を何枚か用意しておき、正規のタグに紛れ込ませたわけですが、上述したようなタグコントロールが行われていると、こうした不正がされても発見できます。番号の付いていないタグがあれば正規のタグでないことが分かりますし、適当な番号が付いていれば、同じ番号のタグが2枚以上回収されていることになるので、非正規のタグの存在が明らかになることでしょう。
なお、在庫の水増しの反対に在庫数を少なくしようとして、使用済みのタグを廃棄しようとした場合には、適切なタグコントロールがされている限り、未回収のタグの存在が明らかになり、回収されるまで棚卸が終わらない事態になりかねません。
以上見てきたように、実地棚卸の際、タグの連番管理を行うことが不正対策として有効なのですが、これは在庫のカウントに限らず、他のさまざまな業務を行う際にも当てはまることです。実務上よく行われている連番管理を挙げてみると、受注の際の受注番号、発注の際の発注番号、売上代金回収の際に使用する領収証の番号、支払手形の番号、仕訳伝票の番号等々、さまざまです。
連番管理の効果を考えるために、仮に、領収証に連番が付いていない場合を考えてみましょう。ある担当者が現金を受け取り、相手に領収証を渡したものの、受け取った現金は自分の懐に入れてしまうといった不正が行われたとします。領収証の連番管理をしっかり行っていないと、領収証が発行されているのに経理部に入金がされていない状態にも気付かないかもしれません。領収証には予め連番を付しておき、領収証は番号順に使用するとともに、番号ごとに、どの相手先にいつ、いくらの領収証を発行したのかといった情報を記録しておきます。
また、支払手形の場合を考えてみましょう。振り出し前の支払手形の綴りには予め連番が付されています。仕入代金等の支払いのために支払手形を振り出して仕入先等に渡す場合には、番号順に振り出すとともに、番号ごとに、どの相手先にいつ、いくらの手形を振り出したのか、手形の期日はいつなのかといった情報を記録しておきます。これを手形記入帳などと言います。
万が一領収証や手形への書き損じをしてしまい、相手先に渡さなかったものについても、勝手に廃棄してはいけません。今後使用されることがないよう、✕印を付けた上で、書き損じてしまったものも残します。こうした連番管理をしっかり行うことで、気付かない間に領収証が発行されて売上代金を着服されることを予防できます。また、気付かない間に手形が発行され、簿外債務が生じ、ある日突然支払いが必要になるなどといった事態も予防できます。
以上、連番管理の効果のうち、不正の発見や予防に有効であるという点を中心に説明しましたが、この他にも、さまざまな効果があります。いくつか例を挙げれば、次のとおりです。
- 順番に並べることができる
連番が付いていなければ、順番に並べることもできず、整理整頓がしにくくなります。連番が付いていて証憑等が番号順に整理整頓されていれば、確認したい証憑等がある場合も、検索が容易になります。
- 番号の抜けや重複が分かる
連番が付いていなければ、抜けや重複があっても気付きませんが、連番が付いていることで、それに気付きやすくなります。その結果、上で説明した不正の発見・予防だけでなく、処理のミスにも気付きやすくなります。
- 資料間のリンク付け、他者との連絡がしやすい
連番が付いていなければ、資料間のリンク付けや他者との連絡がしにくくなりますが、連番が付いていることで、当該番号を使ってある資料と他の資料とのリンク付け(例えば、仕訳番号とその関連証憑のリンク付け)ができるので、業務効率なども良くなります。
| 経理の心得14 | 連番管理を取り入れることで業務の改善につながらないかを考えてみる |
3.おわりに ~連番管理の効果を意識しよう
今回は、実地棚卸を題材に、在庫絡みで起こりやすい不正のパターンの中から、前回に引き続き「(2)実地棚卸中、カウントに操作を加えるパターン」にスポットを当てて、問題点と対処法を考えてみました。特に今回は連番管理にスポットを当て、各種の連番管理とその効果などについて説明しました。次回は「(3)実地棚卸後、カウント結果に操作を加えるパターン」について、別のケースを取り上げて考えてみる予定です。それも併せて、是非、経理パーソンの方々には、ご自身の業務の参考にして頂ければ幸いです。