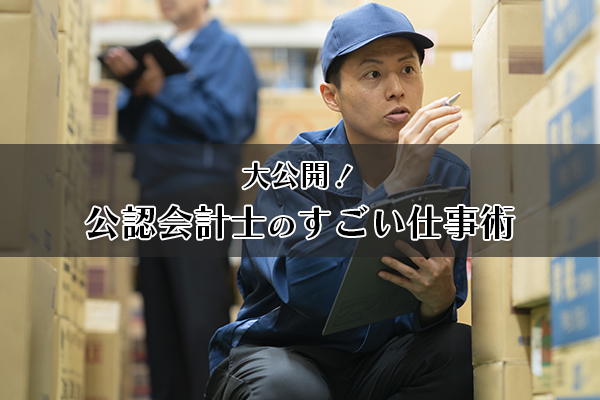前回は在庫絡みで起こりやすい不正の例を考えてみましたが、今回からは、不正が起こりやすいケースにおける問題点や対処法、そこから学べる経理の心得について話を進めていきます。
2.ケースで考える ~実地棚卸に関わる不正からの学び(その2)
まずは【シーン1】をご覧ください。【シーン1】
F社では多種の商品を取り扱っており、多種の商品在庫を保有しています。
ある営業チームは、期末が目前に迫っているにも関わらず、売上・利益のノルマ達成が厳しい状況にあり、営業担当Xは密かに実地棚卸での在庫水増しによって利益を水増ししようと画策しています。
まずは、前回取り上げた不正の例を振り返ってみましょう。以下のような6つの例が挙がっていました。
- 実地棚卸でのカウントの際に、現物の数量よりも多い数量を記入する
- 実地棚卸の際にタグに記入した実地棚卸数量を、事後修正する
- タグ方式を採用している場合に、架空のタグを追加する
- サンプル品・預かり品など、在庫でないものを在庫に含める
- 意図的に同じ商品をダブルカウントする
- カウントの単位(個、Kg、1箱の入り数など)を操作する
【図表1】実地棚卸の流れ
| (1)カウント前 | カウント対象の在庫を倉庫に入庫し、整理・保管 |
| ⇓ | |
| (2)カウント中 | 一覧表やタグをカウント実施者に配布 |
| ⇓ | |
| 実地棚卸で実際に在庫をカウントし、結果を一覧表やタグに記入 | |
| ⇓ | |
| カウント結果(一覧表やタグ)を回収 | |
| ⇓ | |
| (3)カウント後 | カウント結果の数量と帳簿の数量とを照合し、差異を調査 |
| ⇓ | |
| 帳簿数量に正しい数量を反映 |
上記6つの不正の例が、主として(1)から(3)のどの段階で行われる不正なのかという観点で整理してみると、以下のようになります。
- サンプル品・預かり品など、在庫でないものを在庫に含める(①)
- 実地棚卸でのカウントの際に、現物の数量よりも多い数量を記入する(②)
- 意図的に同じ商品をダブルカウントする(③)
- カウントの単位(個、Kg、1箱の入り数など)を操作する(④)
- タグ方式を採用している場合に、架空のタグを追加する(⑤)
- 実地棚卸の際にタグに記入した実地棚卸数量を、事後修正する(⑥)
仮に1人の営業担当者(「営業担当X」とします)が売上や利益のノルマを何としても達成しようと、上記のような不正を働こうとしたとしましょう。どんな状況だとこうした不正が起きやすいでしょうか。上記(1)から(3)のパターンごとに考えてみましょう。なお、今回は(1)についてのみ検討し、(2)と(3)については次回以降検討することとさせて頂きます。
(1)実地棚卸前、在庫自体に操作を加えるパターンの不正
上記①の不正は、「実地棚卸前、在庫自体に操作を加えるパターン」に分類できます。実地棚卸では在庫の現物をカウントしていくことになりますが、あらかじめ営業担当Xはその現物の中に余計なものを紛れ込ませておきます。カウント実施者が現物どおりにカウントし、カウント結果を一覧表やタグに記入したら、そのまま過大なカウントがスルーされてしまいかねません。当該不正が起きやすい状況と対処法
私が監査現場で経験してきたことも踏まえて考えてみると、不正が起きやすい状況として以下のようなことが挙げられます。1つは、保管中の在庫を営業担当Xが日常的に1人で自由に動かすことができる状況の場合です。例えば、普段から在庫保管場所の入出庫・保管管理者がいなかったり、施錠がされていなかったりすると、営業担当Xはいつでも容易にサンプル品・預かり品など余計な在庫を自社在庫のように紛れ込ませておくことができてしまいます。
対処法としては、現物の保管管理を1人で行っている場合は在庫絡みの不正がどうしても起こりやすくなってしまいますので、日頃から在庫保管管理に関して、営業担当と在庫保管管理者の業務を分離しておくことが考えられます。営業担当者自身が在庫の入出庫や保管管理などの在庫管理業務まで行わないようにし、当該業務は別の者が行うようにすることで、不正の発生を予防することになります。
これは在庫に限らず、さまざまな現物を管理する際にも当てはまります。企業には在庫以外にも現金、小切手、定期預金証書、受取手形、株券などさまざまな現物資産があります。これらの現物は、担当者1人では動かすことができないように、現物の保管管理者を別に置くようにしなければ不正の温床になりかねません。
これらを踏まえて、経理の心得として以下の点を挙げたいと思います。
| 経理の心得11 | 現物の保管管理者を別に置くことで、不正を予防する |
本来の帳簿在庫と実地棚卸のカウント数に差異が生じていても、その調査が行われないまま、すべてカウント数に置き換える処理をしている場合も、余計な在庫を紛れ込ませる不正に気付きにくくなります。例えば、サンプル品・預かり品など余計な在庫を自社在庫のように紛れ込ませた場合、その分だけ帳簿上の在庫数より実地棚卸でのカウント数が水増しされることになりますので、本来であれば異常な棚卸数量差異として顕在化すると考えられます。しかし、事後的なチェックが甘いと、いったん余計な在庫を紛れ込まされてしまったら後からそれに気付くことができなくなってしまいます。
したがって、対処法としては、実地棚卸後における棚卸数量差異(帳簿数量とカウント数量の差異)が商品等ごとにどれくらい発生しているのかをチェックし、大きな差異が発生しているなどの異常点があれば、その原因を追究するようにします。それにより、万が一何らかの不正が行われた場合でも、事後的にそれを発見できる手段を組み込むことができます。
これは在庫に限らず、さまざまな現物資産に関わる不正対策として有効です。企業には在庫以外にもさまざまな現物資産があることは上述したとおりですが、こうした現物資産には何かしらの不正リスクが常に存在していると考えられます。現物の存在を定期的に確かめ、管理する帳簿と現物とを定期的に照合し、差異があればその原因追究をおろそかにしてはなりません。それにより、万が一不正が発生した場合でも、事後的にそれを発見できるからです。
これらを踏まえて、経理の心得として以下の点を挙げたいと思います。
| 経理の心得12 | 現物と帳簿の差異は原因追究を行い、不正を発見できるようにする |
3.おわりに ~不正が起こりやすいケースにおける問題点や対処法を考えてみよう
今回は、実地棚卸を題材に、在庫絡みで起こりやすい不正の例を3つのパターンに整理し、「(1)実地棚卸前、在庫自体に操作を加えるパターンの不正」について、問題点と対処法を考えてみました。そこから次の2つを経理の心得として挙げさせて頂きました。- 現物の保管管理者を別に置くことで、不正を予防する(経理の心得11)
- 現物と帳簿の差異は原因追究を行い、不正を発見できるようにする(経理の心得12)
是非、経理パーソンの方々には、ご自身の業務の参考にして頂ければ幸いです。