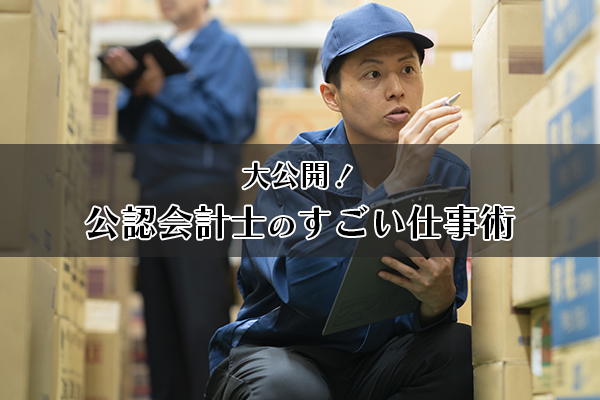今回は在庫絡みで起こりやすい不正の例を考えてみることとし、次回以降、不正が起こりやすいケースにおける問題点や対策、そこから学べる経理の心得について話を進めていく予定です。
2.ケースで考える ~実地棚卸に関わる不正からの学び(その1)
まずは、M社の実地棚卸での様子を描いた【シーン】をご覧ください。【シーン】(第48回の【シーン1】を再掲)
M社では多種の商品を取り扱っており、多種の商品在庫を保有しています。商品の受払を管理する継続記録は特に付けてはおらず、商品在庫の評価方法としては最終仕入原価法を採用しています。実地棚卸は1年に一度、年度の決算日に実施しています。
本日はM社の決算日で、期末時点の商品残高を固めるため実地棚卸が行われています。実地棚卸は、各営業チームが自分のチームの取扱商品について実施する体制になっており、数量のカウントは各チームとも営業担当者の中の1人だけで実施しています。
実地棚卸のカウントが終わると、各営業担当は営業チーム長に、実地棚卸結果のリスト(カウントした商品の数量の一覧)を提出しました。また、後日、商品ごとに最終仕入原価(単価)を乗じて、期末の商品在庫明細を作成しました。
商品在庫明細は各チーム長から管理部に提出されました。しかし、その後、数量のカウント誤りがあったと営業チームから連絡があり、何回かにわたって修正が行われました。
こうした一連の実地棚卸に関して、管理部スタッフは特に疑問を感じることはありませんでした。
(1)不正の動機
【シーン】には、M社が、「売上至上主義のワンマン社長の下、3つの営業チームは売上ノルマを達成しなければと必死に競い合っている」様子が描かれています。目標を掲げて達成に向けて施策を打っていくことは大事です。しかし、過度の売上至上主義と言えるような企業体質の場合は、一般的に不正を行おうとする動機が働きやすく、実地棚卸に関しても通常よりも不正が起きるリスクは高い状況にあると考えられます。私が監査現場で経験した中でも、こうした企業体質の場合は、不正に対して通常以上の注意を払っていました。不正を行おうとする動機が働きやすい状況の場合は通常以上に不正リスクに注意する必要があります。では、不正を行う動機となり得る状況にはどのようなものがあるでしょうか。いくつか例を挙げてみましょう。
【例】
- 社長等からの叱責をおそれて売上や利益のノルマを何としても達成したいケース
- 当期は売上や利益のノルマを達成済みなので、翌期に売上を後ろ倒ししたいケース
- 在庫を換金してお金を手に入れたいなどといった個人的な利益を得たいケース
- ミスで在庫を紛失・毀損してしまったなどといった失敗を隠ぺいしたいケース
このような状況の場合、当期の売上や利益のノルマが達成済みとなったら、逆に必要以上に当期に売上や利益を計上する必要がなくなります。本来であれば当期に計上すべきものを無理やり翌期のために残しておこうとする誘因も働きそうです。これが2つ目に挙げた「当期の売上や利益のノルマを達成済みで、翌期に売上を後ろ倒ししたいケース」で、翌期に売上を後ろ倒しするために在庫を操作するリスクも高まります。
この他、借金返済に充てたいとか、遊興費に使いたいなど、個人的な利益を得たいといった場合は、会社財産である在庫などを盗んで換金するなどの不正が行われるリスクとなります。また、失敗を隠ぺいするために不正が行われる場合もあり、自分に管理責任がある高価な在庫を紛失してしまったり、壊してしまったりといったことがあれば、それをごまかそうとして、在庫があるように操作するリスクもあります。
(2)不正の機会
不正をしようと思っても、実行が困難な状況ではなかなか不正は起きないでしょう。しかし、不正をしようと思ったら比較的容易に実行できてしまうような状況だと、現実に不正が行われてしまうリスクが高まります。以下では、上記「(1)不正の動機」で挙げた「不正を行う動機となり得る状況」ごとに、「こんなことをしたら実際に不正ができてしまうのではないか」ということを具体的に考えてみることにします。それを通じて、どんな状況の場合に「不正の機会」につながりやすいのかを整理してみようと思います。
①売上や利益のノルマ達成のために行われる在庫絡みの不正のケース
売上や利益のノルマをまだ達成できていない営業担当(あるいは営業部)が、ノルマを達成したように見せかけるために、在庫を操作するリスクがあります。それでは売上や利益のノルマ達成のために、在庫絡みでどんな操作を行う可能性があるでしょうか。私が監査での経験を踏まえて在庫操作の例を考えてみることにします。
典型的な例を挙げれば、目標利益をまだ達成できていない営業担当(あるいは営業部)が、在庫を水増しすることで、売上原価を少なく見せかけて利益を水増しするケースが考えられます。在庫単価を水増しする、不良在庫等を廃棄しない(あるいは評価減しない)など、「価格面」での操作を行うこともあります。ただし、ここでは特に実地棚卸でキモとなる「数量面」に着目し、そこでの操作を中心に見てみましょう。
実地棚卸で在庫数を水増しする方法の例として、以下のケースが挙げられます。
【例】
- 実地棚卸でのカウントの際に、現物の数量よりも多い数量を記入する
- 実地棚卸の際にタグに記入した実地棚卸数量を、事後修正する(タグの改ざん)
- タグ方式を採用している場合に、架空のタグを追加する
- サンプル品・預かり品など、在庫でないものを在庫に含める
- 意図的に同じ商品をダブルカウントする
- カウントの単位(個、Kg、1箱の入り数など)を操作する
【シーン】には、M社では「数量のカウントは各チームとも営業担当者の中の1人だけで実施」している様子が描かれていますが、この場合、「実地棚卸でのカウントの際に、現物の数量よりも多い数量を記入」しようと思えば、簡単に行うことができることでしょう。つまり、1人だけでカウントしている場合、通常よりも不正が起きる機会が多くなります。
また【シーン】には、M社では「一連の実地棚卸に関して、管理部スタッフは特に疑問を感じることはありませんでした」とあります。これは営業部の実施する実地棚卸に関して、管理部は営業部任せになっています。この場合、仮に営業部で在庫数量の操作を行っても、管理部でそれに気付く可能性は低く、通常よりも不正が起きる機会が多くなります。
さらに、「実地棚卸の際にタグに記入した実地棚卸数量を、事後修正する」ことができる状況の場合も、簡単に在庫数の水増しができてしまいます。例えば、実地棚卸数量の記入が鉛筆書きで行われていたり、カウントが済んで回収したタグが誰でも勝手に触れることができる状態で放置されていたりすれば、数量の事後修正が容易に行い得る状態であり、通常よりも不正が起きる機会が多くなります。
その他に列挙した在庫数の水増しの例についても、そのようなことが容易に行い得る状況だとすると、通常よりも不正が起きる機会が多くなります。
②個人的な利益を得たい、あるいは失敗を隠ぺいしたいケース
上記「(1)不正の動機」の中で、不正を行う動機となり得る状況の例として、3つ目に「在庫を換金してお金を手に入れたいなどといった個人的な利益を得たいケース」を挙げました。仮に在庫の保管場所に鍵がかかっていない場合、鍵がかかっている場合と比べて遥かに盗難などの不正が行われる機会は増えてしまいます。また、【シーン】には、M社が「商品の受払を管理する継続記録は特に付けてはおらず」という様子が描かれています。このような状況の場合、商品の受払に対するコントロール機能が弱く、実地棚卸に関しても通常よりも不正が起きる機会が多い状況にあります。
不正を行う動機となり得る状況の例の4つ目には「ミスで在庫を紛失・毀損してしまったなどといった失敗を隠ぺいしたいケース」を挙げましたが、現物の受払や保管の管理が甘いと紛失・毀損になかなか気付きません。
しかも、M社では「実地棚卸は1年に一度」だけですので、期中に不正が行われたとしても、それに気付く機会は限定的と言えそうです。
3.おわりに ~在庫絡みで起こりやすい不正の例を考えてみよう
今回は、実地棚卸を題材に、在庫絡みで起こりやすい不正の例を考えてみました。その際、「不正の動機」の面、そして「不正の機会」の面から整理し、何らかの不正の動機がある状況にあって、さらに不正を容易に行い得る状況、すなわち不正の機会が多い状況にあると、どうしても不正リスクは高まります。今回は、在庫絡みの不正の例を考えることに主眼を置きましたが、次回以降においては、不正が起こりやすいケースにおける問題点や対策、そこから学べる経理の心得について話を進めていく予定です。