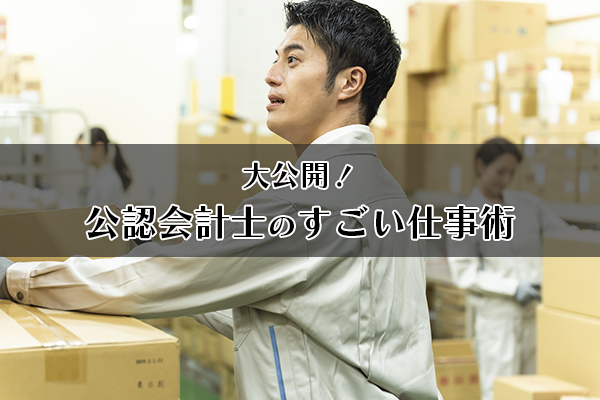2.ケースで考える ~正しく数えるための仕組みからの学び(その2)
まずは、M社の実地棚卸での様子を描いた【シーン】をご覧ください。【シーン】
Aさん「えーっと、この商品は確か倉庫のあの辺に置いてあったはずだ。行ってみよう。」
そして、次の商品は…。
Aさん「この商品はどこに置いてあったかな…。あれー、ないな…」
一覧表を頼りに現物に当たっていますが、どうやら倉庫内を右往左往することになっているようです。そうこうするうちに…
Aさん「あれっ、この辺りの在庫の山ってもう数えたんだっけ?」
在庫の山を見ても、カウント済みか否かがよく分かりません。
また、一覧表へのリストアップがもれてしまっている商品がいろいろあるようなのですが、一覧表頼みのAさんはそのことにまったく気付いていないのでした。
本稿では、カウントミスの原因となりそうなところを考えてみる際に、5W1Hを使ったアプローチを試みており、特に関わりの大きそうな3つ(「What」・「Who」・「How」)の観点に絞って検討を進めています。
今回取り上げる「How」は棚卸の「方法」、つまりカウントの方式などが該当します。
(3)方法に関して(「How」からのアプローチ)
実地棚卸でカウントミスが生じてしまうケースとして、棚卸の「方法」に起因するものがあります。棚卸の「方法(方式)」に着目して、どんなケースが想定されるか考えてみましょう。まったく棚卸を実施したことがないとなかなか考え付かないかもしれませんので、まずは、棚卸の方式について簡単に説明させて頂くことにします。①棚卸の方法
棚卸の方法自体は各社各様ではありますが、典型的には2つの方法に大別できるのではないかと思います。1つは「一覧表方式(リスト方式)」と言われる方法で、もう1つは「タグ方式」と言われる方法です。(A)一覧表方式(リスト方式)
一覧表方式と言うのは、棚卸対象の在庫の一覧表がまずあって、その一覧表に載っている個々の商品等について、それぞれ現物をカウントしていき、その数量を一覧表に記入していくといったイメージになります。【シーン】のM社が採用しているのはこの方式です。【図表1】一覧表方式のイメージ
| № | 商品コード | 商品名 | カウント数量 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
カウント担当者は、【図表1】のような一覧表に沿って、順番に個々の商品をカウントしていきます。そして、実際にカウントした数量を「カウント数量」欄に記入していくといった具合です。
(B)タグ方式
タグ方式と言うのは、【図表2】のようなタグ(棚卸原票)と呼ばれる用紙を発行し、実地棚卸の際に、商品名や数量など必要事項を記入して、カウントした現物に貼り付けていくイメージになります。予め商品コードや商品名などが記入されたタグを発行するようにして、実地棚卸の際は、数量やカウント実施者を記入するにとどめるケースもあります。すべての現物をカウントし終わった後に、すべてのタグを回収し、その後にタグに記入された数量を商品ごとに集計することになります。
【図表2】タグ方式のイメージ
| タグ | ||||||
| タグ№ 商品コード 商品名 保管場所 カウント実施者 カウント数量 etc. |
||||||
| タグ | ||||||
| タグ№ 商品コード 商品名 保管場所 カウント実施者 カウント数量 etc. |
⇒ | 実地棚卸時に個々の商品に貼り付けてカウント | ⇒ | カウント終了後に回収して、数量を集計 | ||
| ・ ・ ・ |
||||||
| タグ | ||||||
②それぞれのメリット・デメリット、並びに生じやすいカウントミス
上記「①棚卸の方法」で挙げた「一覧表方式」と「タグ方式」には、それぞれメリット・デメリットがあり、自社の棚卸に合致しない方法を選択してしまうと、カウントミスを生じやすくしてしまうおそれがあります。以下では、それぞれの方式について、メリット・デメリットを踏まえて、生じやすいカウントミスについて見ていきましょう。(A)一覧表方式(リスト方式)の場合
一覧表方式には、次のようにメリットがある一方でデメリットもあり、状況によってはカウントミスが生じやすくなる場合があります。商品等の情報(商品コード・商品名、場合によっては直近の帳簿数量など)が予め一覧表に記載されているため、実地棚卸では、実際にカウントした数量を記載していけば良いので、比較的効率的に実地棚卸を進めることができます。
一方で、現品にカウント済みなのかどうかの目印が付かないため、各商品等がカウント済みなのか否かが一目で(=現物を見ただけでは)分かりません。また、一覧表をできる限り実地棚卸日(の近く)の状態にまでアップデートしておく手間がかかります。
カウント済みか否かが一目で分からないということは、カウントをもらしてしまうおそれや重複してカウントしてしまうおそれが、通常よりも高いと言えます。例えば、実地棚卸のカウント後に現品を見たときに、すべての商品等をもれなくカウントできたのかを把握しづらいため、カウントもれがあっても気付きづらくなります。また、実地棚卸のカウント後に現品を見たときに、すべての商品等を重複せずにカウントできたのかを把握しづらいため、重複カウント(特に複数の保管場所に分散している商品等)があっても気付きづらいという面もあります。
一覧表に基づいて現物をカウントするというアプローチの場合、一覧表がアップデートされていないなどの理由で一覧表に載っていない商品等があったりすると、そのカウントがもれてしまうおそれも高くなります。【シーン】のAさんからもその様子が見て取れます。逆に一覧表に余計な商品等が載っていた場合、その商品等をいちいち探さなければならないと言ったことも生じかねません。しかも各商品にカウント済みか否かの目印がない場合、類似商品等を間違ってカウント(正しい商品としてもカウントしているとすると二重にカウント)してしまうかもしれません。
また、同じ商品等がいろいろな場所に点在している場合、仮に一覧表が保管場所ごとになっていないとすると、いずれかの場所の商品等について、カウントがもれてしまうなどのミスも起こりやすくなります。
それから、同じ商品等が点在している場合において、実地棚卸時に合計数量だけを一覧表に記載した場合には、場所ごとの現物の数量が記録されていないため、正しくカウントがされたかを後から検証しようとしても、検証は非常に難しくなります。
(B)タグ方式の場合
タグ方式には、次のようにメリットがある一方でデメリットもあり、状況によってはカウントミスが生じやすくなる場合があります。タグ方式では、現物にタグを貼り付けていくため、現物にタグが付いているかどうかを見ることで、カウントがもれている(タグが付いていない)商品等があれば、目で確認できます。そのため、カウントもれが生じにくくなるというメリットがあります。
また、同じ商品等にタグが2つ貼り付けられていれば、それも目で確認できます。そのため、二重カウントも生じにくくなるというメリットがあります。
同じ商品等が点在している場合でも、それぞれの場所で別のタグを商品等に貼り付けますので、保管場所が分かれていることに伴うカウントもれや二重カウントの発生が起こりにくくなるというメリットもあります。
ただし、タグに正しく商品名等を記入し、かつ正しく当該現物に貼り付ける必要があり、なかなか手間のかかる作業になるというデメリットがあります。タグ方式の場合、タグの管理が大変で、発行枚数が多くなると大変さが増します。また、一覧表方式のような一覧性がない点もタグ方式のデメリットの1つかもしれません。
上記のようなデメリットから、カウント作業の途中でミスが生じるおそれが高まります。
例えば、タグに記載の商品名と現物の商品とを取り違えてしまうと、別の商品をカウントしたことになってしまい、カウントミスにつながります。
タグ方式の場合、タグの管理が大変で、それが不適切だとカウントミスに直結します。例えば、現物をカウントし、数量を記入したタグを回収しもれてしまったらどうなるでしょうか。この場合は、その分だけ在庫が過少に集計されることになってしまいます。逆に、現物が存在しないのにタグだけ作成し、何らかの数量を記入したらどうなるでしょうか。その分だけ在庫が過大に集計されることになってしまいます。
また、タグ方式では一覧性がないという難点があります。一覧表方式であれば一覧表に載っているのにカウントが済んでいなければ、カウントもれに気付くことができます。しかし、タグ方式の場合は一覧性に欠けるため、商品等があるはずなのにカウントがもれ、かつ、タグの貼り付けがされていない商品等があることを見落としてしまうと、カウントもれに気付かないままとなってしまうおそれがあります。
③棚卸の方式の選択
上述したような一覧表方式・タグ方式等の特徴や、生じやすいカウントミスやカウントの効率性などを踏まえて、自社に適した方式を選択することになるでしょう。例えば、同一商品は1箇所にまとめて保管されていて、保管場所もほとんど動かないような場合は、概ね保管場所順に一覧表が作成できるのであれば、一覧表方式を選択した方が実地棚卸を効率的に進められるとともに、カウントミスも生じにくくなりそうです。
一方、現物の保管順と一覧表の記載順とを整合させることが難しく、一覧表方式でカウントを進めようとすると、どうしても倉庫のあちらこちらを行ったり来たりすることになるような状況であれば、一覧表方式は馴染まないかもしれません。このような場合は、一覧表方式よりも手間はかかりますが、タグ方式を選択した方が良いかもしれません。保管区域ごとにカウント担当者を分けたい場合で、保管区域ごとの一覧表の作成が難しいようであれば、タグ方式を選択した方が良いかもしれません。
また、選択した方式について、どのようなカウントミスが生じやすいのかを想定しながら、できる限りそうしたミスが生じないように運用を工夫するようにしましょう。例えば、一覧表方式では、新規取扱商品の掲載がもれないように注意する、保管場所の順番と一覧表の順番ができる限り整合するように工夫するなどといったことが考えられます。また、タグ方式では、できる限り必要事項は予めタグに記載しておくことで実地棚卸当日の記入の負担を軽減する、タグの発行・回収管理のルールを決めるなどといったことが考えられます。
以上見てきたように、「方法(方式)」に的を絞って考えてみることは実地棚卸のカウントミスの原因となる点の洗い出しに役立ち、より適した方法の選択につなげることができます。そして、これは実地棚卸に限った話ではありません。経理パーソンが携わるその他の業務でも、「方法」に関わる問題があることでしょう。そうした際にはそれぞれの方法の特徴をつかんだり、それぞれの方法で生じそうな問題を検討してみたりすることが有用です。
これらを踏まえて、経理の心得として以下の点を挙げたいと思います。
| 経理の心得10 | 選択できる方法に着目し、特徴をつかみつつ、生じ得る問題を考えてみる |
3.おわりに ~「方法」に着目してみよう
今回は、実地棚卸でカウントミスが生じる場面を想定しながら、その原因となりそうなところを、「方法」(How)に着目しながら考えてみました。実地棚卸の方法と言うと広範囲になってしまいますが、そのうち実地棚卸における典型的な2つの方式に絞って検討してみました。経理パーソンの方々が携わる業務において問題に直面した際、やみくもにその原因を探ったり、解決策を考えたりするのではなく、前回取り上げた「対象」や「人・組織」、そして今回取り上げた「方法」といった具合に、着眼点を絞ってみることが効果的であることも少なくありません。是非、経理パーソンの方々には、ご自身の業務の参考にして頂ければ幸いです。