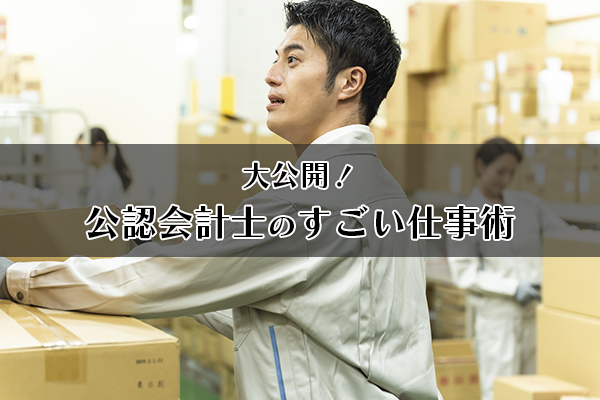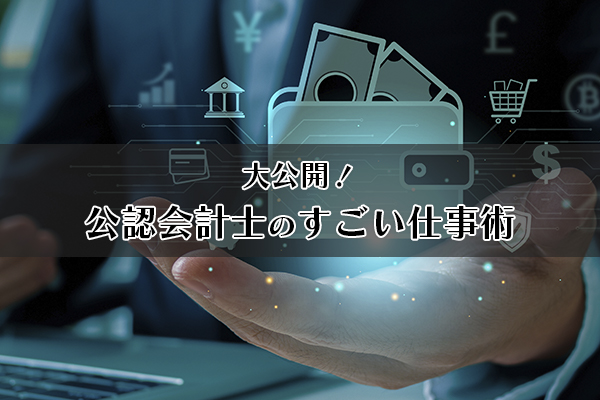2.ケースで考える ~現金実査との共通点からの学び
実地棚卸と現金実査との共通点・相違点
現金実査も実地棚卸も、主としてストック(残高)を固めるために行う手続きである点で共通しています。現金残高を固める一環としての現金実査、棚卸資産残高を固める一環としての実地棚卸は、対象資産は違うものの、どちらも残高を固めることが主目的です。こうした共通点から、「現金実査から学ぶ、経理の心得」の中でまとめた次の経理の心得は、棚卸資産の実地棚卸にも当てはまるのではないかと思われます。
【現金実査から学ぶ、経理の心得】
経理の心得1: ストックの視点を大切にする(第44回参照)
経理の心得2: 締めやすい状況を作る(第45回参照)
経理の心得3: 締めの前後に注意を払う(第45回参照)
経理の心得4: 効果の点から対象やチェック事項、実施方法を考える(第46回参照)
以下では、上記4つの経理の心得が実地棚卸にも当てはまるのかどうかを確認していきましょう。
| 経理の心得1 | ストックの視点を大切にする |
棚卸資産の場合、入出庫というフローを継続的に記録する帳票としては、棚卸資産受払帳が該当します。
継続的に入出庫を記録している場合であれば、帳簿上に入出庫数やそのときどきにおける帳簿上の在庫数の記録があるので、実地棚卸を行うことで、帳簿上の在庫数と実在する在庫数とを照合することができます。そのため、入出庫の記録に生じる誤りを効率的に発見できたり、在庫(現物)の管理に関する弱点が見えてきたりといった効果が期待できます(具体的な内容については、次回以降に説明する予定です)。
一方、継続的に入出庫(フロー)を記録していない場合もあります。これについて、まずは【シーン1】をご覧ください。
【シーン1】(前回のシーン1の一部を抜粋)
M社では多種の商品を取り扱っており、多種の商品在庫を保有しています。商品の受け払いを管理する継続記録は特に付けてはおらず、商品在庫の評価方法としては最終仕入原価法を採用しています。実地棚卸は1年に一度、年度の決算日に実施しています。
(以下、省略)
いずれにせよ、「ストックの視点を大切にする」という経理の心得は、実地棚卸にも当てはまると言えそうです。そして、実地棚卸でミスをせずに正しくカウントするためには、カウントミスをしにくくする工夫なども織り込むことが考えられます。準備段階での在庫の整理整頓であったり、自社の在庫にあったカウントの実施方法の選択(タグ方式や一覧表方式等)であったりということを、例として挙げることができます。
| 経理の心得2 | 締めやすい状況を作る |
締める日時はいつか、関係する社員等にはいつまでに何をしてもらうのか、などを明確に伝達した上で、実行することが必要であることは、「現金実査から学ぶ、経理の心得」の中で説明したとおりです。
実地棚卸の場合も、年度決算などの締めの際には、流れを止めやすくするための準備が必要です。むしろ、現金実査以上にその重要性が高いと言った方が良いでしょう。
ここで一例を挙げて考えてみます。仮に、実地棚卸中やその直前に棚卸資産の現物が移動してしまったとします。そうすると、移動元でも移動先でもカウントせずにカウントもれが生じてしまったり、逆に、移動元・移動先の双方でカウントしてしまい、二重カウントが生じてしまったりするおそれが高まります。そこで、実地棚卸中やその直前においては、棚卸資産現物の移動を止めるのが原則となります。
ただし、棚卸資産は、仕入・製造・在庫保管・販売など、関連する業務が多岐にわたり、実地棚卸も社内の購買部門・製造部門・倉庫部門・営業部門や経理部門など影響の及ぶ部署がどうしても多くなります。影響は社内にとどまらず、社外との調整が必要になることもあります。なぜなら、現物の移動を止めるためには、仕入先からの入庫を止めたり、得意先への出庫を止めたりといったことが必要になると考えられるからです。つまり、実地棚卸当日やその直前に納品されないように仕入先との間で調整したり、実地棚卸当日やその直前には納品をしないことを得意先に了解してもらったりすることが必要になってくるわけです。
また、実地棚卸でも、実施に先立ち、「棚卸実施要領」を作成し、関係者に周知徹底する必要があるでしょう。ただし、実地棚卸は現金実査よりも難易度が高く、棚卸実施要領に織り込むべき項目は多くなるはずです。機会があれば、その中身についても説明したいと思いますが、今回は割愛させて頂きます。なお、ご興味のある方は、経理規程や社内規程についての市販書籍などを参照されるのも良いでしょう。
いずれにせよ、「締めやすい状況を作る」という経理の心得は、実地棚卸にも当てはまることがお分かりいただけると思います。そして、「締めやすい状況を作る」ためには、これらの点を検討した上で、「棚卸実施要領」に織り込むなど、「実地棚卸の準備」を十分に行う必要があります。逆に、準備が不十分だと「締めやすい状況を作る」ことができず、実地棚卸の失敗につながりかねません。
| 経理の心得3 | 締めの前後に注意を払う |
現金実査での説明の際は、実査によって帳簿どおりの現金が実際にあるかがチェックされることになるため、何らかの事情で両者がズレているときなど、実査時になんとか辻褄を合わせようと、その付近では通常よりも操作が行われるおそれが高まるという例を挙げて、締めの前後に注意を払うべきことを説明しました。
棚卸資産は、仕入・製造・在庫保管・販売など、関連する業務が非常に多岐にわたります。したがって、現金の場合以上に、締めの前後において何らかの操作が行われるおそれが高く、こうした操作には多種多様なケースが考えられます。【シーン1】のM社の場合は、「売上至上主義のワンマン社長の下、3つの営業チームは売上ノルマを達成すべく競い合って」いる状況で、締めの前後において何らかの操作が行われるおそれが通常よりも高そうです。
いずれにせよ、「締めの前後に注意を払う」という経理の心得は、実地棚卸にも当てはまると言えそうです。そして、「締めの前後に注意を払う」ためには、これらのリスクについて管理部(経理部)などで検討した上で対策を講じるなど、「管理部が関与しながら改善していく余地」があるところです。逆に、管理部が関与しないまま実地棚卸を行うと、これらのリスクに対処できず、実地棚卸の失敗につながりかねません。
| 経理の心得4 | 効果の点から対象やチェック事項、実施方法を考える |
実地棚卸の場合は特に、「チェック事項」に関して、カウントすること以外に目が行っていないケースなどは問題があると考えられますし、「実施方法」に関して、実地棚卸を一人に任せてしまうケースなどは問題があると考えられます。
また、現金と違って、棚卸資産の場合は評価の問題があります。棚ざらしにしていて汚れがひどかったり、破損していたり、品質が劣化していたりなど、通常の販売ができない商品・製品があれば、廃棄したり、評価損を計上したりといった問題も出てきます。
さらに、現金と比べると、棚卸資産はカウントするのがはるかに難しくなります。このため、正確かつ効率的な棚卸ができるよう実施方法も工夫する必要が出てきます(具体的な内容については次回以降に説明する予定です)。
いずれにせよ、「効果の点から対象やチェック事項、実施方法を考える」という経理の心得は、実地棚卸にも当てはまると言えそうです。そして、「効果の点から対象やチェック事項、実施方法を考える」ということは、実地棚卸の準備段階で十分に検討し、棚卸実施要領に織り込んでおくことが必要ですし、所定の方法にしたがって実施されていることをチェックし得る体制も必要です。
3.おわりに ~現金実査からの学びを実地棚卸にも活かそう
今回は、現金実査と実地棚卸の共通点・相違点を踏まえて、「現金実査から学ぶ、経理の心得」の中でまとめた4つの経理の心得を、棚卸資産の実地棚卸にザックリとですが当てはめてみました。これらの心得は、実地棚卸にも当てはまりそうです。今回はザックリとした当てはめにとどめましたが、実地棚卸は現金実査と比べて難易度が高いため、現金実査よりも留意すべき事項がいろいろありますので、より具体的なところの説明は次回以降させて頂こうと思います。