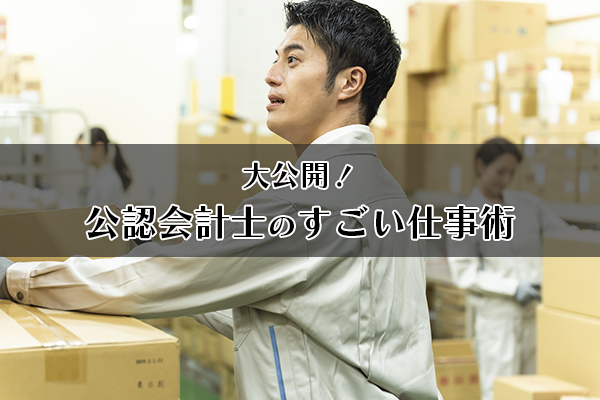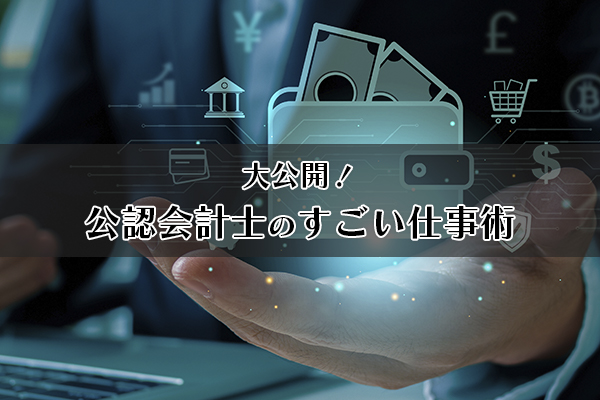これらの仕組みには、実地棚卸を実施する企業は当然のこと、実地棚卸を実施しない企業においても、経理パーソンが押さえておくべきさまざまな心得が織り込まれています。そこで今回からは、実地棚卸を題材にしながら、そこから学べる経理の心得についてお話ししたいと思います。今回は実地棚卸の概要を中心に話を進めることにします。
2.ケースで考える ~実地棚卸からの学び
まずは、経理スタッフの様子を描いた【シーン1】をご覧ください。【シーン1】
M社では多種の商品を取り扱っており、多種の商品在庫を保有しています。商品の受払を管理する継続記録は特に付けてはおらず、商品在庫の評価方法としては最終仕入原価法を採用しています。実地棚卸は1年に一度、年度の決算日に実施しています。
本日はM社の決算日で、期末時点の商品残高を固めるため実地棚卸が行われています。実地棚卸は、各営業チームが自分のチームの取扱商品について実施する体制になっており、数量のカウントは各チームとも営業担当者の中の一人だけで実施しています。
実地棚卸のカウントが終わると、各営業担当は営業チーム長に、実地棚卸結果のリスト(カウントした商品の数量の一覧)を提出しました。また、後日、商品ごとに最終仕入原価(単価)を乗じて、期末の商品在庫明細を作成しました。
商品在庫明細は各チーム長から管理部に提出されました。しかし、その後、数量のカウント誤りがあったと営業チームから連絡があり、何回かにわたって修正が行われました。
こうした一連の実地棚卸に関して、管理部スタッフは特に疑問を感じることはありませんでした。
(1)実地棚卸の目的
実地棚卸を行う目的はいろいろあるのですが、決算に際して行われる実地棚卸の目的は、何と言っても期末の在庫金額を正しく確定させることにあります。そのため、棚卸資産を保有する企業では、少なくとも年1回以上実地棚卸を実施します(半年ごと、四半期ごと、あるいは毎月実施する企業もあります)。在庫金額を確定させるためには、商品や製品ごとの在庫数量と在庫単価を確定させる必要があります。実地棚卸で現物の数量カウントを誤ってしまうと、正しく期末の金額を確定させることができなくなってしまいます。よって、実在する在庫数量を正しくカウントすることが実地棚卸の最重要ポイントになります。
(2)実地棚卸の全体像
上記「(1)実地棚卸の目的」の中では、数量を正しくカウントすることが実地棚卸の最重要ポイントであると説明しましたが、それ以外のところでも、正しく在庫金額を確定させる上で落とし穴になるところがあります。そのため、経理パーソンであれば、実地棚卸の全体像を押さえておく必要がありますので、ここでは実地棚卸の一連の流れを説明しておこうと思います。①在庫現物のカウント
実地棚卸では、上記「(1)実地棚卸の目的」でも触れたとおり、何と言っても実際に保有している商品や製品ごとに実際の在庫現物を正しくカウントし、在庫数を確定させることが必要で、実際の在庫を正しくカウントすることがとても大事です。実地棚卸ではカウントミスは致命的な問題となりかねないので、カウントミスをしにくくする工夫が必要となってきます。また、そのために必要な実地棚卸の準備や当日の実施方法、留意点などがあります。これらの点についての説明は、次回以降に譲ろうと思います。②帳簿と実数の照合
上記「①在庫現物のカウント」が済めば一連の実地棚卸業務が終わりでしょうか。そうではありません。在庫現物のカウント後にも重要な業務が残っています。実地棚卸で在庫を実際にカウントしたからと言って、実地棚卸終了後(例えば、翌日以降)に、各商品・製品の帳簿上の在庫数を実地棚卸でのカウント数にいきなり置き換えてしまう訳ではありません。商品・製品ごとに「帳簿上の在庫数」と、「実地棚卸でカウントした実際の在庫数」とを照合するという業務が入ります(受払の継続記録を付けていない場合には当該照合ができず、そのまま実地棚卸でのカウント数に置き換えることもあり得ます)。
③棚卸数量差異の分析
「帳簿上の在庫数」と「実地棚卸でカウントした実際の在庫数」を照合した結果、両者が一致していればいいのですが、差異が出ている場合があります。その場合は差異原因を調査することになります。差異原因にはさまざまなものがあり、それによってその後の対応が変わってきます。④棚卸資産の評価
実地棚卸では数量のカウントがメインにはなりますが、単に現物が存在すればいいという訳ではありません。現物は存在していても、モノが劣化していて売り物にならないなどと言うこともありますので、実地棚卸では棚卸資産の評価の視点も必要になってきます。上記①から④などの一連の手続きを経て、棚卸資産の数量と金額が確定するとともに、売上原価などの関連損益も確定します。
改めて【シーン1】を見て頂くと、M社の実地棚卸にはいろいろと問題がありそうで、管理部がもっと関与しながら改善していく余地がありそうですので、その辺りも次回以降説明していくことにしようと思います。
3.おわりに ~実地棚卸の概要をつかもう
今回からお伝えする「実地棚卸から学ぶ、経理の心得」は、私が財務諸表監査で実地棚卸を行う中で経験してきたものを念頭に、経理の心得として整理していきます。今回は実地棚卸の概要を中心に説明しました。実地棚卸当日の在庫数カウントは実地棚卸に関わる最重要部分ではありますが、実地棚卸に関わる業務の一部分なので、その後の業務なども含めて押さえておく必要があります。
次回以降、より具体的なところを説明させて頂くとともに、実地棚卸から学ぶことのできる経理の心得について取り上げさせて頂く予定ですので、参考にして頂ければ幸いです。