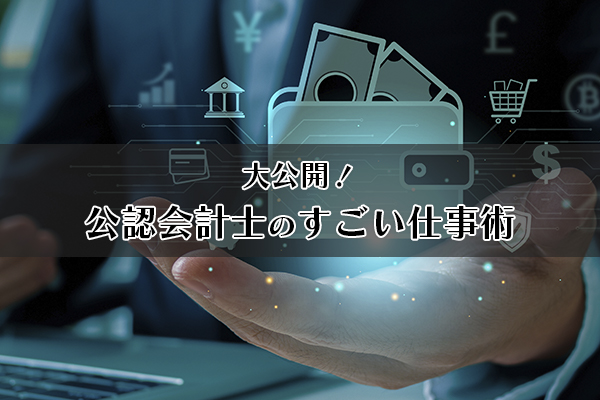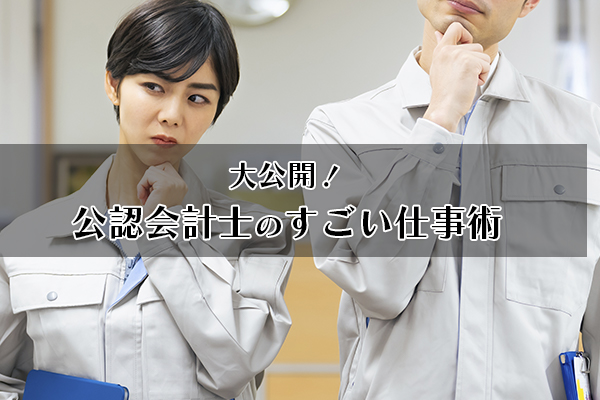現金実査を題材に、今回は4つ目の心得についてお話しし、3回連載の最終回とさせて頂きます。
2.ケースで考える ~現金実査からの学び(その3)
まずは、ある経理財務部での様子を描いた【シーン1】をご覧ください。【シーン1】
経理財務部長「Nさん、決算日を迎えたことだし、実査をお願いしてもいいかな?」
Nさん「分かりました。早速、取り掛かります」
しばらくして、Nさんから実査終了の報告を受けました。
Nさん「無事、実査は終了しました。特に問題はありませんでした」
経理財務部長「あれっ、もう終わったの?」
Nさん「金庫の中の現金、少ししかなかったのであっという間に終わりました!」
不安を覚えた経理財務部長は、久しぶりに自分でも金庫の中を確認してみることにしました。するとそこには……
経理財務部長「あれ?なんだこれは?まだ精算が済んでいない経費支出の領収書が何枚も保管されてるじゃないか!これって期末までに経費処理しておかないといけなかった分だぞ。印紙や切手のストックもこんなにあったのか……」
加えて、現金のカウントミスがあったことも分かりました。十数枚の1万円札の中に紛れていた5千円札をうっかり1万円札としてカウントしていたのです。
経理財務部長「実査を一人に任せてしまうのはリスクがあるな……」
| 経理の心得4 | 効果の点から対象やチェック事項、実施方法を考える |
①実査と聞いて、現金の実査しかしていないこと
【シーン1】で経理財務部長から現金実査をお願いされた経理スタッフのNさんは、金庫の中の現金を数えて早々に実査を終了しています。実査と聞いたNさんの頭には、現金実査のことしか浮かんでいなかったようです。しかし、実査と言っても対象は現金に限られません。例えば、金庫には、現金(通貨)の他にも、小切手(これも勘定科目で言うと現金ですが)や切手・印紙なども一緒に保管されていることが少なからずあります。また、これ以外にも換金性の高い資産がいろいろあり、これらも同時に実査することが考えられます。具体的には受取手形や手元保管の有価証券などです。
こうした資産は換金することが比較的容易であるため、実査のタイミングがずれるとその間に換金して、現金残高が多くあるかのように見せることも可能です。つまり、現金実査と同時に行うことが効果的です。
さらに、当座預金口座がある場合は小切手帳を保有しているはずですが、実査のタイミングで小切手帳がどこまで使用されているか、つまり最終使用の小切手番号及び未使用部分の最初の小切手番号を確かめておくことも考えられます。それによって、遡って振り出していたことにするなどの操作もできなくなりますので、現金実査と同時に行うことが効果的です。
つまり、これらのことから分かる経理の心得とは、「同時に実施した方が効果的な実査対象がないか考える」ということなのです。
②現金実査と聞いて、現金を数えることしかやっていないこと
【シーン1】でNさんは、現金を数え終わるや否や実査を終了しています。どうやら、(現金)実査と聞いたNさんの頭には、(現金を)数えることしか浮かんでいなかったようです。確かに現金実査自体は実際に現金をカウントして実在性を確かめるという作業です。しかし、現金実査で実際に現金を見るのですから、ついでにどんな状態で現金が保管されているのかも見ておくこともできますし、担当者がどんな台帳を使って現金の動きを管理しているかをチェックするチャンスでもあります。つまり、管理上問題となるようなところがないかといったことも同時に確かめた方が効果的です。
ですから、実査を行う人は、実査の際は金庫の中の状態などにも目を向け、管理上問題となるようなところがないかを確かめることも、その目的に含めることが考えられます。そうすれば、例えば、たくさんの領収書(経費精算が未了になっているもの)が保管されていたり、所定の経費精算伝票等によらずに出金したメモ書きが残っていたり、社長の個人的な現金が一緒に保管されていたり、入出金を管理するための台帳が記帳されないまま何日も放置されていたりなど、問題のありそうなところがあれば、それを見つけることもできるでしょう。
つまり、このことから分かる経理の心得とは、「同時に実施した方が効果的なチェック事項がないか考える」ということなのです。
③現金実査を一人に任せてしまったこと
【シーン1】には、Nさんが現金のカウントミスをしていたことも描かれています。一人に任せてしまうと、カウントミスをしていても気付きません。これを防ぐには、一人がカウントし、それを別の人がチェックするといったダブルチェックをかけるといったことも必要になります。【シーン1】には描かれていませんが、現金実査を入出金担当者自身が行うことのリスクもあります。現金の実査には、誤った金額で現金の受け渡しをしてしまっていないかなどを自己点検するために、現金の入出金の担当者自らが、日常的に行う現金実査もあり得ます。しかし、入出金担当者に任せきりにしておくと、処理誤りなどが起きても気付きにくいですし、現金の着服などの不正の機会につながるリスクも増します。こうしたことに対する牽制をかけるという意味では、入出金担当者以外の者(当該部署の管理者や他部署の人など)が実査を行わなければ、その効果は期待できません。場合によっては抜き打ちで実査を行うことも有効です。
現金実査に、入出金担当者等に牽制をかけるという意味を持たせるのであれば、それを達成できるようなかたちで実施者を選定したり、方法を決めたりするように留意する必要が出てきます。
つまり、このことから分かる経理の心得とは、「効果的な実施方法はないか考える」ということなのです。
このように、経理パーソンが何らかの業務を行うときに、効果の点から対象やチェック事項、実施方法を考えてみることは経理パーソンの心得の一つとなり得るでしょう。上の①から③に挙げたようなことは、より効果的に業務を進める上で押さえておきたい点です。
上の経理の心得4を踏まえて、経理財務部長は結局、【シーン2】のような見直しを行うことにしました。
【シーン2】(【シーン1】の続き)
しかし、経理財務部長が実査の実施をお願いする際、単に現金を数えるだけのものではないということや、実施上の留意点などをNさんに伝えていたかと言うと、全くそうではありませんでした。
経理財務部長は反省したのです。
経理財務部長「本来、効果的な実査となるよう、事前にきちんと考えていなければならなかったのに、それができていなかった。それに実査担当者にもこうしたことを伝えていなかった」
これを機に、経理財務部長は実査の重要性を再認識しました。決算時に行う実査について、実査対象範囲や、実査時にチェックすべき事項、具体的な方法などを見直すとともに、その手続書やチェックリストなども整備していったのでした。
加えて、決算時のみ入出金担当者以外の者に実査を行わせて、普段は担当者任せにしていた入出金管理についても、適宜担当者以外の者によるチェックがかかるように改めるとともに、特に期末前後で不自然な入出金などがないかにも注意するようになりました。
3.おわりに ~現金実査から学べる経理の心得を、業務に活かそう
今回までの3回で、現金実査を題材にして、そこから学ぶことのできる経理の心得をまとめてみました。そこでは、ストックの視点を大切にすること(心得1)や、締めやすい状況を作ること(心得2)、締めの前後に注意を払うこと(心得3)、効果の点から対象やチェック事項、実施方法を考えること(心得4)の4つを取り上げ、これを通じて、現金実査に限らず、経理パーソンが行う業務の中で持っていて頂きたい心得として整理してみました。年度決算・四半期決算・月次決算などの決算の締め、月々の売上代金や仕入代金の請求書の締め、月々の給与計算の締めなど、経理業務においては締めが付き物ですし、業務を進める上ではそれが効果的・効率的かが問われる場面も少なからずあるでしょう。
是非、読者の皆様が、こうした経理の心得を念頭に置きつつ、ご自身に関わる業務に活かして頂ければ幸いです。