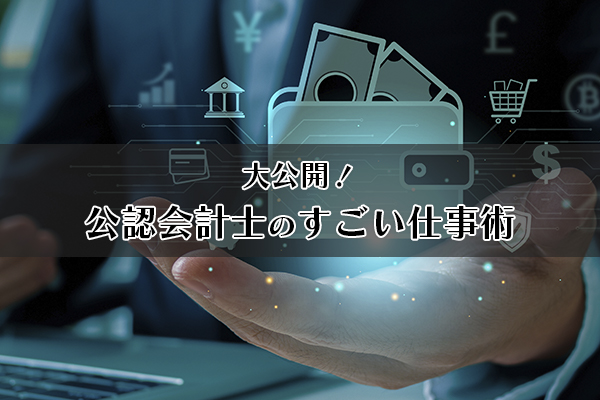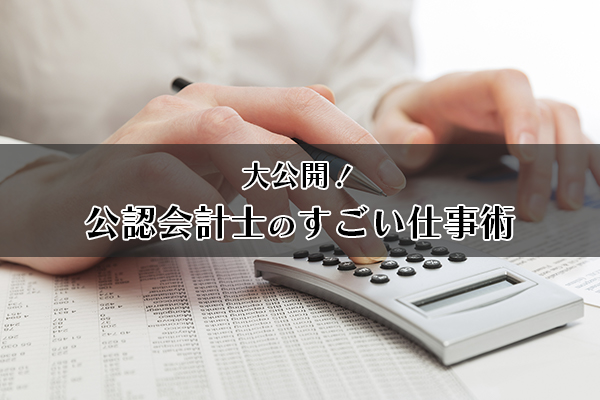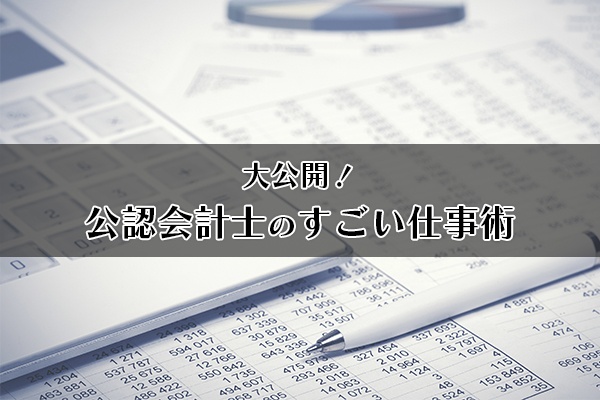今回も現金実査に関わるシーンを題材にしながら説明していきたいと思います。
2.ケースで考える ~現金実査からの学び(その2)
前回は、現金実査から学べる経理の心得の中でも、私が最も重要だと考えている「ストックの視点を大切にする」ことについて取り上げました。今回は、その他の心得から、「締めやすい状況を作る」ことと、「締めの前後に注意を払う」ことについて取り上げようと思います。| 経理の心得2 | 締めやすい状況を作る |
【ケース1】
−決算日
決算日を迎えたある日のM社でのこと。その日の業務時間も終わりに近づいたので、経理財務部長は自ら現金実査をすることにしました。経理財務部長は金庫を開けると、通貨の種類別に数量をカウントし、その結果を金種表(実査結果の報告書=20万円)に記載し、その場を離れました。
ところがしばらくすると、外出先から戻ってきた社員のAさんが経費精算のため経理財務部にやってきました。
社員A「今日の旅費交通費(2万円)を精算してもらえますか?」
入出金担当のKさんは金庫から現金を取り出し、Aさんに渡すとともに、帳簿上も決算日の出金として処理しました。
−翌日−翌期の初日
社員のBさんが売上代金(3万円)を持って、経理財務部にやってきました。社員B「昨日、僕が商品を販売した分の代金です。現金売りだったんで!」(本当は今日売り上げたんだけど…)
入出金担当のKさんはBさんから受け取った現金を金庫に納めるとともに、帳簿上も決算日の入金として処理しました。
−さらに翌日
経理財務部ではいよいよ本格的に決算作業に入りました。その過程で経理財務部長が、実査結果の報告書と、決算日の試算表の現金残高とを見比べていたときのことです。経理財務部長「あれっ、ちょっとだけ差異があるな…。でも、これ位なら問題ないか」
そして自ら、差額(1万円)を現金過不足(雑損)に振り替える仕訳処理をし、試算表の残高を実査額に合わせました。その結果、経理財務部長が想定していなかった問題が起きたのでした。
では、「締めやすい状況を作る」ということはどういうことなのでしょうか。
「締め」とは、流れているものを確定させるためにどこかで区切るといった意味で、経理業務の中でもいろいろな場面で締めが登場します。経理に関連する締めとしては、例えば、年度決算・四半期決算・月次決算などの決算の締め、月々の売上代金や仕入代金の請求書の締め、月々の給与計算の締めなどの他、現金実査の際の締めも挙げられます。
このように経理業務ではしばしば登場する「締め」ですが、締めやすい状況を作るということは、数字等を確定させやすい状況、誤りや不正が起こりにくい状況となるように準備することと言ってもいいでしょう。
以下では、決算時の現金実査の場合を使って、経理に関わる締めに際して締めやすい状況を作ることをご説明していこうと思います。
まず、現金の入出金取引を思い浮かべて頂くと、普段の日であろうと決算日であろうと、入出金が絶えず行われているのが通常で、その都度、現金残高も動いていきます。そうした中で決算日を迎え、決算日の現金残高を固めなければなりません。その一環として決算日には実査が行われます。
3月決算の会社であれば3月31日が決算日です。ただし、決算日の中の好きなタイミングで現金実査をしていいわけではなく、その日もうこれ以上現金が動かない状態になってから、現金実査をする必要があります。ところが、【ケース1】のように、経理財務部長がもうこれ以上は入出金がないと思ったとしても、締めがあいまいな状態になっていると、後から社員が経費精算にやってきて出金が生じてしまったり、営業担当が得意先から回収した現金を経理に持ち込んだりといったことが起きてしまいます。
これでは、せっかく現金実査をして期末時点の現金残高を確定させたつもりでも、問題が生じかねません。
【図表1】ケース1における実査額と帳簿金額の状況
| 項目 | 実査額 | ケース1の 帳簿残高 |
差額 | |
| 実査時点 | 20万円 | 20万円 | − | |
| ① | Aさんの経費精算(当期分) | △ 2万円 | 2万円 | |
| ② | Bさんの売上代金(翌期分) | 3万円 | △ 3万円 | |
| 小計(決算作業時) | 20万円 | 21万円 | △ 1万円 | |
| ③ | 経理財務部長が雑損計上 | △ 1万円 | 1万円 | |
| 合計(決算確定時) | 20万円 | 20万円 | − |
(注)①~③のいずれも、試算表上は当期に計上されている。
現に【ケース1】では、帳簿上の現金残高を実査額に合わせるために、差額(③の1万円)を現金過不足(雑損)として処理してしまいました。しかし、ここでの実査額(20万円)は、社員Aさんの経費精算による出金(①の2万円)が行われる前の残高です。また、ここでの試算表の現金残高は、社員Bさんが回収した売上代金の入金(②の3万円)が行われた後の残高になっています。
本来であれば、①の経費は当期に計上し、②の売上は翌期に計上すべきものです。こうした正しい処理がされている状態で現金実査をしていれば、帳簿上の現金残高と実査額がともに18万円だったはずであり、その結果、現金過不足は発生しておらず、③の雑損処理は不要であったはずです。しかし、「締め」が意識されていなかったため、正しい処理ができませんでした。
流れを一旦止めるためには、止めやすい状態を作るように準備する必要があります。例えば、「決算日の入出金は15時までとします」とか、「当期の仮払いの精算は決算日の前日までに済ませてください」とか、「不要不急の経費支出や仮払いは決算日の翌日以降に処理をお願いします」などと社員に予め周知しておくのです。そうすれば、強制的かつスムーズに入出金の流れを一旦止められます。
また、入出金を締め切って期末時点の現金残高を実査したということは、後から入出金取引を勝手に追加計上するのを防ぐという重要な意味があることも忘れてはならない点です。もしこれがいい加減だと、例えば後から次のような取引が計上されてしまいかねません。
(例)
- 売上が予算に未達だったので、架空(or翌期)の現金売上を当期に追加計上してしまう。
- 利益が出過ぎたので、架空(or翌期)の経費の現金支出を当期に追加計上してしまう。
以上見てきたように、締めの際には、流れを止めやすくするための準備が必要です。締める日時はいつか、関係する社員等にはいつまでに何をしてもらうのか、などを明確に伝達した上で、実行しましょう。
| 経理の心得3 | 締めの前後に注意を払う |
【ケース2】
Sさん「現金残高が現金出納帳の残高よりも5万円も少ない。紛失してしまったのか、誤って誰かに余計に渡してしまったのか……。どうしよう」
悩んだSさんは決算日の数日前、この5万円を一旦仮払金に振り替えました。翌期が始まってすぐに、それを取り消す仕訳処理をする予定です。
また、この件で悩んでいた結果、決算月の下旬に、金庫の現金を使って支払った小口の経費について、経費の仕訳処理をしないまま溜め込んだ状態になっていました。
Sさん「仕方がない。期末直前に処理未了のまま溜め込んでしまった分は、一旦、仮払金に振り替えておこう」
そして迎えた決算日。経理財務部長が実施した現金実査では、帳簿どおりの現金が金庫に保管されていたため、特に問題なく終了しました。
上記「経理の心得2 締めやすい状況を作る」では、「締め」について説明しましたが、締めがあることで、締めの前後(その付近)では何らかの操作が行われたり、誤りが生じたりしやすくなるといった問題も起こりがちです。分かりやすい例で言うと、当期の売上予算を達成できそうもないので、翌期に売上計上すべきものを当期に計上してしまったり、当期の利益が予算を下回りそうなので、当期に計上すべき費用を翌期に回してしまうといったケースです。
現金残高で言えば、実査によって帳簿どおりの現金が実際にあるかがチェックされることになります。そのため、何らかの事情で両者がズレているときなど、実査時になんとか辻褄を合わせようと、その付近では通常よりも操作が行われるおそれが高まるのです。
例えば、前日までは現金が私的に流用されていて、実査のときだけ一時的に現金を戻していただけかもしれません。あるいは、【ケース2】のように、帳簿よりも実際の現金が多額に不足していたため、一旦「仮払金」勘定などで処理して一致しているように見せておき、翌期が始まってすぐにそれを取り消しているだけかもしれません。【ケース2】のような仮払金への振替を行えば、すぐに気付くと思われるかもしれませんが、日々の業務の中で通常の仮払いとその精算が繰り返し発生するような場合、案外まぎれてしまいかねないのではないでしょうか。
したがって、形式的に帳簿残高と実際の残高が一致していることで安心してしまうのではなく、一致するように調整した結果なのかもしれないという点を頭に置き、その前後の部分に異常がないだろうかという視点を持っておくことが、経理パーソンとして大切です。
現金以外であっても同じような問題は生じ得ます。仮に、預金取引について帳簿上だけ何らかの処理を追加する操作をしていたとします。この場合、前後の部分に余計な取引が記帳されていたら、「預金の入出金の銀行記録」(通帳や当座照合表等)と「会社帳簿上の入出金記録」の間に齟齬が生じるので、例えば、決算日の前後数日における両者の記録を照合してみることは、異常をチェックする一つの方法になり得ます。
また、上述した予算未達に関連したケースとして、売上予算未達のために、一旦当期に架空の売上を計上し、翌期になってから売上取り消しの処理をして辻褄を合わせるといったこともあります。不自然なマイナス計上が翌期初の付近で行われていないかを見てみることも、前後の部分に異常がないかをチェックする一つの方法になり得ます。
このように、締めの前後では通常以上に何らかの操作が行われやすくなります。【ケース2】のような場合には、経理財務部長としては、決算日前後(前だけでなく、後もです)の現金出納帳で摘要や相手勘定などが不自然なものや、翌期早々に取り消された仕訳などに特に注意を払うことが大切だったと言えるでしょう。そして、こうした視点は他の経理パーソンにも通じることだと思います。
3.おわりに ~現金実査から経理の心得を学ぼう
前回は、「ストックの視点を大切にする」ことを、そして今回は、「締めやすい状況を作る」こと、「締めの前後に注意を払う」こと、を取り上げ、これらを通じて、現金実査に限らず、経理パーソンが行う業務の中で持っていて頂きたい心得として整理してみました。次回ご紹介する点と併せて、是非、読者の皆様が、こうした点を念頭に置きつつ、ご自身に関わる業務を行って頂ければ幸いです。