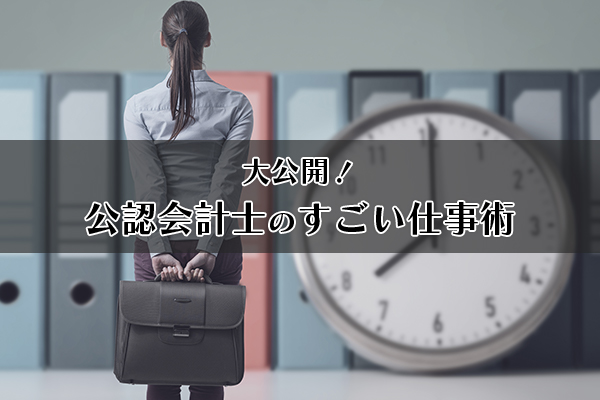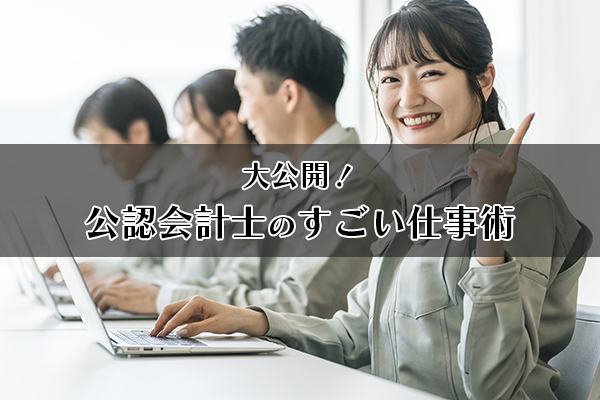「原価管理①」では、人の生産性アップにつながる原価管理の仕組み作りの第一歩として、「実績時間の把握」に絞って話を進めました。
「原価管理②~③」では、実績時間を把握した後のステップである、「実績時間の分析」に話を進め、実績時間が多いのか少ないのかを判断するためのモノサシが必要であること、そして、モノサシの一つとして計画値を挙げ、タイムリーかつ効率的に分析するための仕組みについても説明しました。
「原価管理④」では、実績時間の分析から対応策を検討する際に気を付けたいポイントについて説明しました。
「原価管理④」までは基本的に「時間」に基づく分析についてのみ説明してきましたが、「原価管理⑤~⑥」では、非財務数値である「時間」を、財務数値(決算数値)につなげて分析するための仕組みについて説明しました。
今回は、原価管理の連載(全7回)の最終回です。これまで説明してきた原価管理の仕組みが企業内にどんな変化をもたらすのかを人の生産性を中心に考えながら、原価管理の効果についてまとめようと思います。
2.ケースで考える ~原価管理が企業内にもたらす変化
ここまでの原価管理①から⑥を通じて、人が中心の組織における原価管理の仕組みについてひと通りの説明をしました。では、こうした原価管理の仕組みを導入することで、企業内にどんな変化がもたらされるのでしょうか。以下、これについてケースを使って考えていくこととします。まずは、ある監査法人での出来事を描いた次の【シーン1】をご覧ください。
【シーン1】(原価管理①の【シーン1】を再掲)
X監査法人では、監査の質を重視する一方で、採算確保も軽視しておらず、全メンバーが日々の出社時間と退社時間を記録し、月1回人事総務部門に勤務の実績時間の報告を上げています。
ところがここ数カ月、勤務時間が増えてしまっており、何とか手を打たなければなりません。そこで経営者は全メンバーに対して一斉に残業削減の指示を出そうとしているのですが……
(導入した原価管理の仕組みの概要)
・各従業員は月2回(前半分/後半分)タイムシートを作成する。
・タイムシートには日次でどの監査先業務にどれだけ時間を使ったかを記入する。
・従業員の給与水準に応じたランク別の業務単価を設定することで、「時間」は「コスト」(金額)にも換算される。
・タイムシートのデータは監査先ごと等適当な単位に集計され、法人本部等で分析される。
・監査チームの管理者は自分の管理下の業務について、メンバー別の実績時間やコスト等を把握できる。
・監査チームごとに年間業務計画を立案し、メンバー別・日別の予定業務時間、予定損益を設定する。
(1)見つかる課題の内容の変化
導入前: 大ざっぱになりがち
導入後: より具体的に
これに対して、業務を適当な単位に細分化し、業務ごとにかかった時間を把握することで、どの業務にどれだけの時間がかかっているかが分かると、それぞれ適正な時間なのか、かかり過ぎているのかを検討する材料にすることができます。それにより、どの業務に課題があるのかが見えやすくなりますので、生産性アップにもつなげやすくなるはずです。
ただし、時間を把握する際には注意が必要な点があります。せっかく業務ごとに時間を把握するとしても、業務の単位が粗過ぎると課題発見につながらなくなってしまいます。例えば、ほとんど経理業務だけを行っている人について、「経理業務」という単位で時間を把握するのだとしたら、大部分を占める「経理業務」にかかっている時間の内訳が分かりません。これでは時間を分析しても具体的な課題が見えてきません。この場合には、例えば、月次決算業務・年度決算業務・日常取引の記帳業務など、適当な単位に細分して設定するようにします。そうすることで、より具体的にどの業務の生産性に課題があるかなどが見えやすくなります。
また、課題のありそうな業務について、こうすれば時間を削減できるなどといった対策を検討し、今後の業務を進める際にはこのくらいの時間で行うことが適正だなどといったかたちで、業務予定時間を設定することもできます。
複数の業務をドンブリ勘定で見るのではなく、業務ごとにかけている時間やコストを見ることで、業務配分の見直し、業務のやり方の見直し、場合によっては業務の廃止などを検討する材料になります。例えば、管理者であれば、「それ程時間やコストがかかっていないと思ってある業務を実施してもらっていたが、こんなに時間がかかるならコスト対効果が見合わないのでこの業務は止めよう」などといった、業務の取捨選択を判断する上での材料になります。
(2)課題発見のタイミングの変化
導入前: タイミングが遅い
導入後: タイミングが早期化
月次で業務時間やコストの実績値の把握・分析を行えば、年に1回だけ把握・分析を行う場合よりも早いタイミングで問題が発生していることを認識できます。そして、分析に当たっては、実績値を単独で見るのではなく、前年同期の実績値(累計や単月)あるいは当年の計画値などのモノサシと比較することで、課題が見つけやすくなります。
そして、計画値を使う場合に大切なのが、どのような計画値と比較するかです。例えば、「年度合計の計画値しかない場合」と「月次に展開された計画値がある場合」の違いを考えてみましょう。前者の場合には「実績値が年度合計の合計値を超過して初めて問題として認識される」のに対して、後者の場合には「途中の段階でも、その時点までの計画値を超過していれば問題として認識できる」のです。
このようにして課題発見のタイミングが早くなれば、改善のための適切な対応策も早く講じることができるようになり、生産性アップにも早くつなげられるようになります。
1年を通じて行う業務の最終段階で課題が見つかっても、ほとんどできる策はありません。課題発見のタイミングをできる限り早め、より早く対策を講じられるようにできれば、対応策の幅も広がりますし、効果も大きくなりますので、それに適した仕組みを導入できるように検討しましょう。
(3)法人内の各階層に応じた分析が可能に
導入前: 状況把握・判断のための情報が不足
導入後: 階層に応じた情報の充実
そこで、ここでは大きく「①各個人レベル」と「②管理者レベル」の2つに分けて整理することにしましょう。
①各個人レベル
タイムシートがない場合、各個人はどの業務にどれだけ時間を使ったのかが分かりませんが、各個人がタイムシートを作成することでこれらの状況をつかむことができます。各個人は、業務ごとにかかった時間を確認することで、業務の効率性などを意識しながら、業務を進めていくことができ、必要に応じて業務のやり方の見直しなどを行っていくことができます。また、後述の「②管理者レベル」での分析を通じて課題が見つかれば、そのフィードバックを受け、今後の業務の見直しをすることもできるようになります。
②管理者レベル
タイムシートがない場合でも、管理者には、管理下のメンバーごとの残業時間や勤務時間合計などの情報は上がってきますが、それだけでは、残業や業務時間合計が多い・少ないといった点ばかりに目が行きがちです。それ以上の分析をしようと思ったら、個々のメンバーに状況をヒアリングせざるを得ません。
一方、各個人が業務別の内訳時間を記載したタイムシートがあるとどうでしょう。管理者は、管理下のメンバーごとの切り口から見れば、メンバーがどの業務にどれだけの時間をかけているのかが分かり、当該メンバーの働き方に関する課題の有無などの分析に使えます。
また、個人のタイムシートを個別に見るだけでなく集計することで、さらにさまざまな分析ができるようになります。例えば、業務ごとの切り口から見れば、ある業務について誰がどれだけの時間をかけて行っているのかも分かり、当該業務の進め方に関する課題の有無などの分析に使えます。
さらにランク別の業務単価を設定すれば、時間という非財務情報の分析だけでなく、コストという財務情報にして分析することもできますし、報酬が発生する業務では業務ごとの採算の分析にもつなげられます。
そして、もう一つ大事なことは、客観的な裏付けを持った上で判断できるということです。原価管理の導入前は、数値データが乏しく、管理者の判断も感覚的なものになりやすい面が見られます。しかし、客観的なデータに基づかずに、感覚的に対処しようとしても生産性アップのための適切な対応はできません。
業務ごとの内訳時間の把握や、ランク別の業務単価の設定等を行うことで、より詳細な数値データが充実し、また、時間などの非財務データに加えてコストなどの財務データが充実します。業務時間やコスト、採算などで問題が発生していないかなどを、客観的なデータに基づいて把握・分析した上で判断することができるようになります。
上記「(2)課題発見のタイミングの変化」で説明したような仕組みを導入すれば、実績値の分析をタイムリーに行うことができ、問題が発生している場合には、客観的なデータの裏付けを持ってメンバーにフィードバックできるとともに、対応策についてもより適切に協議できるようになります。
このように、分析したいことが異なると必要なデータも変わってきますので、どのような単位で集計したデータが必要になるのかを検討し、収集できる仕組みを用意しておくことが重要です。そして、各階層において当該データを分析し、課題が見つかればタイムリーに対応を図っていくことで、生産性アップにつなげていくことができるでしょう。
以上、原価管理の仕組みを導入したことで、導入前と比べて法人内に現れる主な変化について、(1)から(3)としてまとめました。
【シーン1】で描いたX監査法人も原価管理の導入で効果が現れ始めたようです。
【シーン2】
その結果、法人内の各個人、各監査チームの管理者、法人全体のそれぞれが、業務ごとの実績時間に基づく客観的なデータを活用して、時間やコスト、採算などをタイムリーに分析し、課題があればタイムリーに対応策を講じることができるようになり、人の生産性アップにつながり始めたのでした。
3.テレワーク環境等、働き方の多様化への対応に向けて
コロナ禍を経て、従来のオフィスワークから従業員宅でのテレワークが増加する等、働く環境に変化が生じ、今後も働き方の多様化が進んでいくことが見込まれます。そうした状況の中、原価管理の有無によって管理者による管理下の従業員の状況把握にも違いが生じると思われますので、最後にその点に少しふれておきたいと思います。原価管理が導入されていない場合、管理者がいないところで業務に従事する従業員の状況については、どうしても把握がしづらい面があります。一方、原価管理が導入され、管理下の従業員の業務内容とそれにかかった時間等のデータが分かると、管理者がいないところで業務を遂行する場合でも、状況把握がしやすくなる面があります。
ただし、テレワークが中心になってきた場合、業務にかかった時間を管理するよりも、設定した目標を達成できたかがより重要になってくることも想定されます。また、管理者から従業員の業務の進捗や成果物が見えにくくなる恐れもありますので、目標に対する進捗状況を共有したり、成果物を共有したりする(例えば、共有サーバーに作業ファイルを保存する)仕組みを整備することも検討する必要がありそうです。
いずれにせよ、働き方が多様化する中で、適切な仕組みがないと生産性低下につながりかねないので、適切な仕組み作りは今後ますます重要性が増してくると言えるでしょう。
4.おわりに ~原価管理で人の生産性アップにつなげよう
これまで7回にわたって、人の生産性アップにつながる原価管理の仕組みについて考えてきました。もちろん、原価管理の仕組みを導入すれば人の生産性が必ずアップするという訳ではありません。使い方を間違えてしまえば、時間やコストによる締め付けが強化され、それによってかえってモチベーションが下がり、生産性も悪化してしまうことだってあり得ます。しかし、使い方を誤らなければ、ご紹介してきた原価管理の仕組みによって、これまで十分なデータがそろっていなかったがために見落とされていた問題点に、新たに気付くこともできるでしょう。また、数値データの不足・数値の誤った分析等で事実誤認が生じ改善につながっていなかったところについて、より的確なデータの入手・分析が可能となり、的確な対応もできるようになるでしょう。
これまでご紹介してきた原価管理の仕組みを参考に、自社に合った仕組みにアレンジしていただき、生産性アップなどにつなげていただければ幸いです。