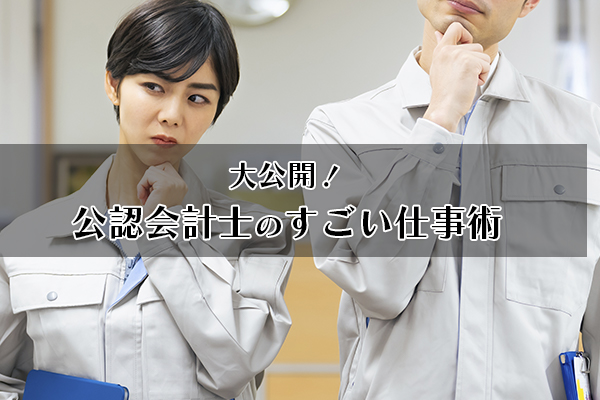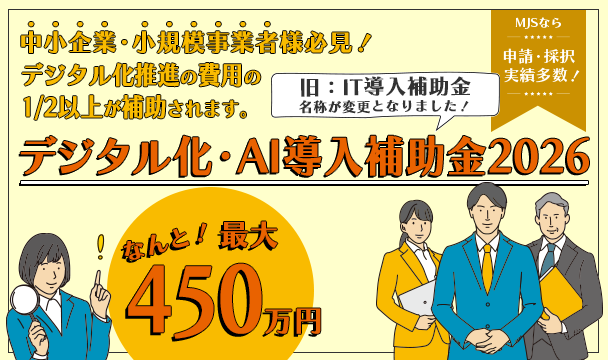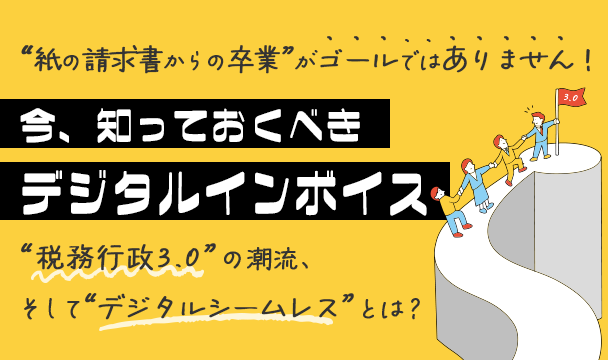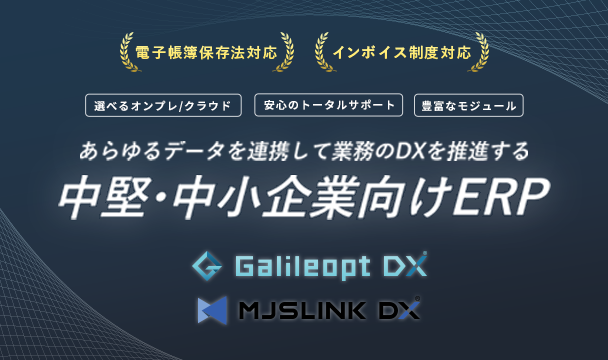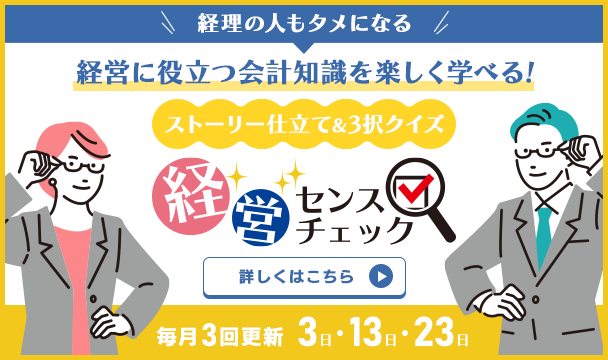本稿ではここまで、プロセス思考のステップのうち、問題の発生原因を特定していくステップに相当する4つのステップ、さらに、発生した問題を業務改善につなげていくためのステップについて説明してきました。
【1stステップ】ザックリとプロセスをつかむ
【2ndステップ】起こりがちな問題のパターンを押さえておく
【3rdステップ】起こりがちな問題をプロセスと紐づける
【4thステップ】問題が起きやすいプロセスが持つ弱点を押さえておく
【5thステップ】改善ポイントを整理し、改善案を検討する
今回は、【5thステップ】までのステップに関係してくるテーマとして、業務改善項目の評価を取り上げます。
2.ケースで考える プロセス思考のステップ(6thステップ)
発生してしまった問題を改善につなげるためには、ヒト・モノ・カネといった経営資源を使うことになりますが、資源には限りがありますので、限られた経営資源の中で効果を出すことを考えなければならないのも事実です。そのため、複数の業務改善項目がある場合には、その優先順位付け、すなわち業務改善項目の評価をすることが大事になります。そこで今回は、ケースを使いながら業務改善項目の評価について説明しようと思います。まずは次の【ケース】をご覧ください。
【ケース】
卸売業を営むS社には、仕入業務に関連して以下のAからDのような問題が発生しました(あるいは発生するおそれがあります)。
(問題A)発注書・納品書・請求書の未照合
全社共通の問題として、発注書と納品書、納品書と請求書の照合が十分にはされていないため、発注数と納品数の不一致に気づかないまま商品を受け入れてしまうという問題が多数発生している。
(問題B)納品書(紙)から納品データへの移行
当期から、既存の主要仕入先の1社が紙の納品書の発行をやめて、納品データでやりとりすることになり、S社では当該納品データに基づいて倉庫への商品入荷処理をすることとした。ところが、移行から間もないこともあってか、実際には納品された商品が、納品データからもれているといった取引が何件か発生していたが、S社ではそれに気づかなかったため、帳簿の在庫と実際の在庫にずれが発生している。
(問題C)スポット的な取引
スポット的に小口の取引をした仕入先から請求書が届くのが遅れ、仕入計上が遅れた。
(問題D)新規大口取引
来期は、従来の営業所に加えて新しい営業所を設置(倉庫を併設)することになっており、新設の営業所では大口の取引を新規仕入先と開始する予定である。
このケースでは、仕入業務に関していくつかの問題が発生している(発生するおそれがあるものも含む)状況にあります。複数の問題があり、それらについて業務改善していこうとするとき、ヒト・モノ・カネといった経営資源をそれ程使わなくても業務改善が進められるのであれば、あまり優先順位付けを気にする必要はないかもしれません。しかし、ある程度以上の経営資源を割かなければならないのであれば、改善項目の優先順位(特に重点を置いて対応すべき改善項目)を決める必要が出てきます。
それでは、優先順位を決める必要がある場面においては、どのような対応をしたら良いでしょうか。実は、こうした場面では、「①発生可能性」と「②発生した場合の影響度」の観点が活用できるのではないかと思います。これらの観点は、以前に本稿の「リスクアプローチ」の中で紹介したものです。今回のような業務改善項目の優先順位付けに当てはめるとすれば、今後も同じような問題が発生する可能性はどうなのか、同様の問題が発生した場合の影響度はどうなのかといった観点から検討してみると良いでしょう。
なお、これ以外にも改善の実現までに要する時間の長短や要するコストの大小などの観点もあり得るので、実際に適用する場合には、今回の【ケース】を適宜アレンジして頂ければと思います。
今回取り上げた【ケース】ではAからDの問題が起きていますが、これらに関する業務改善項目の優先順位を考えてみましょう。「①問題の発生可能性」の観点と「②問題が発生した場合の影響度」の観点から検討してみます。
「発生可能性」については、例えば、取引頻度が高かったり、処理の難易度が高かったりすれば、発生する可能性が高くなりそうです。「発生した場合の影響度」については、例えば、金額的な影響が大きかったり、問題が起きたときの対応に時間がかかったり、影響の及ぶ範囲が広かったりすれば、影響度は高くなりそうです。
(問題A)発注書・納品書・請求書の未照合
Aの問題については、発注書と納品書、納品書と請求書の照合が十分にはされていない状況であるわけですが、全社の仕入業務全般に関わっており、取引頻度が高く、このまま不十分な照合の状況が続けば今後も同様の問題が発生する可能性は高いと言えます。また、これは全社共通・各仕入取引共通の問題であり、影響金額・対応時間・影響範囲などから考えて、問題が発生した場合の影響度も高いと言えます。(問題B)納品書(紙)から納品データへの移行
Bの問題については、移行から間もなかったとは言え当期に何件か問題が起きており、今後も同様の問題が発生する可能性はそれなりにあると言えます。主要な仕入先であり金額的な影響はやや高くなる可能性があるものの、仕入先が特定されており、問題が起きている件数などから影響度は中程度と言えます。(問題C)スポット的な取引
Cの問題については、スポット的に行われた小口の取引であり、今後の発生可能性、発生した場合の影響度とも低いと言えます。(問題D)新規大口取引
Dの問題については、新設の倉庫のため発生可能性が低いとも言い切れないので中程度と想定できます。また、特定の営業所の倉庫に限った問題ではあるものの、大口の取引を開始する予定であるため、ここで問題が起きると影響度は高いと想定できます。以上のようなことから、問題AからDについて発生可能性と影響度を整理してみると、【図表】のとおりとなります。
【図表】 業務改善項目の優先順位付け
| 対象項目 | 発生可能性 | 影響度 |
|---|---|---|
| 問題A | 高 | 高 |
| 問題B | 中 | 中 |
| 問題C | 低 | 低 |
| 問題D | 中 | 高 |
これを踏まえて、「発生可能性」と「発生した場合の影響度」の観点から優先順位を考えてみましょう。
最優先で業務改善が必要なのは、発生可能性が高く、発生した場合の影響度も高い問題Aです。次いで優先度が高いのは、発生可能性は中程度ながら、発生した場合の影響度が高い問題Dです。その次に優先度が高いのは、発生可能性・発生した場合の影響度とも中程度の問題Bです。発生可能性・発生した場合の影響度とも低い問題Cについての改善はこの中では優先度が低いと言えます。
このように、取引の「頻度」や処理の「難易度」といった判断軸から「発生可能性」を評価したり、「金額」「時間」「範囲」といった判断軸から「発生した場合の影響度」を評価したりすることで、「発生可能性」や「発生した場合の影響度」の高いところを見極めて優先的に業務改善を進めることができます。そうすれば、些末なところに対応して肝心なところに対応できていないといった事態にならずに済みます。
3.プロセス思考のステップを踏んで、発生した問題を業務改善につなげよう
今回は、プロセス思考の中の5thステップまでのステップに関係してくるテーマとして、業務改善項目の評価を取り上げました。問題が発生してしまったときにそれを改善につなげるためには、ヒト・モノ・カネといった経営資源を使うことになりますが、限られた経営資源の中で効果を出すために、業務改善項目の優先順位付け(評価)をすることが大事です。そして、優先順位付けする際には、「問題の発生可能性」や「問題が発生した場合の影響度」といった観点から検討してみると良いことなどを、ケースを使って説明しましたので、具体的な業務改善を考える際の参考にして頂ければ幸いです。