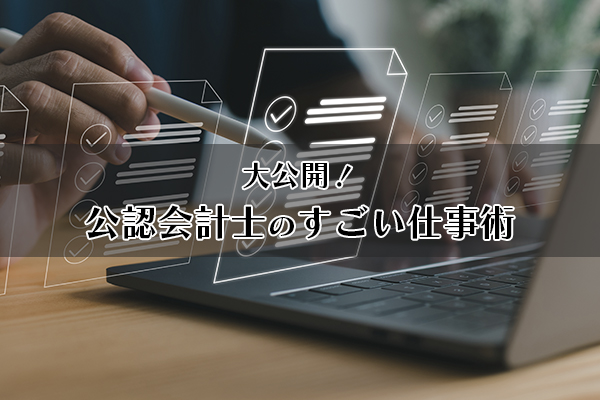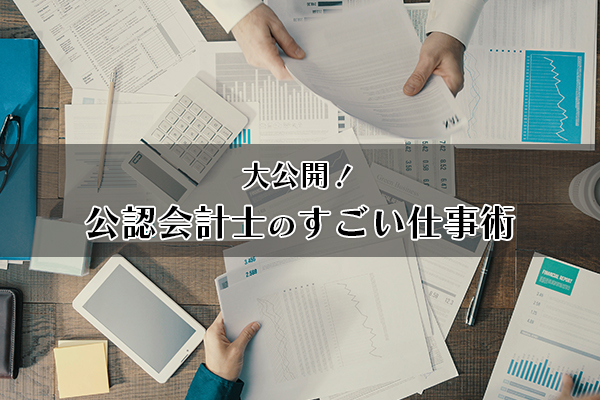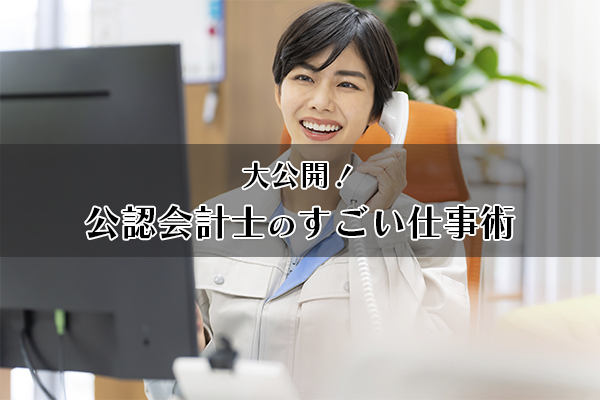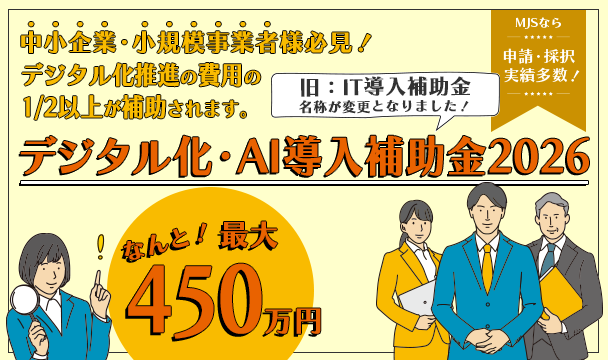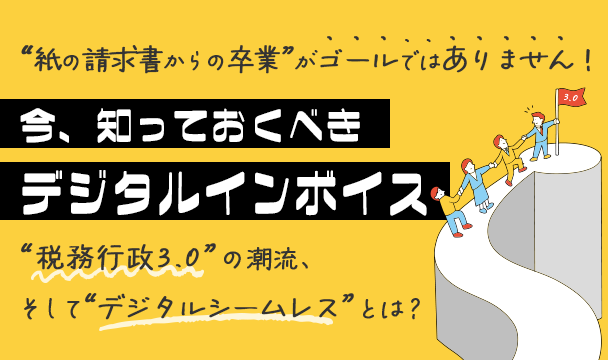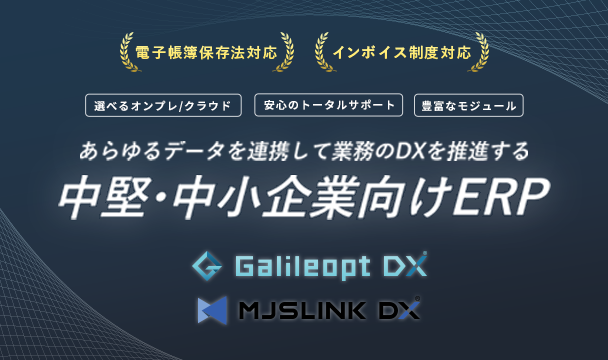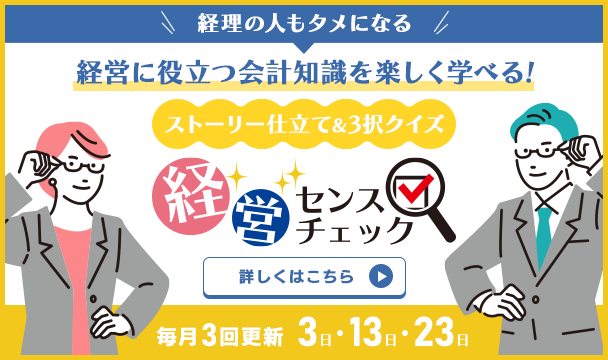本稿ではここまで、プロセス思考のステップのうち、中盤までの3つのステップについて説明してきました。
【1stステップ】ザックリとプロセスをつかむ
【2ndステップ】起こりがちな問題のパターンを押さえておく
【3rdステップ】起こりがちな問題をプロセスと紐づける
前回から、4thステップとして、「問題が起きやすいプロセスが持つ弱点を押さえておく」ことについて説明しています。
2.監査現場に学ぶ 問題が起きやすいプロセスが持つ弱点(その2)
4thステップ「問題が起きやすいプロセスが持つ弱点を押さえておく」については、私のこれまでの経験なども踏まえて考え、「仕組み」に弱点があることが多いこと、その中でも「(1)整備面の弱点」と「(2)運用面の弱点」の2つに集約できることを前回説明しました。そして、このうち1つ目の「(1)整備面の弱点」について考え、それは業務を行う上でのルールに不備があるということや、ルールの不備は4W2Hの観点を使って整理できることなどを説明しました。
【図表1】4W2Hの観点で分かるルールの不備
・When(時期に関するルール)
・What(元資料に関するルール)
・Who(人に関するルール)
・How(手段に関するルール)
___________________
・Why(趣旨の考慮)
・How Much(コスト対効果の考慮)
今回は2つ目の「(2)運用面の弱点」について考えていきます。
(2)運用面の弱点
業務を行う上での適切なルールがあったからといって、業務がうまくいくとは限りません。担当者がルールどおりに業務を行うとは限らないからです。そこで、ルールに従って業務が行われるような仕組みをプロセスの中に織り込むことが必要になります。逆にいうと、こうした仕組みがない、あるいは十分でないのであれば、それが運用面の弱点ということになります。
ここでの仕組みがどんなものかというと、担当者の業務がルールに従っているかをチェックするというものなのです。1つは担当者が自分でチェックすること、もう1つは他者がチェックすることです。以下、本稿では簡便的に、前者を「自己チェック」、後者を「他者チェック」といいます。
①担当者の業務がルールに従っているか担当者自身がチェックする仕組み(自己チェック)
ルールに従って業務が行われるためには、何よりも担当者自身がルールに従う必要があります。しかし、実際にはこれがうまくいっていないこともよくあります。そもそも大前提として、担当者自身にルールに従う意識がなければならないことはいうまでもありません。問題は、担当者がルールに従う意識を持っていてもそのとおりにならないことがあるということです。
どういうことかを発注業務を例に考えてみましょう。発注業務の場合において、発注担当者がルールに従って発注業務を行う意識を持っているとしても、日常的に何十件・何百件もの発注業務があると、その中の一部についてうっかりミスをしてルールからはずれた発注をしてしまうことは十分にあり得ることです。意識だけではうまくいかないということです。
そのため、このような場合に、ミスなどでルールからはずれてしまうといったことができるだけ起こらないようにしなければなりません。そこで考えられるのが自己チェックです。例えば、発注担当者の段階で、チェックリストなどを使って発注業務がルールに従っているかを自身でチェックすることは、その1つの方法になります。
②担当者の業務がルールに従っているか他者がチェックする仕組み(他者チェック)
自己チェックにより、できるだけ担当者自身の段階で問題の発生を食い止められるようになっているとよいのですが、自分が行った業務におけるミスなどに自分自身だけで気付くことは難しいことも事実です。そこで、担当者自身の段階で問題の発生を食い止められなかった場合でも、別途それに気付く仕組みがあることが重要になってきます。
これにはいくつかのパターンがあり、例えば以下のようなチェックをする仕組みが挙げられます。
(A)ダブルチェック
ダブルチェックというのは、同じ内容について複数人がチェックすることをいいます。
例えば、発注業務において、発注担当者が購入依頼書の内容を転記して注文書を作成し、その人自身で転記ミスがないか等をチェックするとともに、転記ミス等がないかを別の人にも再度チェックしてもらうケースが挙げられます。
ダブルチェックをすれば確かにミスなどは発生しにくくなりますが、二重に作業が生じることになるので業務負担が大きくならざるを得ません。
(B)クロスチェック
クロスチェックというのは、異なった視点などでチェックを行うことをいい、本稿では一般的なクロスチェックよりも広めにとらえることにします。
例えば、「個々の取引に対する担当部門管理者による承認」、「個々の取引を合計した全体に視点を置いたチェック」、「取引発生後のてん末に視点を置いたチェック」などが考えられます。発注業務における発注もれのチェックであれば、担当者が行った個々の発注取引について、1日分・1週間分・1か月分など発注の合計資料を管理者が確認して異常(発注が少な過ぎるなど)がないかをチェックするのが一例です。また、営業部門からの商品購入依頼書について、その後の納品状況をチェックする(これにより、購入依頼があったのにいつまでも納品がされないなど、発注もれがあれば分かる)といった例もあります。
(C)フォーマットチェック
フォーマットチェックというのは、入力ミスなどが起こりそうな項目について、所定の要件に合致しないものは入力できないように予め設定しておくことをいいます。
例えば、発注業務において、発注書の統一フォーマットを定めるとともに、ルールからはずれる発注入力ができないようにシステムでの制限をかける(金額欄に数値以外が入力できない、所定の仕入先以外を入力するとエラーメッセージが出るなど)といったことが考えられます。
また、ここまで挙げてきた各種のチェックについては、別の観点から整理することもできます。それは、予防のためのチェックなのか、発見のためのチェックなのかという観点です。本稿では、前者を「予防チェック」、後者を「発見チェック」と呼ぶことにします。
例えば、担当者が発注業務を行う際に、所定のルールから逸脱しないようにその都度チェックリストを使いながら業務を進めるといった場合は「予防チェック」です。発注担当者と別の人がダブルチェックした上で発注するということであれば、これも「予防チェック」といえるでしょう。1日分・1週間分・1か月分など発注の合計資料を管理者が確認して異常がないかをチェックするといった場合は「発見チェック」です。フォーマットチェックにより、所定の要件に合致しないものは入力できないように設定しておくのであれば、これは「予防チェック」といえるでしょう。
予防チェックだけでは、一度それをすり抜けてしまったミスなどにはなかなか気付くことができません。また発見チェックだけでは、(たとえ後から気付くとしても、)一旦はミスなどが発生してしまいますし、その分発見できずにすり抜けてしまう可能性はどうしても高くなります。従って、予防チェックと発見チェックをうまく組み合わせた体制になっているのがよいでしょう。いずれか一方のチェックしかない場合や、それらのチェックが粗い場合には、担当者の業務がルールに従っているかをチェックする仕組みが不十分であり、運用面の弱点がある可能性が高くなります。
なお、すでにお気付きの方もいらっしゃるでしょうが、担当者の業務がルールに従って行われるようにチェックする仕組み自体についても、ルール化していくことができます。そして、チェックをルール化する際には【図表1】にある4W2Hの観点に照らすことで、ルールの不備とならないように注意しましょう。
3.問題が起きやすいプロセスが持つ弱点を押さえておこう
前回と今回を通じて、プロセス思考の4thステップとして、「問題が起きやすいプロセスが持つ弱点を押さえておく」ことを取り上げました。問題が起きやすいプロセスにはどんな弱点があるのかを考えると、「仕組み」に弱点があることが多く、大きくは「(1)整備面の弱点」と「(2)運用面の弱点」の2つに集約できます。このうち今回は、「(2)運用面の弱点」について説明しました。ルールに従って業務が行われるような仕組みがないことが運用面の弱点ということになります。ルールに従って業務が行われるための仕組みとしては、「担当者の業務がルールに従っているか担当者自身がチェックする仕組み」(自己チェック)や「担当者の業務がルールに従っているか他者がチェックする仕組み」(他者チェック)があることを説明するとともに、他者チェックについては、ダブルチェック・クロスチェック・フォーマットチェックの3つを例に挙げて説明しました。さらにこれとは別に、予防チェックと発見チェックという観点についても説明しました。
こうしたチェックをする仕組みがないのであれば、そこには運用面の弱点がある可能性が高くなります。これらの観点に照らしてみると、仕組みの「運用面の弱点」と思われるところに気付きやすくなるはずなのです。