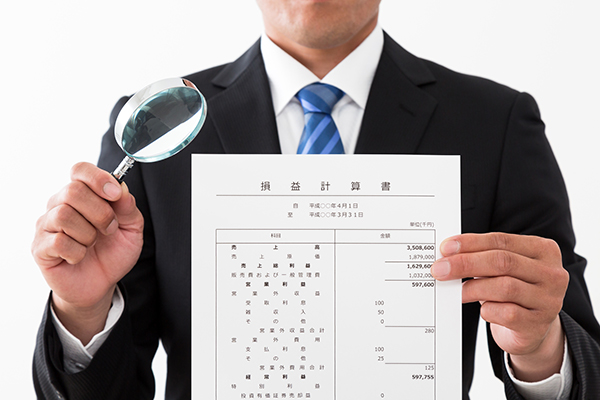企業における利益の基本ともいえる売上総利益は、売上から売上原価を差し引いて計算します。
この売上原価を算出するためには、棚卸資産の金額を正確に算定することが重要です。
今回は棚卸資産の評価方法のうち、移動平均法について解説します。
棚卸資産の評価と移動平均法
仕入れから販売までの一定期間、社内に留めておく在庫商品のことを棚卸資産と呼びます。
販売業など、仕入れと販売を繰り返す事業で売上原価を算定する際は、この棚卸資産がどのくらいの価値を持つのか確認することが重要になります。
売上原価は商品の仕入れや製造にかかった費用を指すものであり、売上総利益を算出するために必要な額です。
会計上で棚卸資産を評価する方法は、個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、売価還元法、最終仕入原価法など、数多く存在しています。
評価方法は事業や棚卸資産の種類・性質などを考慮して選択しますが、採用した評価方法は継続して適用しなければなりません。
なお、上記の通り会計上では棚卸資産の評価方法は選択することができますが、税務上では最終仕入原価法が原則的な評価方法となっています。
商品有高帳とは
商品有高帳は、商品の仕入れ・販売時における日付、数量、単価、金額、商品ごとの残高などを記録する帳簿で、在庫状況や売上原価を正確に把握するために作成します。
残高は、その棚卸資産の数量に払出単価を掛けることによって算出します。
ただし、同じ商品でも仕入れの時期などによって仕入単価は異なるため、単純に仕入単価を払出単価とすることはできません。
そこで使用するのが移動平均法による計算です。
移動平均法とは
移動平均法は棚卸資産の評価方法の一つで、仕入の都度、棚卸資産の平均単価として払出単価を算出する方法です。
移動平均法による平均単価の求め方は以下の通りです。
平均単価 =(受入棚卸資産取得原価 + 在庫棚卸資産金額)÷(受入棚卸資産数量 + 在庫棚卸資産数量)
受入棚卸資産は今回仕入れた商品のことであり、取得原価は1個あたりの仕入金額に数量を掛けたものを指します。
つまり受入棚卸資産取得原価は、今回の仕入れの総額ということになります。
在庫棚卸資産は以前仕入れたまま在庫となっている商品を指します。
ここから導き出された平均単価を払出単価として、商品有高帳の残高や売上原価を求めることができます。
総平均法との違い
移動平均法と似た方法に総平均法というものがあり、あわせて平均原価法と呼ばれています。
移動平均法では仕入れのたびに平均単価を算出しますが、総平均法では一定期間経過したタイミングで平均単価を算出します。
総平均法による平均単価の求め方は以下の通りです。
平均単価 =(繰越分を含む期間中の棚卸資産の取得原価の合計)÷(繰越分を含む期間中の受入棚卸資産数の合計)
移動平均法による計算例と商品有高帳への記入
ここからは具体的に、移動平均法による計算例と商品有高帳への記入例を解説していきます。
1カ月間、以下の通りに、先に仕入れたものから順に棚卸資産が払出された場合を確認してみましょう。
| 日付 |
内容 |
個数 |
1個あたりの仕入単価・売価 |
| 5/1 |
繰越商品 |
20個 |
100円 |
| 5/10 |
仕入 |
5個 |
120円 |
| 5/15 |
売上 |
5個 |
300円 |
| 5/20 |
仕入 |
10個 |
200円 |
| 5/25 |
売上 |
8個 |
400円 |
| 5/31 |
商品残高 |
22個 |
|
移動平均法による計算例
5月15日の売上時の払出単価
受入棚卸資産取得原価 = 5月10日の仕入商品個数 × 仕入単価
5個 × 120円 = 600
在庫棚卸資産金額 = 5月15日時点での繰越商品の個数 × 単価
20個 × 100円 = 2,000
受入棚卸資産数量 = 5月10日の仕入商品個数
5
在庫棚卸資産数量 = 5月15日時点での繰越商品の個数
20
払出単価
(600 + 2,000)÷(5 + 20)= 104円
5月25日の売上時の払出単価
受入棚卸資産取得原価 = 5月20日の仕入商品個数 × 仕入単価
10個 × 200円 = 2,000
在庫棚卸資産金額 = 5月25日時点での繰越商品の個数 × 5月15日に算出した払出単価
20個 × 104円 = 2,080
受入棚卸資産数量 = 5月20日の仕入商品個数
10
在庫棚卸資産数量 = 5月15日時点での繰越商品の個数
20
払出単価
(2,000 + 2,080)÷(10 + 20)= 136円
商品有高帳への記載例
| 日付 |
摘要 |
個数 |
単価 |
受払金額 |
| 5/1 |
前月繰越 |
20 |
100 |
2,000 |
| 5/10 |
仕入 |
5 |
120 |
600 |
| 5/15 |
売上 |
5 |
104 |
520 |
| 5/20 |
仕入 |
10 |
200 |
2,000 |
| 5/25 |
売上 |
8 |
136 |
1,088 |
| 5/31 |
残高 |
22 |
136 |
2,992 |
今回の例では、在庫の単価が100円、1回目の仕入単価は120円、2回目の仕入単価は200円と、徐々に仕入単価が高くなっています。
同様に、移動平均法による払出単価についても、1回目の売上時の払出単価は104円、2回目の売上時の払出単価は136円と高くなっていることがわかります。
このように、移動平均法では直近での仕入単価の状況も反映したリアルタイムの払出単価を算出することができます。
参考:総平均法による計算例
総平均法による払出単価は、その期間中すべての棚卸資産の取得原価と数量を使って算出します。
5月の払出単価
繰越分を含む期間中の棚卸資産の取得原価の合計 = 繰越商品の個数 × 仕入単価 + 5月10に仕入れた商品の個数 × 仕入単価 + 5月20日に仕入れた商品の個数 × 仕入単価
20個 × 100円 + 5個 × 120円 + 10個 × 200円 = 4,600
繰越分を含む期間中の受入棚卸資産数の合計 = 繰越商品の個数 + 5月10に仕入れた商品の個数 + 5月20日に仕入れた商品の個数
20個 + 5個 + 10個 = 35
払出単価
4,600 ÷ 35 = 131.4円
仕入単価は5月を通じて上昇していますが、総平均法による払出単価は一定です。
移動平均法で算出された払出単価と比較すると、1回目の払出単価はより高く、2回目の払出単価はより低く計算されていることがわかります。
なお、払出単価は5月末に計算するため、5月15日、5月25日時点での商品有高帳の払出単価欄は空白のままにしておく必要があります。
売価の情報を商品有高帳に記載することのないようにご注意ください。
移動平均法のメリット
仕入れのたびに計算を行う移動平均法のメリットは、リアルタイムで払出単価を把握できることにあります。
これは以下のようなケースで活用することができます。
- 仕入単価が期中に大きく値上がり・値下がりした際の損益計算
- 競争相手が多い商品や仕入単価が変動しやすい商品の取り扱い
- 市場の変化があった場合における販売戦略の検討
棚卸資産の評価額をタイムリーに把握できることは、状況が変動しやすい事業において正確な財務分析に役立ちます。
移動平均法のデメリットと対策
移動平均法のデメリットは、計算の手間です。
特に、取り扱う商品や仕入れの回数が増えると、計算がより複雑になります。
この場合、総平均法を利用し、棚卸資産の評価期間を一定期間で区切った方がいいこともあります。
ただし、このデメリットは会計ソフトを導入することで解消できることがほとんどです。
移動平均法、総平均法については基本的に対応している会計ソフトが多いので、こうしたITツールを活用して効率的に対応していきましょう。
※本記事の内容は掲載日時点での情報です。
**********
移動平均法は売上原価をタイムリーに把握できるため、実務でもよく利用されています。
棚卸資産の評価は会計ソフトで計算している場合も多いと思いますが、紹介した計算例を参考に計算の流れを理解し、自社に合った計算方法を選択できるようにしてくださいね。