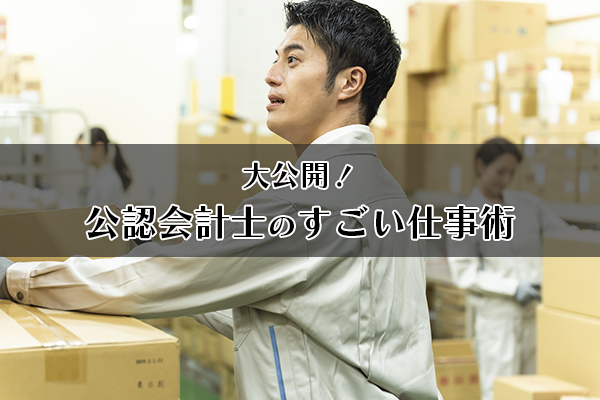そして前回からは、不正が起こりやすいケースにおける問題点や対処法、そこから学べる経理の心得について話を進めています。
2.ケースで考える ~実地棚卸に関わる不正からの学び(その3)
前回は、実地棚卸に関連したいくつかの不正の例を挙げた上で、主としてどの段階で行われる不正なのかという観点で次の(1)から(3)のように整理しました。また、このうちの(1)について、どんな状況だと不正が起きやすいのか、それに対してどう対処したらいいのかなどについて話を進めました。【図表1】実地棚卸での段階ごとの不正の例
- サンプル品・預かり品など、在庫でないものを在庫に含める(①)
- 実地棚卸でのカウントの際に、現物の数量よりも多い数量を記入する(②)
- 意図的に同じ商品をダブルカウントする(③)
- カウントの単位(個、Kg、1箱の入り数など)を操作する(④)
- タグ方式を採用している場合に、架空のタグを追加する(⑤)
- 実地棚卸の際にタグに記入した実地棚卸数量を、事後修正する(⑥)
(2)実地棚卸中、カウントに操作を加えるパターンの不正
上記②から⑤の不正は、「実地棚卸中、カウントに操作を加えるパターン」に分類できます。②から⑤の不正が行われると、いずれも「在庫の現物」と「カウント結果の記録(一覧表やタグ)」とが一致しないことになります。ここで【シーン2】をご覧ください。
【シーン2】(前回の【シーン1】のつづき)
営業担当Xは今回の実地棚卸でのカウント実施者の1人であり、F社では担当領域の在庫は担当者が1人でカウントすることになっています。
営業担当X「商品Pは実際の在庫は100個だけど、150個あったってことにしておこう」
そして、タグにはカウント数量を「150個」と記入したのですが、その様子を見ている人は誰もいませんでした。
当該不正が起きやすい状況と対処法
私が監査現場で経験してきたことも踏まえて考えてみると、当該不正が起きやすい状況として以下のようなことが挙げられます。1つは、【シーン2】のように、実地棚卸時に営業担当X自身が1人でカウントを実施している場合であり、この場合は容易に【図表1】の②から⑤のような在庫数量の水増しができてしまいます。【シーン2】で、現物の数量が100個なのに、一覧表やタグに150個あったものとして記入してしまったのは、このうちの②の不正です。
では、この不正にはどのように対処したら良いでしょうか。前回、不正対策としては、「予防」と「発見」の両方の視点が大事になることにふれましたが、この不正への対策にも通じることです。
まずは予防の視点から対処法を考えてみましょう。例えば、実地棚卸でカウント数を操作する動機が生じやすい営業担当者自身にはカウントを担当させず、第三者的な立場の人にカウントを担当させるという方法が考えられます。【シーン2】で言えば、営業担当Xではなく、管理部門の人にカウントを担当させるといった具合です。ただし、対象商品に対する知識が全くない者がカウントを実施すると、カウント誤りが生じたり、カウントがとても非効率になったりしてしまうことも考えられます。そのため、全くの第三者だけでカウントすることは不正対策としては有効だとしても、カウントの正確性や効率性の面では問題があります。
そこで、代替案として、対象商品に対する知識を持っている者がカウントを行いつつ、不正に対して牽制をかけるようにすることが考えられます。つまり、実地棚卸時のカウントを2人1組で実施するのです。
その場合のやり方としては大きくは2つあり、1つは「カウント係と記録係とに分けるやり方」であり、もう1つは「一緒にカウントと記録を行うやり方」です。
前者の場合は、カウントと記録を1人だけで行う場合と違って、不正なカウントと記録が行いづらくなります。これは職務分掌に近いかもしれません。ただし、この場合でも、カウント係のカウントの様子を記録係が適宜目視し、記録係の記録の様子をカウント係が適宜目視するなど、もう1人がおかしなカウントやおかしな記録をしていないかといった点に注意を払う必要があります。そうすることでお互いの牽制(=「相互牽制」)がかかるようになります。
後者の場合は、2人の目でカウントし、記録をしていくので、「ダブルチェック」に近いイメージで、牽制がかかります。
なお、2人1組でのカウントは人手を要するために非効率と思えなくもありません。しかし、2人1組でのカウントは、不正対策や正確性確保の対策になります。万が一実地棚卸後の棚卸数量差異の調査などでカウント誤りが多数見つかると、後日改めて在庫のカウントをし直さなければならないといった事態にもなりかねません。したがって、2人1組のカウントを行えば棚卸作業の手戻りが生じにくく、効率性にもつながると考えられる点は補足させて頂きたいと思います。
ここまではカウント担当者同士による相互牽制について見てきましたが、それに加えて大事なのが、カウント作業を第三者の視点でチェックすることです。例えば、カウント担当者が2人1組でカウントを実施している際に、管理部門の者などがカウントの状況を観察するようにしたり、サンプルベースで正しくカウントされているかをチェックしたりするようにします。こうすることでカウント実施者に対する第三者の観点からの牽制が働き、不正対策の効果を強めることができます。
以上見てきたように、実地棚卸の際、担当者1人で何でも自由に操作できてしまわないように「牽制をかける」ことが不正対策として重要であることが分かりましたが、これは在庫のカウントに限らず、他のさまざまな業務を行う際にも当てはまることで、経理パーソンの方々には意識して頂きたい点です。特にリスクの高い業務(不正が行われた場合の損失が大きくなる業務や、高頻度で不正が行われかねない業務)に対しては、1つの牽制では不十分なこともあるので、二重三重に牽制がかかる仕組みを検討してみることもお勧めします。
【図表2】牽制のイメージ
| 担当者 | ⇐ | 相互牽制 | ⇒ | 担当者 | ||
| ⇑ | ||||||
| 第三者の牽制 | ||||||
| 管理者や他部署 |
これらを踏まえて、経理の心得として以下の点を挙げたいと思います。
| 経理の心得13 | リスクの高い業務には、十分な牽制をかけることを意識する |