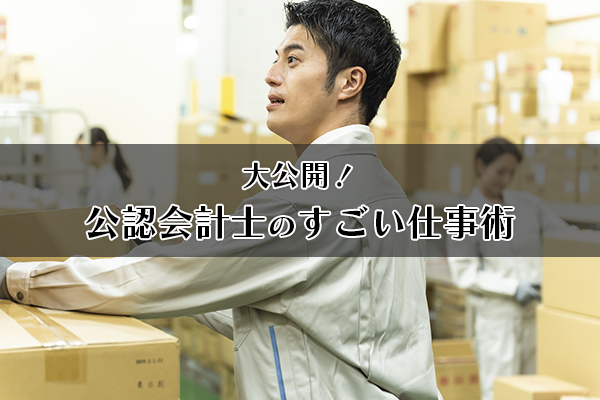今回は実施棚卸で特に重要な「正しく数える」ことにスポットを当て、正しく数えるためのさまざまな仕組みを取り上げるとともに、経理の心得として整理してみようと思います。
2.ケースで考える ~正しく数えるための仕組みからの学び
まずは、M社の実地棚卸での様子を描いた【シーン】をご覧ください。【シーン】(本連載第48回の【シーン1】の一部を修正の上抜粋)
実地棚卸のカウントが終わると、各営業担当は営業チーム長に、実地棚卸結果のリスト(カウントした商品の数量の一覧)を提出しました。
実地棚卸結果のリストは各チーム長から管理部に提出されました。しかし、その後、数量のカウント誤りがあったと営業チームから連絡があり、何回かにわたって修正が行われました。
一連の実地棚卸に関して、管理部スタッフは特に疑問を感じることはありませんでした。
カウントミスの原因となりそうなところを考えてみる際のアプローチ方法にはいろいろあるでしょうが、今回は5W1H(「What」・「Who」・「When」・「Why」・「Where」・「How」)の中から特に関わりの大きいと思われる3つ(「What」・「Who」・「How」)に絞って、そこに着目しながら検討を進めてみようと思います。
ここでの「What」は棚卸の「対象」、つまり商品や製品などが該当します。また、「Who」は棚卸に携わる「人・組織」、つまりカウント実施者やその他の関係者が該当します。そして、「How」は棚卸の「方法」、つまりカウントの方式などが該当します。今回と次回にわたって、この3点について見ていきます。
カウントミスの発生要因などを考える上で、まずは棚卸を実施しているときの状況を想定してみることが、アプローチしやすいのではないかと思いますので、今回と次回にわたって、この3点について見ていきます。
(1)対象に関して(「What」からのアプローチ)
実地棚卸でカウントミスが生じてしまうケースとして、棚卸の「対象」(商品・製品・原材料・仕掛品など。以下、単に「商品」あるいは「在庫」と言うこともある)に起因するものがあります。「対象」に着目して、どんなケースが想定されるか考えてみましょう。全く棚卸を実施したことがないとなかなか考え付かないかもしれませんが、例えば、以下のようなケースが挙げられます。実際には、過去に生じた事例なども踏まえて、各社で洗い出すことになるでしょう。【カウントミスが生じやすい例】
- 同じ商品があちこちに点在して保管されているケース
- 1箱に入れる商品の個数がそろっていない、あるいは入っている個数が同じ箱同士でまとまっていないケース
- 自社在庫と、預かり在庫(自社の在庫としてカウントしてはならないもの)とが、明確に区分されないまま一緒に保管されているケース
- 個々の商品の保管場所が決まっていないケース
- 棚卸実施中に在庫現物が動いてしまうケース
- カウント単位(数量or重量、箱単位or箱内の個数単位など)を取り違えてしまうケース
- 業務を細切れにせず、同じ業務はできるだけまとめる(経理の心得5)
- 業務を標準化して効率を上げる(経理の心得6)
- やるべきこと、やる必要のないことをしっかり区分する(経理の心得7)
(2)人・組織に関して(「Who」からのアプローチ)
実地棚卸でカウントミスが生じてしまうケースとして、棚卸に携わる「人・組織」に起因するものがあります。棚卸に携わる「人・組織」に着目して、どんなケースが想定されるか考えてみると、例えば、以下のようなケースが挙げられます。【カウントミスが生じやすい例】
- 1人だけでカウントするケース
- 在庫量に対してカウントする人数(合計)が少ないケース
- 普段、対象の商品と関わりがなく、予備知識がない人だけでカウントするケース
- 実地棚卸の役割分担や責任の所在などが明確でないケース
①1人だけでカウントするケース
これはカウント担当が全体として1人という意味ではなく、それぞれの担当者が担当区域などによって分かれて、個々の在庫をカウントする際には1人でカウントをしているという意味です。【シーン】では、数量のカウントは各チームとも営業担当者の中の1人だけで実施しており、カウントミスも発生しているようです。どうしても1人で作業をすればミスが生じやすく、またミスが生じたとしてもそれに気付きにくくなります。そこで、カウントする際は必ず2人1組になって実施するようにすることが考えられます。カウントする人とそれを記録する人、一次カウントする人とダブルチェックする人などといった形をとることで、正確かつ効率的なカウント作業を進めることができます。
②在庫量に対してカウントする人数(合計)が少ないケース
これは、全体としてカウント担当者が足りておらず、一人ひとりがカウントしなければならない在庫量が多過ぎて、作業負担が大きいといった状況です。このような状態では徐々に集中力も下がり、カウントミスが生じやすくなるおそれがあります。そこで、在庫量なども勘案し、十分なカウント担当者の人数を確保しておくようにします。場合によっては、2日がかりで棚卸を実施したり、ここ数日間は動く予定のない在庫は実地棚卸当日よりも前倒しでカウントを進めておくこともあり得ます。
③普段、対象の商品と関わりがなく、予備知識がない人がカウントするケース
これはどういうことでしょうか。「現物の数をカウントするだけなんだから、誰が数えたって結果は一緒でしょう」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実際にカウントしてみると意外とその差が大きいことに驚くかもしれません。在庫の保管責任などのない第三者的な立場の人だけでカウントすれば、保管責任者本人がカウントしたときよりも、確かにカウント結果の客観性は高まるかもしれません。しかし、他の類似商品と取り違えたり、1箱ごとの個数の違い(10個入りと20個入りなど)を見過ごしたり、日頃カウントすることに慣れていない分カウントミスをおかしやすかったりなど、カウントミスの生じる可能性が高まるケースが多いのではないかと思われます。作業の効率も悪い分、時間に追われてカウントミスを起こすこともあり得ます。むしろ、それなりに対象商品に知識のある人がカウントし、第三者がそれをチェックするという形にした方がカウントミスは生じにくくなったりするのです。【シーン】では、各チームとも営業担当者がカウントしており、その意味では取扱商品に対する予備知識などもあり、全くの第三者がカウントするよりも正確かつ効率的にカウントできる素地はあるかもしれませんが、上記①にも記載したとおり、1人だけでカウントしている点に難があると言えます。なお、【シーン】の実地棚卸でのカウント誤りには、単純なカウントミス以外に、実は不正なカウントがされているという面があるのですが、その点については別途取り上げる予定です。いずれにせよ、こうしたカウント誤りのリスクを勘案してカウント対象の在庫に応じて担当者を選任することが考えられます。そして、それらの担当者によるカウントの状況を第三者である経理部門や内部監査部門などが立ち会って状況を観察したり、担当者のカウントした結果が正しいかを適宜サンプルチェックしたりといった形にすることが考えられます。
④実地棚卸の役割分担や責任の所在などが明確でないケース
通常、実地棚卸には社内外のいろいろな関係者(購買部門、倉庫部門、営業部門、経理部門、取引先など)が参画します。それにも関わらず、それぞれの役割分担や責任の所在などがあいまいだったりすると、棚卸がうまくいかなくなるおそれがあります。【シーン】では、役割分担や責任の所在などが明確になっていないようで、実状としては実地棚卸がほとんど営業部任せになっており、一連の実地棚卸において生じている問題に対して、管理部では特に疑問を感じることなく、他人事のようになっている面があります。適切に実地棚卸が行われ、棚卸資産残高が正しく確定できるよう、管理部(経理部)は主体的に問題点の把握・改善に努める必要がありそうです。
以上見てきたように、「人・組織」に的を絞って考えてみることは実地棚卸のカウントミスの原因となる点の洗い出しに役立ちますが、これは実地棚卸に限った話ではありません。経理パーソンが携わるその他の業務でも、「人・組織」に関わる問題があることでしょう。そうした際には上記①から④に挙げたようなことも少なからず関係しており、問題をつかんだり、解決策を考える際のヒントになるかもしれません。
- 業務を1人だけで実施しているところを複数人で実施することで解決できないか(①参照)
- 業務に対する人員数は十分か(②参照)
- 業務に対する知識・能力はあるか(③参照)
- 業務の分担や責任の所在は明確か(④参照)
| 経理の心得8 | 業務を行う人の知識・能力など、「人」に着目して問題を考えてみる |
| 経理の心得9 | 人員数、業務の分担、責任の所在など、「組織」に着目して問題を考えてみる |
3.おわりに ~「対象」や「人・組織」に着目してみよう
今回は、実地棚卸でカウントミスが生じる場面を想定しながら、その原因となりそうなところを、「対象」(What)と「人・組織」(Who)に着目しながら考えてみました。例えば、「人」に関しては知識や能力などに着目することで、また「組織」に関しては人員数、業務の分担、責任の所在などに着目することで、さらに問題を深掘りすることができるのではないでしょうか。経理パーソンの方々が携わる業務において問題に直面した際、やみくもにその原因を探ったり、解決策を考えたりするのではなく、「対象」や「人・組織」といった具合に着眼点を絞ってみることが効果的であることも少なくありません。是非、経理パーソンの方々には、ご自身の業務の参考にして頂ければ幸いです。